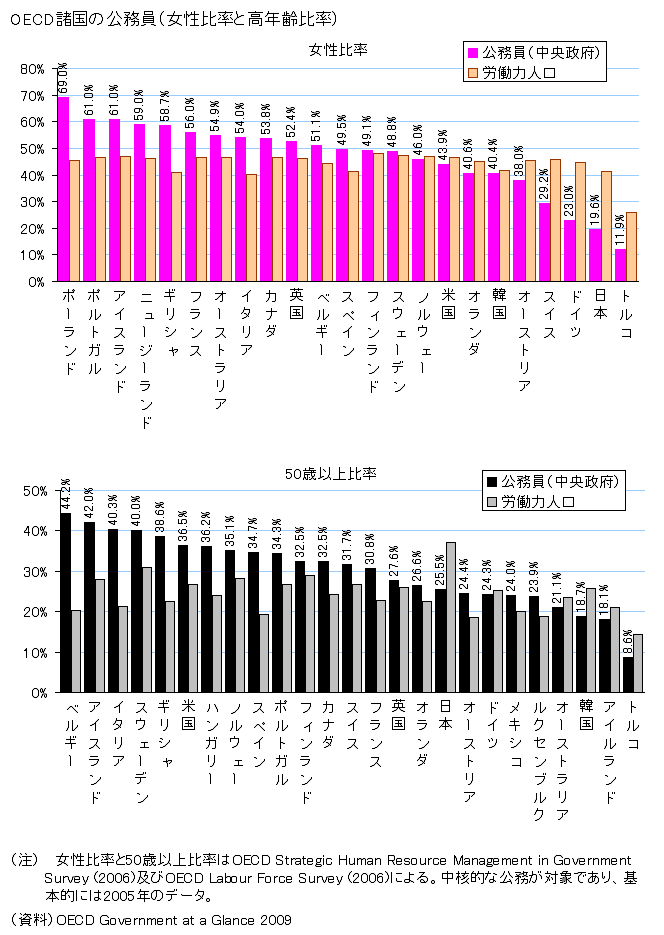
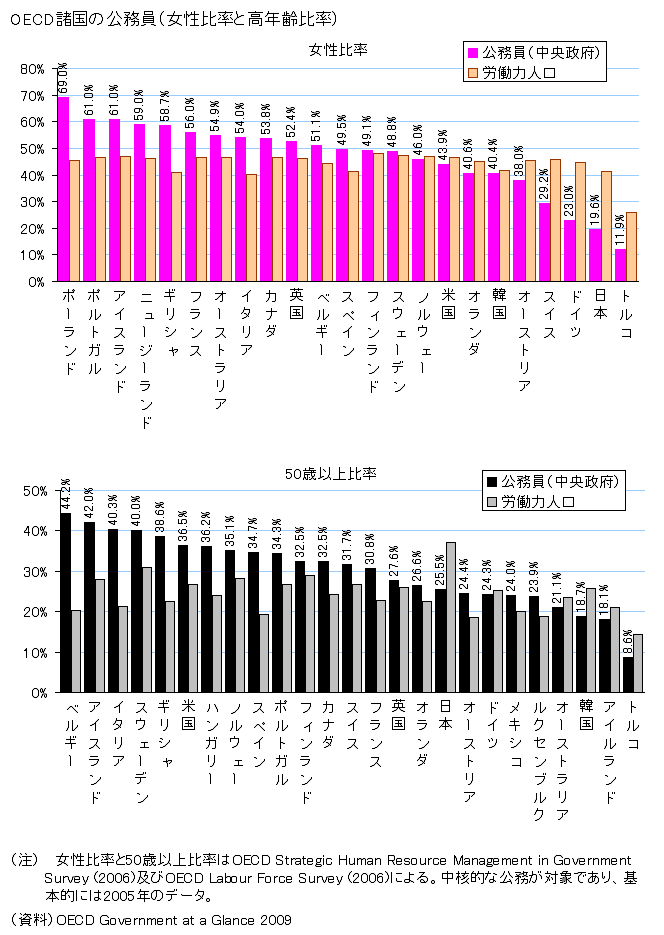
ここでは、同じくOECDデータにより、公務員(中央政府)の女性比率と高齢比率を図録にした(女性比率データ、高齢比率データ)。 女性比率については、スイス、ドイツ、日本、トルコでは中央政府雇用者に女性が少ない。これは、こうした国での中央政府の職責の違いにもよっている。例えば、ドイツでは多くの中央政府雇用者がもともと女性比率の小さな防衛職と警察職であることが影響している。非中央レベルの雇用者を入れると政府労働力の52%は女性である。 韓国のような例外を除き、OECD全般に公務員の高齢化が進んでいるのは、多くの国で1970年代から1980年代中頃までに進んだ急速な公務員の拡大が1990年代にかけて凍結されたからである。 日本の場合は、50歳以上の高齢比率が25.5%とOECD諸国の中では低い方であり、また、労働力人口一般の50歳以上比率が目立って高い割には公務員の同比率が低い点も特徴である。公務員の天下りが早期退職を促してこうした結果となっている可能性がある。天下り先まで含めた高齢比率が知りたいところである。なお、民主党政権が掲げている天下り全面禁止が天下り以外での民間再就職なしで進み、定年までの就労率が上昇すれば、日本の公務員の相対的な平均年齢の若さは維持されないであろう。 自衛隊員の場合は民間就労が制約され他国と比べ高年齢化が進んでいる点については図録5221参照 OECDの報告書(Government at a Glance 2009 日本では、公務員の定年までの就労継続と総定員抑制に圧迫され、2011年から中央官庁の新規採用が抑制される(2011年度の一般職国家公務員の新規採用を2009年度比で約4割減を2010年5月21日閣議決定)。つまり、OECD諸国とは異なり、これから職員の高年齢化が進むわけである。上で指摘されているOECD諸国における公務員の高齢化のメリット、デメリットは逆に読み替えることができる。例えば、民間セクターにとっては新規採用が相対的に有利となる。 女性比率を取り上げた国は23カ国であり、具体的には、比率の高い順に、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、ニュージーランド、ギリシャ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、英国、ベルギー、スペイン、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、米国、オランダ、韓国、オーストリア、スイス、ドイツ、日本、トルコである。 高齢比率を取り上げた国は25カ国であり、比率の高い順にベルギー、アイスランド、イタリア、スウェーデン、ギリシャ、米国、ハンガリー、ノルウェー、スペイン、ポルトガル、フィンランド、カナダ、スイス、フランス、英国、オランダ、日本、オーストリア、ドイツ、メキシコ、ルクセンブルク、オーストラリア、韓国、アイルランド、トルコである。 (2010年10月4日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||