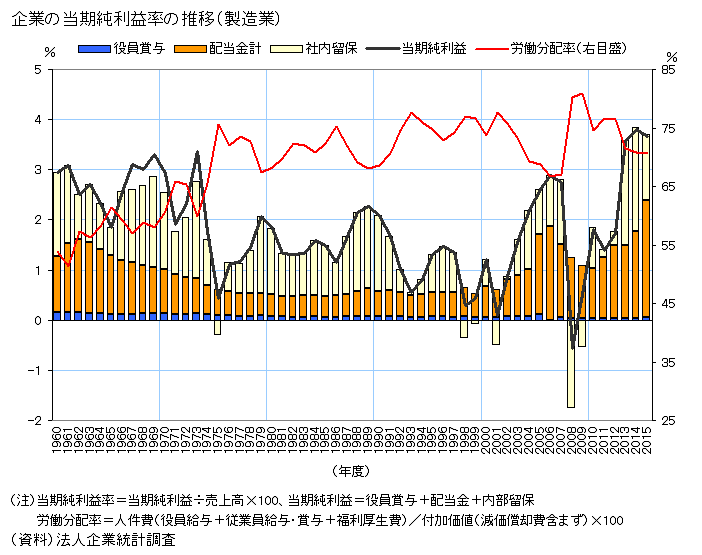
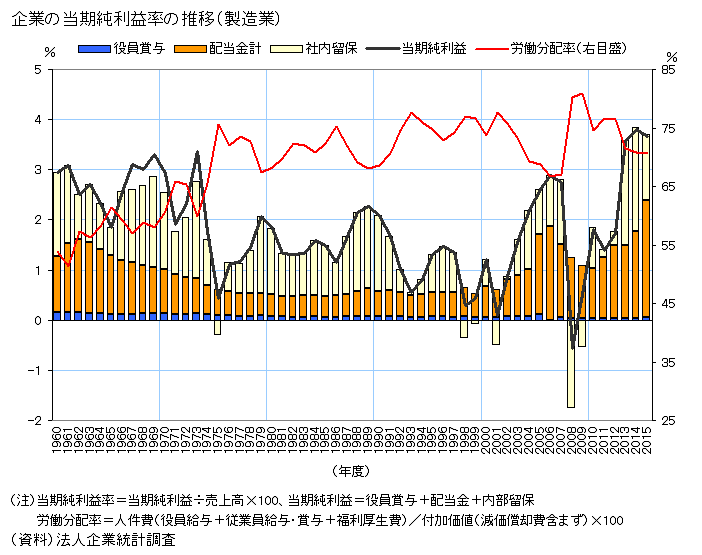
当期純利益の内訳の推移を見ると、近年、配当金のシェアが急拡大する傾向にあり、2005年度〜06年度には、1.59%、1.88%と当期純利益全体の半分を越え、過去最大の対売上高比となるに至っている。その後もリーマンショックによる当期純利益の激減にもかかわらず配当金のシェアはそれほど低下しなかった。 企業経営は、利益の拡大と配当金の増加などによる株式価値の向上に向かっており、その分、賃金の支払いへ向かう部分は大きくないというのが最近の傾向であることがうかがわれる。 さらに労働分配率との関わりを短期変動と長期変動の2局面から見ておく。 短期的な動きでは、企業の利益率が下がっても人件費が急に下がることはないので利益率の下降局面では労働分配率が上がる。逆に利益率が上がれば労働分配率は下がる。実際の推移も確かにそういう動きとなっている。 長期的には利益率の水準と労働分配率の水準の差を見なければならない。 1973年までの高度成長期には、一貫して利益率が高いため、一方でさらなる企業成長のため高い内部留保率を確保するとともに、他方で、人件費比率の上昇が可能であった。 その後、安定成長期、低成長期と我が国経済が大きくシフトした(図録4400)。それとともに企業の利益率は傾向的に低落した。1990年前後のバブル経済の時期は傾向線から上ブレした時期といって良いであろう。 ところが労働分配率の水準自体は高止まりしていた。デフレ経済の中で給与水準自体はマイナスにしにくく(給与の伸びを抑えられても下げるのは難しい)、また給与水準の高い中高年層のシェア拡大によって、こうした状況となったと考えられる。米国と異なり中間管理職の消滅でなく新規雇用抑制と早期希望退職というリストラの形態をとった日本の「プロセス最適化」「やせ我慢」型の対応がこうした労働分配率の高止まりを生んだという見方もある(西村清彦「日本経済〜見えざる構造転換」2004)。 こうした中、世紀の変わり目の時期に、非正規雇用者の増加、リストラの進行・一巡(中高年層の整理、低利用資産の整理)、企業の買収・合併等による企業価値の向上などが進み、企業の利益率は急回復した。人件費や設備費に要する固定費用が縮減されたので比較的小幅の需要拡幅でも販売価格が大きく上昇し、収益の回復も急速だったという見方もある(西村前掲書)。 この結果、労働分配率は低下した。また、配当金シェアの持続的上昇に見られるように内部留保による既存企業の成長路線というより、株式価値の上昇を目指した資金循環による新規企業成長路線という経済成長の側面も大きくなった。 こうした経済成長の形態変化をこの図録から見てとることが可能である。 リーマンショック後の不況による利益の急減に対しては従来を上回る規模の内部留保の取り崩しで対応した側面が大きく、従業者給与はそれほど下がらなかったため、結果として、不況期の通例として労働分配率は上昇した。 2013〜14年度には内部留保が空前の規模となり、配当金が内部留保を再度下回っている。株式価値の重視については2006年度頃よりは落ち着いたが、2015年度には配当金が増え、過去最大となった。 (参考)企業収益に係る各種の指標の違い
(2007年7月27日収録、10月3日更新、2013年12月6日更新、2015年10月14日更新、2016年9月5日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||