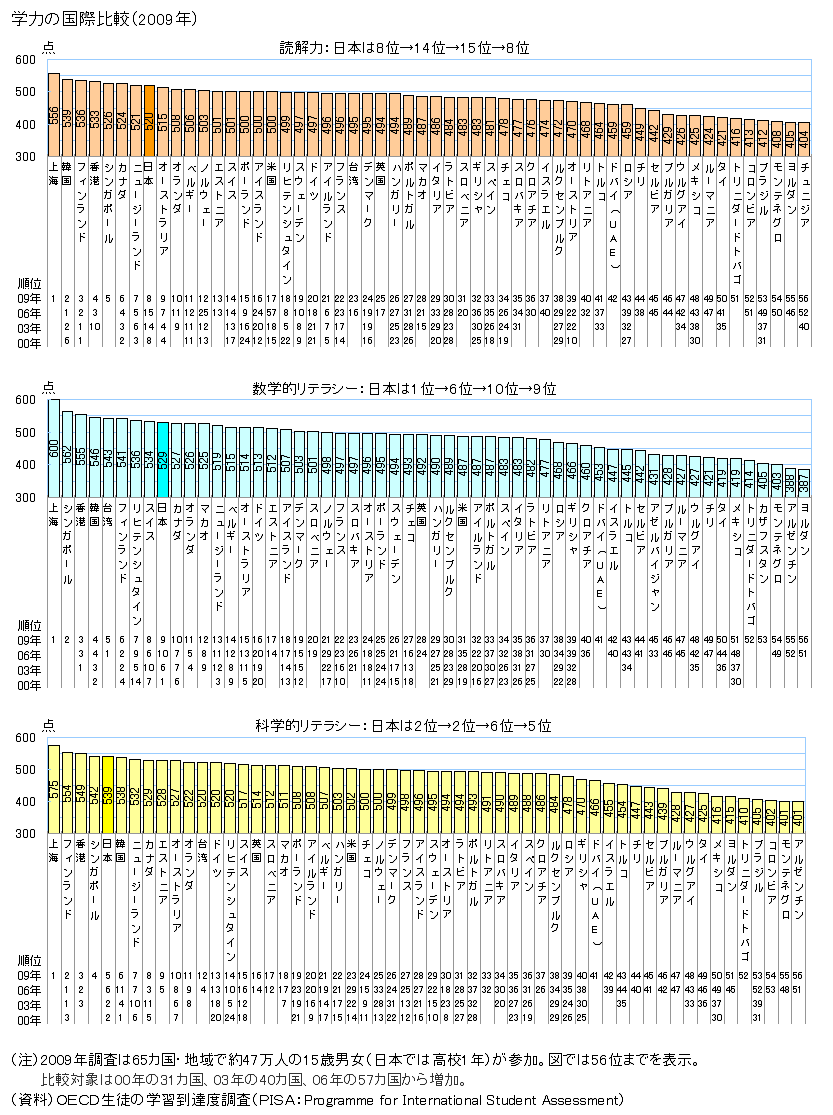
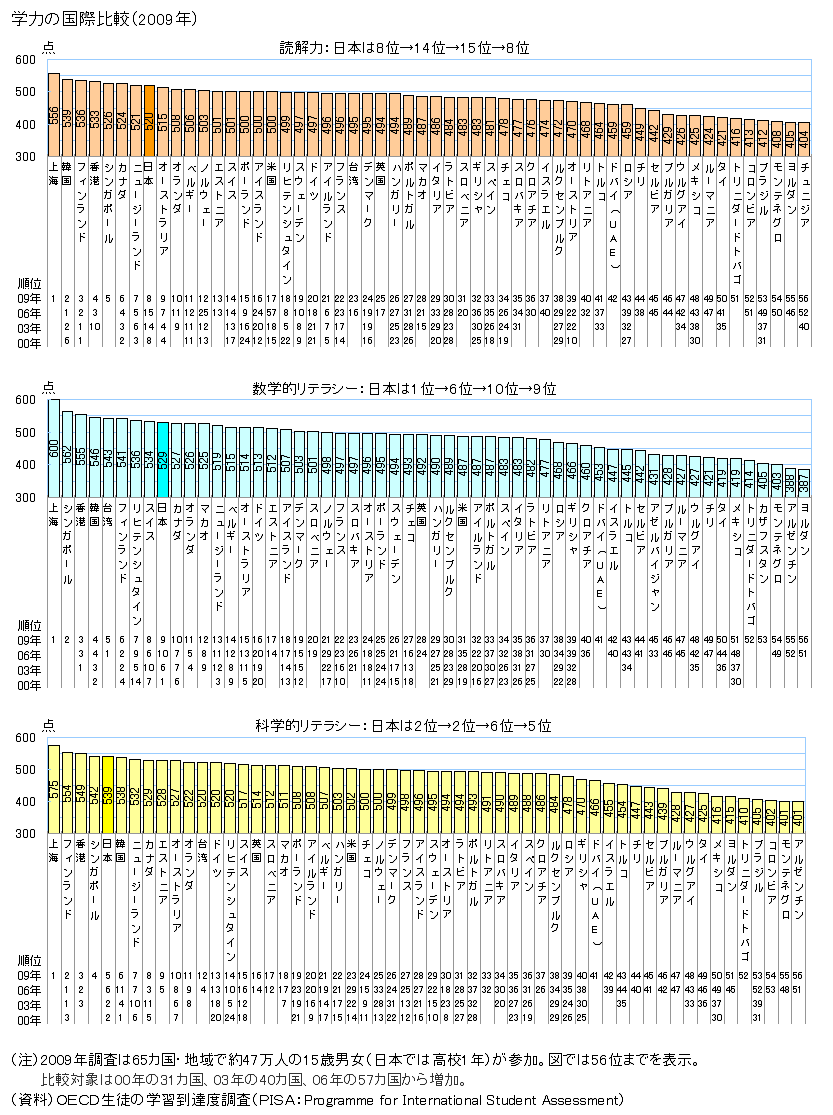
| OECDでは世界の15歳児童を対象に学力(学習到達度)に関して実際にテストを行う調査を3年ごとに行っている。この結果は、自国の学力レベルに関心を持つ各国国民の関心の的になっているので紹介することとする(なお、大人の学力テストというべき成人スキル調査の結果は図録3936参照)。 図には2009年の点数とともに2000年から3年ごとの順位を記した。点数はOECD加盟国の平均点が500点になるように配点を調整し、得点を出している。参加国は毎回増加。 「調査には、上海のほかシンガポール、ドバイなど8カ国・地域が新たに参加。日本では無作為に抽出された約6000人が、3分野のテストと学習環境などのアンケートに回答した。中国、インドは「言語が多様なことなどから全国一斉テストの実施は難しい」とOECDの参加要請を断った。上海、香港などは自主参加だった。上海がトップを独占したことについて、OECDは「中国で最も教育改革が進んでおり、同国全体の平均を表しているわけではない」とコメントした。」という(毎日新聞2010.12.8)。 分析対象国は、読解力の高い順に、上海、韓国、フィンランド、香港、シンガポール、カナダ、ニュージーランド、日本、オーストラリア、オランダ、ベルギー、ノルウェー、エストニア、スイス、ポーランド、アイスランド、米国、リヒテンシュタイン、スウェーデン、ドイツ、アイルランド、フランス、台湾、デンマーク、英国、ハンガリー、ポルトガル、マカオ、イタリア、ラトビア、スロベニア、ギリシャ、スペイン、チェコ、スロバキア、クロアチア、イスラエル、ルクセンブルク、オーストリア、リトアニア、トルコ、ドバイ(UAE)、ロシア、チリ、セルビア、ブルガリア、ウルグアイ、メキシコ、ルーマニア、タイ、トリニダードトバゴ、コロンビア、ブラジル、モンテネグロ、ヨルダン、チュニジア(ここまで図示)、インドネシア、アルゼンチン、カザフスタン、アルバニア、カタール、パナマ、ペルー、アゼルバイジャン、キルギスの65カ国である。 日本の状況を分野ごと2000年から2009年について示す以下の通りである。
前回は読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーのすべてで順位が低下し、マスコミでも危機感をもって大きく報道された(図録3940w参照)。 今回は日本の順位が回復し、教育界の努力が実ったともみなせるが、なお、学力格差が解消していない点が指摘された。また、新たに参加した上海、シンガポールを含め、アジア勢が上位を独占した点に注目が集まった。 関連して科学得点の分散から見た学校間、学校内の学力格差の国際比較について、日本の学校間格差が大きい点を図録3941(2006年結果による)に掲げた。 (2004年12月19日収録、2007年12月10日更新、2010年12月8日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||