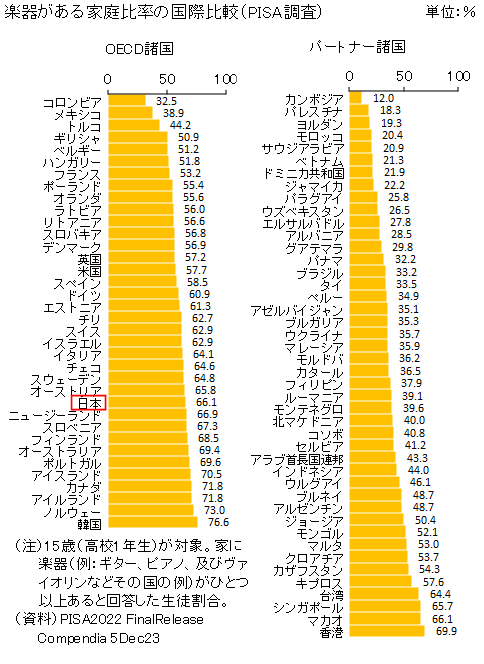
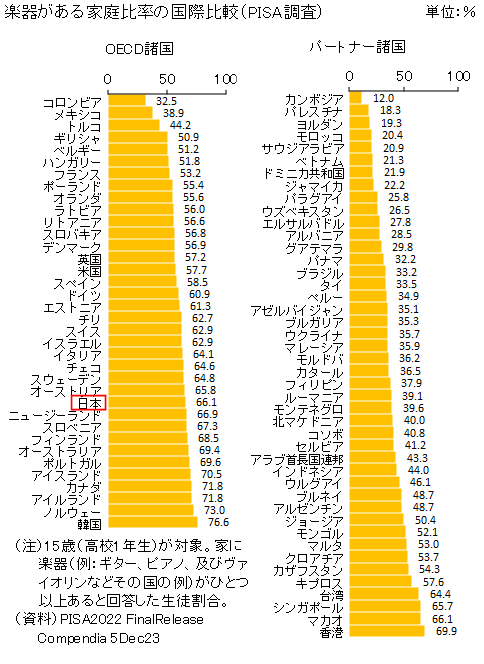
どんな楽器の保有を調べているかと言うと、各国、ギターとピアノは共通で、その他、国によってヴァイオリンなどその国で普及している楽器をひとつ加えた中から1つ以上を有しているかの保有率である。 この楽器保有率は、どの国がどれだけ音楽好きかをあらわしているとともに、ピアノが対象とされていることからうかがえるように、楽器を有するだけの所得水準に達しているかどうかの要素の影響も反映していると考えられる。 日本は66.1%と約3分の2の家庭で楽器を保有している。OECD諸国の中でも11番目の高さであり、日本人はまあ音楽が好きな国民なのだと言えよう(下段の所得水準との相関分析参照)。 OECD諸国の中で最高は韓国の76.6%であり、韓国人の音楽好きが目立っている。 2位以下はノルウェー、アイルランド、カナダ、アイスランドと北方諸国が続いている。気候が寒い冬には家で楽器を楽しむ生活習慣が普及するのだろうか。逆に、ギリシャ、フランスの楽器保有率が低いのは暖かい気候だから家で楽器を楽しむより屋外で自然と親しんだ方がよいからかもしれない(図録3956aの読書率も同様)。 主要先進国(G7、韓国)の順位を低い方から並べると以下である。 1.フランス 53.2% 2.英国 57.2% 3.米国 57.7% 4.ドイツ 60.9% 5.イタリア 64.1% 6.日本 66.1% 7.カナダ 71.8% 文化度が高いと思われているフランスは意外と低い。最高はカナダである。美術品の保有と同様なのも興味深い。 OECD以外の調査パートナー諸国はOECD諸国より全体として値が低いが値のばらつきはやはり大きい。最低はカンボジアの12.0%、最高は香港の39.9%である。 香港の次いで高い保有率なのは、マカオ、シンガポール、台湾の順である。OECD諸国の韓国、日本を合わせ、儒教圏諸国で楽器保有率が高い点が目立っている。儒教では伝統的に音楽を修養を媒介する重要な存在としてきたことがこうした結果を生んでいるとも考えられる。 (注)儒教において、音楽は「礼」(礼儀作法)と対をなす「礼楽思想」の中心であり、人々の心を正しく導く重要な役割を担っているとされた。 孔子は音楽を格別の存在と考えていた。論語述而編には「子、斉にありて韶(しょう、古代の舜の時代の管弦楽)を聞く。三月、肉の味わいを知らず」とある。 また、音楽を楽しみの手段以上の社会的人格形成の手段と見ていた。論語泰伯編には「子曰く、詩に興こり、礼に立ち、楽になる」とある。これは、詩に興こり(詩経による正しい感情の高揚)、礼に立ち(礼による人間秩序の法則づけ)、楽になる(音楽を通じ、法則による感情の整理を行い、人間性の包括的完成に至る)という教養の順序をあらわすものとされる(吉川幸次郎「論語上」p.214、262)。 経済発展度をあらわすIMFデータの2022年PPPドル・ベースの1人当たりGDPとここでの楽器保有世帯比率とのR2値(対数相関)を算出すると0.5898とかなりの相関、すなわち生活に余裕があるほど楽器を家に有する傾向となっている。 下図には所得と楽器保有比率の相関図(相関曲線は対数相関)を描いてみた。相関曲線より上に位置する国は音楽好き、下に位置する国はそうでないと考えることができよう。北方圏諸国や日本のほか儒教圏諸国で楽器保有比率が所得水準で相応の比率以上に高く、逆に産油国で低くなっているように見える。 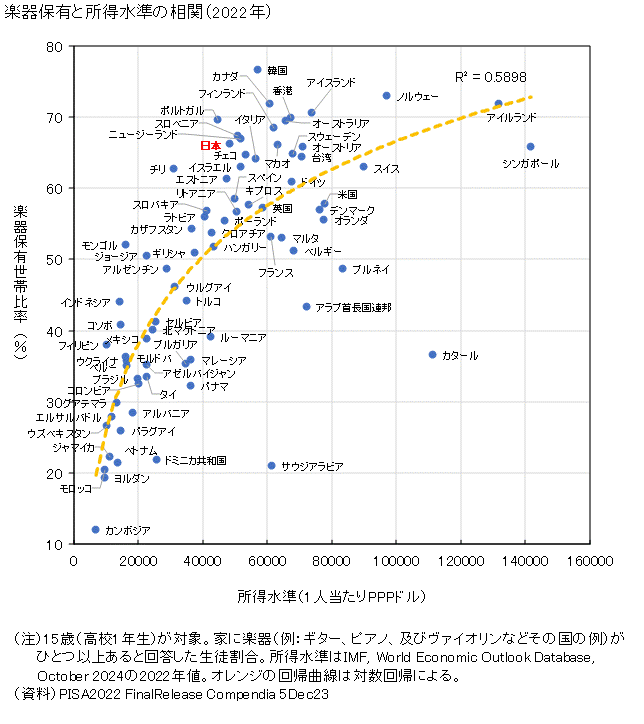 対象となった諸国は、OECD諸国、パートナー諸国の図の順にコロンビア、メキシコ、トルコ、ギリシャ、ベルギー、ハンガリー、フランス、ポーランド、オランダ、ラトビア、リトアニア、スロバキア、デンマーク、英国、米国、スペイン、ドイツ、エストニア、チリ、スイス、イスラエル、イタリア、チェコ、スウェーデン、オーストリア、日本、ニュージーランド、スロベニア、フィンランド、オーストラリア、ポルトガル、アイスランド、カナダ、アイルランド、ノルウェー、韓国、カンボジア、パレスチナ、ヨルダン、モロッコ、サウジアラビア、ベトナム、ドミニカ共和国、ジャマイカ、パラグアイ、ウズベキスタン、エルサルバドル、アルバニア、グアテマラ、パナマ、ブラジル、タイ、ペルー、アゼルバイジャン、ブルガリア、ウクライナ、マレーシア、モルドバ、カタール、フィリピン、ルーマニア、モンテネグロ、北マケドニア、コソボ、セルビア、アラブ首長国連邦、インドネシア、ウルグアイ、ブルネイ、アルゼンチン、ジョージア、モンゴル、マルタ、クロアチア、カザフスタン、キプロス、台湾、シンガポール、マカオ、香港である。 (2025年10月22日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||