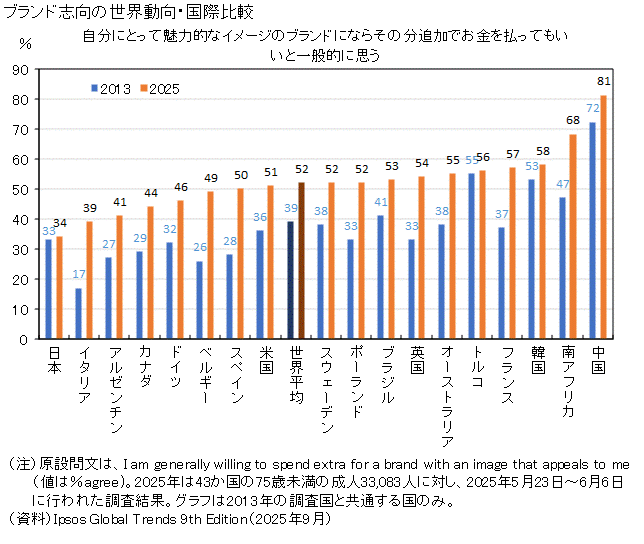
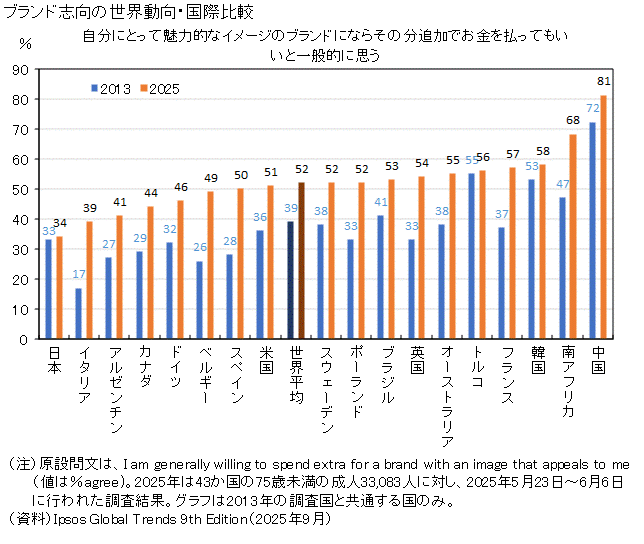
この調査の1項目であるブランド志向の世界動向や各国比較について見てみよう。 イプソス社は新しい潮流として「ヌーヴォー・ニヒリズム」を取り上げている。これは、①主要国で行われた2024年の選挙で、現在の政治家や政治体制への不満としてあらわされた露骨なニヒリズム、②そして経済的ストレスによって長期的な夢の実現が阻害された結果生じた従来より快楽主義的な「今を生きる」精神、という2つのトレンドの融合とされる。 さらにこれと関連して「個人主義への逃避」という潮流を指摘している。これは、世界状況を変えられないという意識の下で、人々が自分の生き方を重視し、自分自身だけでコントロールできるものに注目しているという動きである。 そして、後者を示す指標として、上のブランド志向データを掲げている。 2013年から2025年にかけてのブランド志向の変化に着目すると、いずれの国でもブランド志向が上昇している点が目立っている。世界平均でも39%から52%への13%ポイントの増と大幅である。 ここでブランド志向の指標としているのは「大抵の場合、魅力的なイメージを持つブランドであれば、高いお金を支払っても構わない」への同意率である。英文では、I am generally willing to spend extra for a brand with an image that appeal to me (%agree)。 このデータに関するイプソス社のコメントは次の通りである(第9版)。
地域別の動向に着目すると、回答国民の中で東アジアに属するのは中国、韓国、日本であるが、ブランド志向という点では中韓と日本とで両極端になっている点が目立っている。 服飾ブランドの両雄はフランスとイタリアだろうが、フランス人のブランド志向は高いがイタリア人のブランド志向はむしろ世界の中でも低い点が目立っている。イタリア人はそんなにブランドにこだわっていないのは不思議な気がする。 2013年から25年にかけての動きを見ても日本はほとんどかわっておらず、世界的なブランド志向の高まりの中では異質である。 日本人のブランド志向が低いのは何故だろうか。 日本には「無印良品」という「ブランド」という概念をなくすことを目指して作られたブランドがある。無印良品は、流行や個性を排し、素材、工程、包装の「実質本位」の考え方に基づいており、幅広い層に「これがいい」でなく「これでいい」という満足感を提供することを特徴としているとされる。 衣服のユニクロ、日用品のニトリなどにも、これと似た発想の要素がある。 無印良品、ユニクロ、ニトリ、あるいは量販店やコンビニチェーンのプライベート・ブランドは、普通はそれぞれがブランドの一種ととらえられているが、むしろ、ブランドを否定するノーブランド的な要素に特徴があるといえるのではなかろうか。こうしたブランド選択するのは少し高い値段を出しても自分の存在を際立たせるのが目的ではなく、むしろ、自分らしさにこだわらず、商品そのものの機能や価値を追求するためだからである。 100円ショップにもそうしたところがある。 こうしたノーブランド・ブランドを好むこうした日本人の志向がここで取り上げたブランド志向で日本人の値が低い理由だと思われる。つまり、日本人は「個人主義への逃避」消費という側面があるとしても、むしろ、それ以上に「個人主義からの逃避」消費への傾斜が著しいと言えるのではなかろうか。ブランド志向が世界一強い中国人と、世界一弱い日本人。しばしば問題となる両国の政治的な対立も、こうした人としてのあり方の差が、根本的な要因のひとつなのかもしれない(注)。 (注)日本人と中国人の国民性の違いは以下のような中国史家の記述にもうかがわれる。この違いがここでは個人主義の違いとしてあらわれているようにおもえる。 日本人のエリートと庶民の関係は「血縁・地縁からはじまって、さらに同朋など、上下左右さまざまなつながりからできあがり、その関係の行きわたった全体に、「公」という共通の意識がかたちづくられ、法共同体をなします。そのため日本人は、法律をよく守るのです。 これに対し、中国では王朝も政権も皇帝も官僚も、いわばよそ者で、信頼の対象ではありません。中国人が信頼できる強いつながりは血縁・地縁しかなく、そこでいったん切れてしまいます。 だからこそかれらは、日本人よりはるかに血縁・地縁を大事にするのです。自分たちの血縁、身内の間の約束は、ものすごくよく守るのですが、逆にそこから一歩出たら、まったく気にしません。他人の決めたルールや、国の決めたルールなど守る必要もないし、守ろうという気持ちすらもっていません。どうでもいいのです。だから、国際法を破っても平気なのです」(岡本隆司「教養としての「中国史」の読み方」PHP文庫、第6章「「士」と「庶」の二元構造」)。 日本人のブランド志向の低さは、ちゃんとした階層に属していると見られるための階層消費とでも呼ぶべき側面が希薄だからという見方も成り立つかもしれない(家計消費に占める服飾費の小ささからこの点を図録2270でふれたので参照されたい)。 なお、以上と関連して、無印良品やユニクロは余白型ブランドであり、これが、以下のように、日本人の志向が産んだ世界戦略となっているという見方もある。 無印良品のコスメに典型的に見られるように「本物同様の品質で価格が安い代替品」というジェネリック薬と同じ効用をもつブランドだという特徴があり、それは無印良品の当初からの考え方という。「無印良品のデザイナーの一人である原研哉さんが語っている「エンプティネス(空っぽ)」という概念が、ブランドを形作るDNAの一部となっています。原さんは日本の神社の「屋代(しろ)」を例に挙げ、日本文化が持つ「空っぽ」は「満たされる可能性そのもの」と説明します。四本の柱と屋根だけの空間に神様が宿るように、無印良品の商品も「空っぽ」であることでユーザーの自己表現の場となるのです。 このような特性を持つブランドを、「余白型(キャンバス)ブランド」と呼ぶことができます。無印良品の商品はシンプルで自己主張が少ないため、使う人が自分の生活の文脈で意味づけをしやすく、SNSなどでの発信がしやすいという特徴があります。無印のレトルトカレーもコスメも、ブランドとしては「空っぽ」であり、その部分を消費者が自分自身の表現で埋めていくのです」(コムギコ、TBS NEWS DIG 2025.11.26)。 そして、こうした特徴は日本の音楽文化「ボカロ」「初音ミク」、人種も国籍も特定されていないファンタジーの世界観をもつ日本のアニメやゲームキャラクターにもこの「余白性」があり、日本文化を生かした余白型ブランドが世界的成功のカギとなっているという。「ユニクロも無印良品と同様に「余白性」を持ったブランドといえます。(中略)無印良品とユニクロに共通する「余白型ブランド」のコンセプトは、日本発のブランドが世界で成功するための重要な鍵となる可能性があります。ユーザーの創造性や自己表現を受け入れる「空っぽのうつわ」としての特性が、グローバルな多様性の中で強みとなっているのです」(同上)。
図の対象国は、並び順に、日本、イタリア、アルゼンチン、カナダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、米国、スウェーデン、ポーランド、ブラジル、英国、オーストラリア、トルコ、フランス、韓国、南アフリカ、中国である。 (2025年11月8日収録、11月27日余白型ブランド説、12月11日コラム追加、2026年2月19日岡本隆司引用)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||