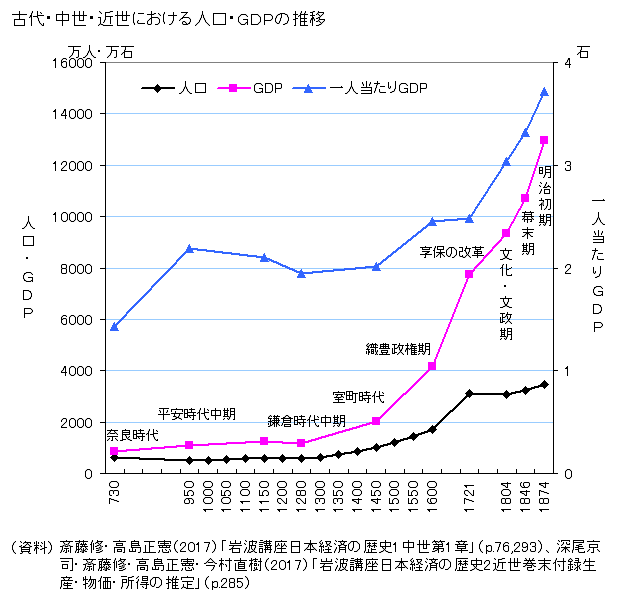
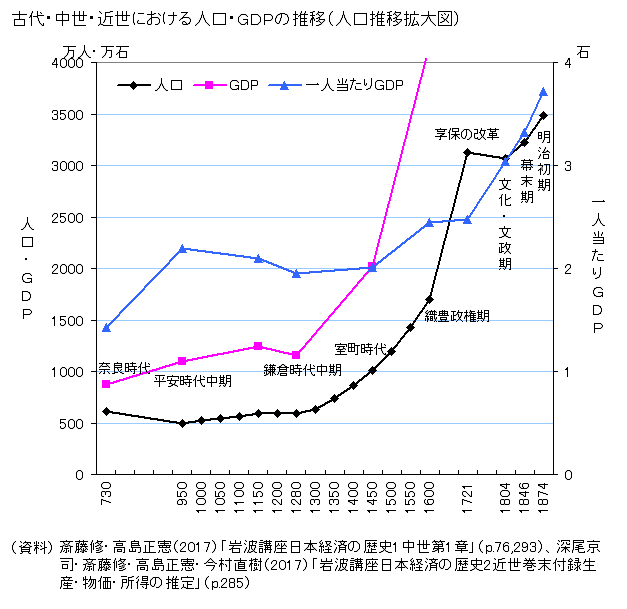
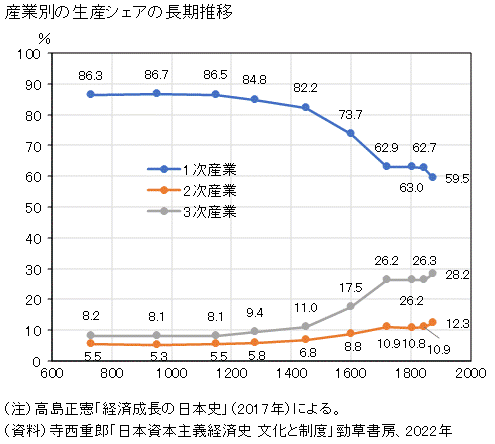
�y�N���b�N�Ő}�\�I���z
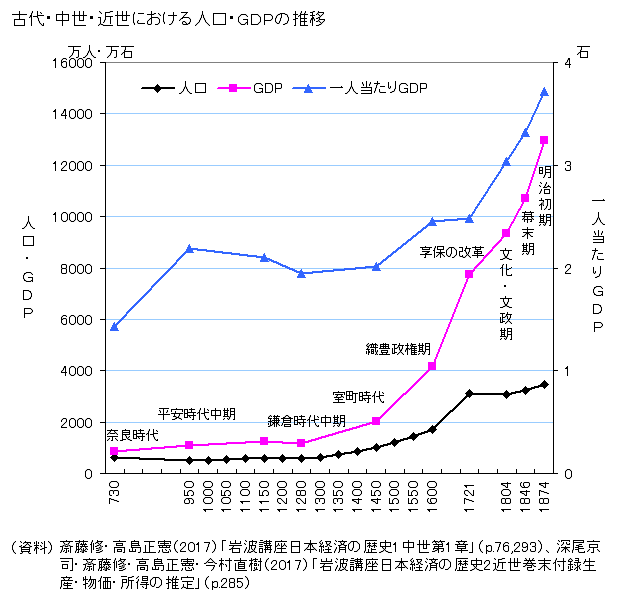 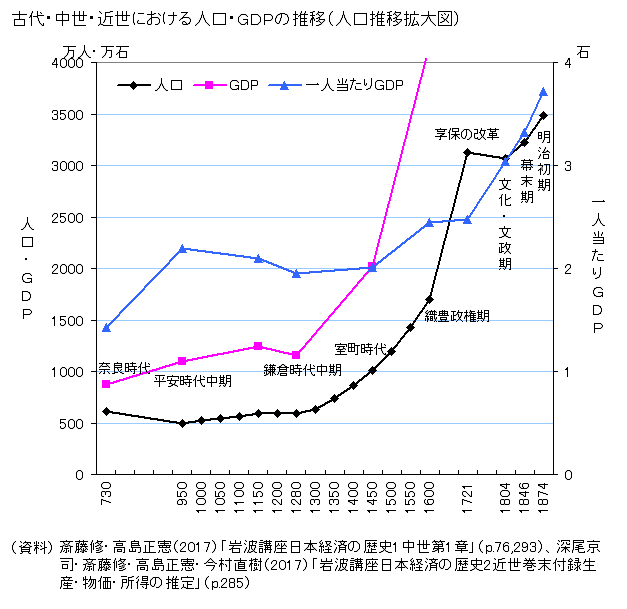 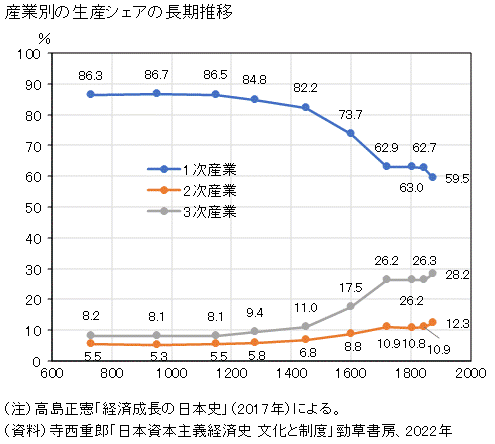 |
| �@ | �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@2017�N�Ɋ��s���J�n�����u��g�u�����{�o�ς̗��j�v�͑�1���`2���ɋߐ��ȑO�̐l����GDP�Ɋւ���V�������v���f�ڂ��Ă���B�����ł́A�����1�}�ɂ܂Ƃ߂Ď������B �@GDP�̐��v�͌Ñ���ł�v�[�Ɗ֘A�Â����\�ȃf�[�^���c���Ă���_�Ɛ��Y�ʂɊ�Â��Ă���B1���Y�Ƃ�GDP�͂���ɗыƂƋ��Ƃ̕��𐄌v���ĕt��������߂���B �@�S���I�ɐ����ʂ��2���A3���̐��Y�̃f�[�^�͂Ȃ��̂ŁA1����2���A3���̐��Y�̔䗦���A�s�s�l���̊����i�s�s���䗦�j�y�є_�����̐l�����x�Ƒ��ւ��Ă���Ƃ������̎�������ߋ��ɂ����̂ڂ��Đ��v����Ă���B �@��������1���`3���ɂ܂�����S�̂�GDP�����߂��邱�ƂɂȂ�B �@����ƕʌ��v���ꂽ�l���ɂ����1�l����GDP���Z�o�����B�����Ōf����1�l����GDP�̐��ڂ���{�ȊO�̎�v���Ɣ�r�������ʂɂ��Ă͐}�^4546�Q�ƁB �@�Ñォ��ߑ�܂ł�ʂ��Ċe���̓����͈ȉ��̂悤�ɗv���B
�@730�N�`1600�N�̐l���Ɋւ��ẮA����܂ł̋S�����v�ɑ���V���v�Ɋ�Â��Ă���B �P�D�Ñ�E����
�@�E�ޗǎ���ȍ~�̓��E�V���E�݊C�Ƃ̕p�ɂȍ��ی𗬂ɂ���Ė��m�̕a���̂��҂����܂ꂽ�e���ŕ��������ɂ����Ă͐l�����������Ă���B �u���̌�A���A�W�A�̌𗬂��a�ɂȂ������Ƃɉ����A�������̊g��Ɠy�n�J���̐i�s�������āA�l���K�͈͂ȑO�̐����։������B���̔w�i�ɂ͕��m�c�̑��݂��������B���̂��̎q���ɕ������ď��^����Ƃ����y�̐��́A�������^���ꂽ�y�n�ɖ����n���܂܂�A���̖����n���q������ɂ���Ă���ɊJ�����ꂽ�Ƃ����Ӗ��ŁA�J���̎���ɂ����Ắu�����I�ȁv���x�ł���A���l�������ɍD�s���Ȏd�g�݂���������ł���v�i�֓��C�E���������i2017�j�u��g�u�����{�o�ς̗��j1������1�́v�Ap.61�j�B �@�������A����1150�N�ɂ����Ă̐l���������ɔ_�Ƃ̐��Y���͂ނ���ቺ���A1�l����GDP�͒ቺ���Ă���B �@12�`13���I�ɂ͍ēx�l��������邢�͌�������B13���I��2�x�ɂ킽��v�K�}���Ɍ�������v���Ղ̊������ɔ����C���t���G���U�Ђ��V�o�ꂵ�����ƂȂǂɂ����̂Ƃ����B �@���̌�A14���I����l���̎����I�ȑ����X���������ƂȂ�B����́A13���I������14���I�ɂ����āu12���I�㔼�ɖG��I�Ȃ������Ŏn�܂����W�����ւ̓���������ɂ܂łȂ����Z�n�̌`���ƂȂ����v�i����Ap.63�j����ƍl������B�܂�A���̍��ɂȂ��āA����Ɠ��{�̔_�����̓����ł���u���v�̑��݂���ʉ���������ł���B���Â̐̂��瑺���������킯�ł͂Ȃ��̂ł���B �@���������̑����̐����ƂƂ��ɂ͂��܂��������̍k�n�J���́A���q���㔼�����k������̂���A13���I������14���I����ɂ́A���n���̍D�����̓y�n�̊J���͂��炩���B������A�u�c���ꂽ�J���\�n�͉͐쉈���̂悤�ȃ��X�N�̑����ꏊ�A�X�Βn�̂悤�ȍ��x�ȓy�؋Z�p�̕K�v�ȏꏊ�A���邢�͑�K�͂Ȑl�������̕K�v�ȊC�ݎ��n�Ȃǁv�ƂȂ����Ƃ����j�w�E�̌���������i�|���뎡�u�������{�ƒn���̎Љ��v��g�V���A2016�N�Ap.113�j�B�퍑�喼�������ꂱ�������J����e�Ղɂ���܂ŁA�o�ς̊g��͐����I�ł���Ɏ~�܂�A1�l����f�c�o�͐L�єY�Ƒ����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B �@�Ȃ��A13���I������14���I����ɍD�����̓y�n�ɂ��ĊJ���̖O�a���ɒB�����Ƃ������̌����ɗ��ƁA�������ɂ�����W���̔����̗v���Ƃ��āA��L�̂悤�ȓy�n�J���𑣐i��������Ƃ������A����ꂽ�o�C���߂��鑈���̑����̒��ŗ��Q�����L�ł���l�X���������ł߂�@�\�ɏœ_���������Ă���悤���i���Ap.115�j�B �@�l���̎����I�ȑ����X�����\�ƂȂ����̂́A�u�����S���R�ɂ���̂��Ȃ��������߁A�����ƈقȂ�A�y�X�g�̂悤�Ȓv�����̍��������ǂɔY�܂���Ȃ������v�i����Ap.63�j�̂��傫���ƌ�����B�܂��A16���I�㔼����͐퍑�喼�̈�~�x�z�ɂ��Q�[�p�x�̏k����������Đl��������������i�Q�[�p�x�ɂ��Ă͐}�^0288�Q�Ɓj�B �@1600�N�̐l���͂���܂ł̒��1200���l�ł͂Ȃ��A1700���l�ɒB�����ƍl������B �@1�l����GDP�̒P�ʂ͔_�Ɛ��Y�ʂł���i����180���b�g���j�ł���킳��Ă���B1��2.5�U��150kg�ɂ�����A�l��l����N�Ԃɏ����Ă̗ʂɓ���Ƃ���Ă����B��l������GDP��2�Ȃ�1�l�̐��Y�҂�����1�l�̔Y�ҁi�q�ǂ��A�E�l�A���m�A�V���Ȃǁj��{���銨��ƂȂ�B �@����������D�L�������ɂ����Ĉ�l������GDP��0.5�̑����͑�ςȃC���p�N�g����������ł���B���̎����̈�l������GDP�̑����v���ɂ��ẮA�퍑�喼�̗̍��x�z�ɔ������Y�g��A�y��16�`17���I�ɂ�����C�O�Ƃ̋Z�p�𗬂̊g��i�z�R�J���u�[���Ȃǂ��j����b�ɂ������ʌo�ς̔��B�A����ɂ��2���E3���Y�Ƃ̔��B���l������B�����ȑO�ɊO�m�q�C�̂��߂̎��D�͍����Ŏ��O��������Ă�������łȂ��A�����P���̈�����ǎ��ȑD�ނ③�D�Z�p�ւ̐M������t�B���s���ɗA�o������Ă����̂ł���i�����u�����v�������ɁAp.209�j�B �Q�D�ߐ�
�@�ߐ���ʂ���GDP���L�ё����Ă���Ƃ����f�[�^�̎�v�ȍ����́A�������̋ᖡ���炱��܂ňȏ�ɔ_�Ɛ��Y�Ɋւ��ĕ\���������������������Ă����Ƃ������v���ʂɂ���Ă���B�u���ˑ̐����ɂ����镕���̎�E���{���_���̑S���Y��c���ł��Ă��炸�A���̌X���͋ߐ��㔼�ɂȂ��Ă�茰���ɂȂ��Ă������\���v�������̂ł���i���������E�[�����i�E���������i2017�j�u��g�u�����{�o�ς̗��j2�ߐ����͑�1�ߐ����ƃ}�N���o�ρv�ip.10�j�B �@���\������o�āA���ۊ��Ɏ���܂ł̋ߐ��O���Ƃ���ȍ~�̋ߐ�����Ƃł́A�l����o�ς̓����̃p�^�[����180�x�ω�����B �@�]�ˑO���ɂ́A�ߑ�ȑO�̍ő�̐l���������ƂȂ�GDP������ɉ����đ��������B�l������������1�l�����GDP�͑����Ȃ������B�V�c�J���ɂ��_�n�Ɛl���̐����I�Ȋg�傾���������ς�o�ϐ����̗v������������ł��낤�B�����ɂ��f�Ղ̏k���╽�a�̑㏞�Ƃ��Ă̋Z�p�J���̗}���ɂ���āA���Y���̏㏸�͂ނ���l�דI�ɗ}����ꂽ�̂ł���B�Ⴆ��3�{�}�X�g�ŗ����\�������O�m�q�C�D�͋ւ����A1�{�}�X�g�̉��ݍq�s�D�݂̂������ꂽ�B �@���}�ɂ�������悤�ɁA�ߐ��O���ɂ͑傫���l�����������A����Ɣ�Ⴕ�āA�]�˂₻�̑��̏鉺�����������A�s�s�����i�i���̎����̓s�s���̐��ڂ͐}�^1153�Q�Ɓj�B���̌��ʁA�s�s�̏��ƥ�T�[�r�X�ƒ��S�ɔ�1���Y�Ƃ����������ƍl������B���\�����ɂȂ���o�ϐ����ł���B���ꂪ�����I�g��̈ꑤ�ʂ������Ƃ����悤�B �@�Ƃ��낪�A�]�ˌ���ɂ́A�l�������炭�����X���ƂȂ�A�̂��̍]�ˊ���C���[�W�̂��Ƃɂ��Ȃ����B�Ƃ��낪�AGDP�͍]�ˌ�����L�ё����Ă���A1�l����GDP�͍]�ˑO���̉����X������]���āA�傫�ȏ㏸�X�����L���Ă���B �@�ߐ�����̐l����؊��ɂ́A�s�s���͂ނ����ނ������A�l�����x���̂͑������Ă���B���H�i�E���Y�i���Y��_���H�Ƃ̔��B�ɂ���Ĕ_�����̐l�����x�����܂������߂ƍl������B�k�O�D�Ȃǂ̐��^�ɔ}��ꂽ����엿�Ȃǂ̒��ԓ����̊g���n��ԕ��Ƃ̊g��ɂ���Ď��������X�ɑ������A�����ŗ����������Ĕ_�����̏���g�傷��Ƃ����V�����o�Ϗz�̃p�^�[�����S����키�悤�ɂȂ������Ƃ������o�ϐ����Ɍ��т������̂ł��낤�B 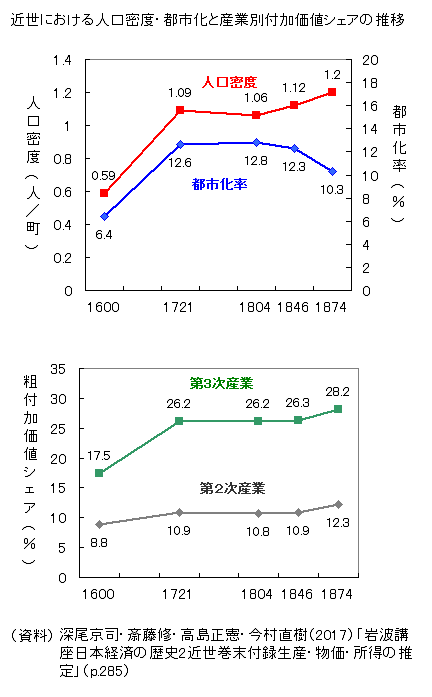 �i2017�N12��22�����^�A12��23���l�����ڊg��}�A12��27���ߐ��̃R�����g�����A12��28�������̃R�����g�����A2023�N8��21���Y�ƕʐ��Y�V�F�A���ڐ}�j
�m �{�}�^�Ɗ֘A����R���e���c �n |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@