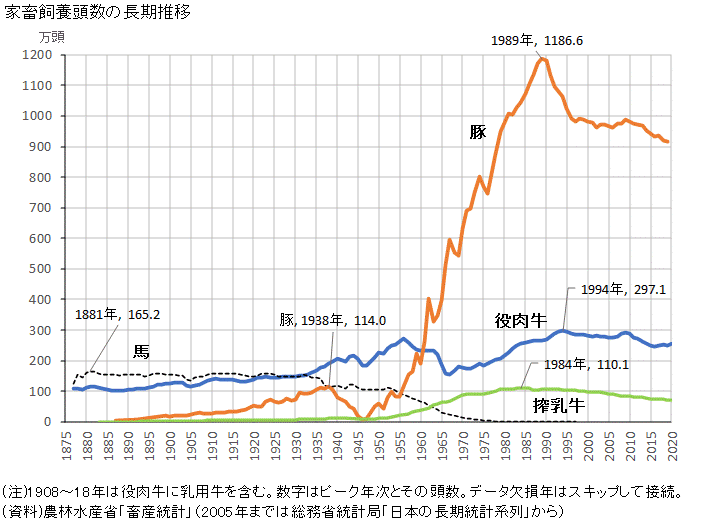
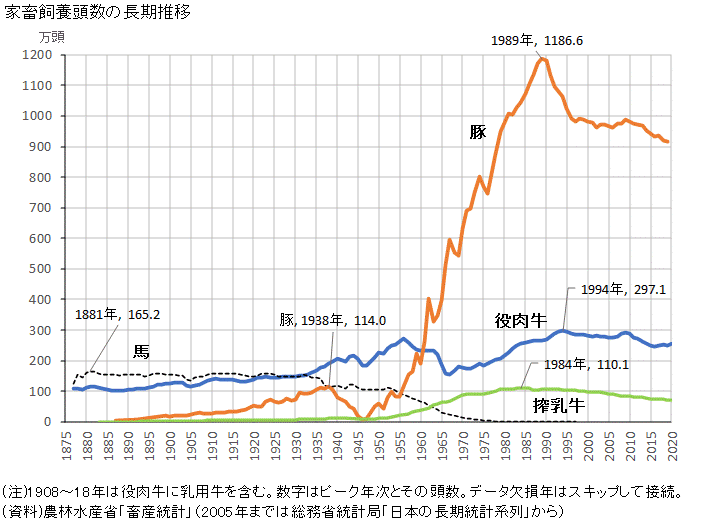
日本の家畜飼養は江戸時代まで基本的に肉用ではなく農耕用(役畜及び肥料源)だった。牛馬は運搬用、馬は軍用としても重要だった。つまり役畜としての利用が主だった(注)。 (注)いずれの役割が重要だったかは、地域によって異なる。 例えば、かつては基本的に林野だけでなく作付け前後の水田や畑を含めた放牧地で育てられていた木曽馬は、「他地域に移出されて、農耕馬や駄馬として利用されたが、地元ではあまり使役されなかった。...代かき馬のほか、馬は朝草、干し草、稲、厩肥などの運搬にはよく用いられた。しかし乗馬として利用されることはあまりなく、主として糞畜として、また仔馬を生産する用畜として飼われてきたのである」(市川健夫「日本の馬と牛」東京書籍、1981年、p.60)。「焼畑・切替畑でもない限り、農業を再生産していくためには、施肥を必要とする。自給性の強い高冷地山村では、馬の厩肥はなくてはならぬもので、これを生産する糞畜として、馬が大量に飼われてきたのである」(同)。 北海道は酪農王国として知られているが、もともとは処女地開拓後の耕作の繰り返しによる肥沃度低下を食い止めるため、デンマークに範を仰いで提唱された厩肥供給を通じた有畜農業の振興がはじまりだった。 後段でふれるように、岩手・青森の南部牛は、物資運搬用の駄牛として使われたほか、他地域への供給のための繁殖牛としての役割が大きかったが、明治以降は肉畜としての役割へとシフトしていった。 軍馬としての役割も小さくない。日清戦争(1894年)では24万人の軍隊と5万8000頭の馬が動員された(対する清国では兵員35万人、馬7万3000頭)。日露戦争(1904年)では101万人の兵員に加えて17万2000頭の馬が動員された(対するロシアは軍隊129万人、馬29万9000頭)。頭数に加えて速力、輓曳力、負担力における軍馬の劣勢、コサック馬騎兵隊との苦戦を反省し、日露戦後に建てられた「馬政第一次計画」(2006年)では、国防上の見地から品種改良の強力推進がうたわれ、国防上、産業上、馬の頭数は150万頭を維持することが決められた。計画の品種改良は「目標の3分の1を越えて3分の2が血液を更新するに至ったが、このように短期間に品種改良がなされた国は世界に例がない」という。2006年勝馬投票をともなう競馬がはじめて認められたのも馬の改良資金を得るためである。 そして、日中戦争(1937年)から45年の終戦まで、中国大陸のみで24万頭の馬が出征し、終戦時生存していた頭数は12万4000頭だった。「第二次世界大戦を通じて、日本本土から軍に徴用された馬についての資料はまったくないが、総数150万頭の3分の1、50万頭と推定されており、農村など地域経済に与えた影響も大きなものがあった」(市川健夫、前掲書、p.207〜210)。 明治以降、最初は老廃牛を食用に供するところから肉食が解禁、普及し、大正時代に豚肉が加わり、その後、特に戦後、牛乳・乳製品、豚肉、鶏肉、鶏卵の摂取が大きく拡大した(注)。他方、トラクターやトラックが普及して、牛馬は農耕用・運搬用としての役割を終え、馬は基本的に競走馬以外は飼養されず、牛はもっぱら肉牛、そして乳牛として飼養されることとなった。 (注)老廃牛の食用解禁前夜の状況は、1864年7月に下関攻撃の準備で大分県姫島に立寄った英国の外交官アーネスト・サトウの以下のような記述からうかがえる。「その日、後ほど我々は姫島に上陸したが、住民は非常に親切だった。十分すぎるほどの魚を我々に売ってくれたが、野菜、牛肉、鶏肉は持っていなかった。肥えた農耕用の牛がたくさんいたが、人々は貧乏で半分飢えているように見えた。人口は約二千人ほどだった。島は肥沃ではなかった。病気の水夫のためと偽って(そのようにするよう日本人に勧められたのだが)牛肉を買おうとしたが、できなかった。人口の半分は塩の製造に従事していた」(「一外交官の見た明治維新」講談社学術文庫、p.131)。 老廃馬も食されていたと思われる。明治期前半には東京の下層労働者階級が日常的に馬肉飯(馬肉の骨附のコソゲ落とし)、煮込み(牛の臓物煮込み)などを食していた様子については図録7842コラム参照。 馬の頭数推移が役畜の衰退を示していると考えられる。戦前には、それでも、1933年までは、おおむね150万頭以上と馬の頭数はそれほど大きく減っておらず、役畜として活用され続けていたことがうかがわれる。 大正時代の地域分布を見ると、東日本では馬、西日本では牛が多かった(下図参照)。このため、豚肉の消費が躍進したのちにも、西日本では牛肉消費が多く、肉といえば牛肉を意味する習慣が長く続いている(図録7238a参照)。 牛と馬の飼養頭数を比較すると昭和初期に逆転するまで馬の頭数の方が多い時代が続いていたが、その後、馬は役畜としての役割が衰退し、頭数が減少の一途を辿ったのに対し、牛は役畜から肉用としての役割へ転換し、頭数は増勢を維持した。 大正以降の役畜としての牛馬の歴史の要約については以下を参照(市川健夫「日本の馬と牛」東京書籍、1981年、p.204)。 「日本における役畜は、大正中期まで馬54%、牛46%の割合で、やや馬の方が優勢であった。ところが大正期に入ると、短床犁の普及、駄載の減少、湿田の乾田化、朝鮮牛の導入、牛肉の消費増加などの要因から、徐々に馬飼育から牛飼育へ転換が進められた。 昭和6年の満州事変、12年の日中戦争にともなう軍馬の大量徴発、農業労働力・機械力の不足などを補うために、役肉牛の導入が増加した。また畜力利用も年々増して、終戦を迎えた昭和20年には、畜耕面積は田47%、畑53%にも達した。そして畜力の利用は昭和28年ごろまで順調に伸びていった。農家における牛馬の飼育は、「糞畜」といわれるように、厩堆肥の生産が主目的であったが、畜力利用の増加とともに、使役日数は平均40日、多い地方では80日にも達するに至った。 昭和28年ごろから動力耕耘機の導入が増加し、また35年ごろからトラックが激増していった。この結果、役畜としての牛馬は、昭和40年代にはその歴史的な使命を終わったのである」。 役畜から肉牛へのシフトを典型的に示す地域事例としては、黒毛和牛の最大産地となっている中国山地をあげることができる。もともと中国山地は砂鉄・製炭用の運搬が巨大に必要だったたたら製鉄とむすびついた放牧主体の牛馬混合飼育地域だった。19世紀初めの文政年間の備後国比婆郡では「中層農以上は、運搬・農耕用に牡牛1頭と馬2〜3頭を所有し、また下層農・貧農は、繁殖用と農耕を兼ねた牝牛を3〜4頭飼うのが一般的だった」(p.139)。明治になって近代製鉄の生産増加とともにたたら製鉄が衰退し、大正期に壊滅状態に陥ると、「牛の仔取りと製炭が、中国山地における主要な生産部門になっていった。この結果、牛の飼育が増加する反面、馬産が後退し、また繁殖用の牝牛の比重が増加していった。そして、我が国における役肉牛の素牛(もとうし)の最大生産地を形成するに至った」。 それとともに、製鉄用薪炭林に針葉樹が植林され、放牧地・採草地が急速に減少し、ペットの犬のように運動させる必要があるため放牧時代とは異なり牛の面倒を見る婦人や老人、子どもがいないと経営が成り立たない牛の舎飼いが増加していった。また肉牛としての品種改良が進み、「役畜としてもっぱら使用した時代は、和牛のからだは前躯が発達したものが歓迎されたが、肉牛として飼育されている現在では、肉付きのよい後躯の発達のよい牛が高い評価を受けている」(p.146)。そして、蔓牛方式(在来型品種改良)と雑種化・洋種化方式を揺れ動いたのち、各地の改良和種の中から但馬牛が頭角をあらわし、黒毛和種として普及することになった。神戸牛や松阪牛や近江牛も素牛・但馬牛の系統である。 豚はトンカツ、かつ丼、ポークカレーなどの豚肉料理の開発・普及によって東京から全国に広がり(図録7238a参照)、飼養頭数の増加率も牛を上回るに至ったが、戦時中、終戦直後には、食糧難のあおりで、豚を食べるより人間がイモなど豚のエサを食べた方がよいということで飼養頭数は1938年をピークに急減した。 その後、高度成長期には、食糧難の解消、所得向上、食の欧風化、肉食の普及に伴って、豚の頭数が急増することとなった。1961年には、豚の飼養頭数が264万頭と牛を上回り、その後も急増を続け、1989年のピーク時には1,100万頭を越えるに至っている。 豚ほどではないが、飼養頭数の増勢を続けていた牛は、搾乳牛については1984年に110万頭、肉牛については、1994年に297万頭のピークを記している。 「家畜単位」という考え方がある。大きさの異なる種々の家畜数を総合的に表示するため、日本では牛、馬は1頭1単位とし、豚は5頭、ヒツジ,ヤギは10頭、ウサギは50頭、ニワトリ,アヒルなどの家禽は100羽でそれぞれ1単位とする。 牛には搾乳牛を含め、頭数の最も多い家畜は何かを考えるため、この換算単位を適用すると、1925年まで「馬」の時代が続き、その後、「牛」の時代が現在まで続いていることになる。 日本大百科全書(ニッポニカ)によると、FAOの「家畜及び食肉報告書1946」では、飼料の消費量を基礎に家畜単位(animal unit)を算出し、ウシを1として換算して、ウマ0.8、ブタ3.2、メンヨウ10.0を1単位としているという(西田恂子)。この換算単位を適用すると、1935年まで「馬」の時代、それ以降が「牛」の時代ということになる。 日本におけるメインの家畜は何かという観点から大雑把にまとめると、明治・大正期は「馬」の時代、昭和期に入り、戦間期をはさんで高度成長期までは「牛」の時代、そして、その後は「牛」と「豚」の時代へと変遷してきているといえよう。 下には、豚肉がやっと普及し始めた1924年段階の都道府県別の家畜飼養頭数を図示した。「東日本」は、牛は少なくて馬が多く、「近畿、中四国」は、馬は少なく、牛が大勢を占め、「九州」は馬も牛も多かったことが明確である。「東日本」で牛が例外的に多かったのは、乳用牛を含む北海道と南部牛の北東北だった。 また、豚が飼養されていたのは、まだ、豚肉料理が開発された東京を中心とした同心円状の関東、東山、東海といった地方、及び豚が明治以前からの伝統料理だった沖縄、鹿児島に限られていた様子をうかがい知ることができる。 参考に付した鶏の飼養羽数を見ると、近年のように東北と九州に集中してはおらず、各地方ブロックに北海道、茨城、千葉、愛知、福岡、鹿児島といったような拠点地域が散らばっていた様子がうかがえる。 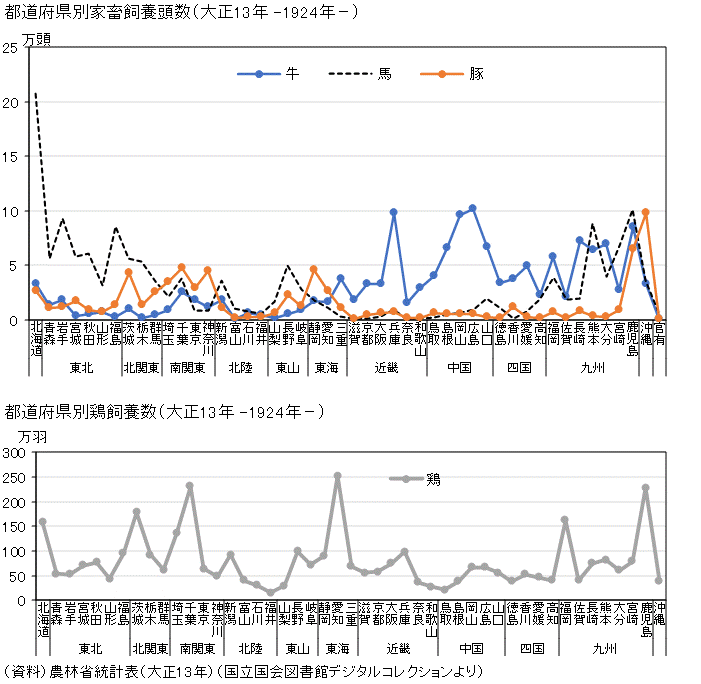 「東の馬、西の牛」という家畜の地域分布が、「東の豚肉好き、西の牛肉好き」のおおもとになっているが、それでは、「東の馬、西の牛」という家畜の地域分布はいかにして生じたのだろうか(注)。この点を探るため、上図をさらにさかのぼる明治19年の段階の耕牛と耕馬の地域分図を以下に掲げた。
(注)こうした地域分布はいつからなのであろうか。延喜式に見られる「蘇」の貢納地には関東や中部が多く(表)、やがて馬地域となる東日本において、古代には牛が馬とともに飼われていたことが分かる。ところが鎌倉後期の1310年に出版された「国牛全図」に「馬は関東をもって先とし、牛は西国を以てもととす」と記され、中世になると、日本の馬と牛の飼養圏が地域分化してくる(市川前掲書、p.17)。「蘇」は牛乳を煮つめて濃縮した乳製品であり、壺に入れられて京都に送られた。醍醐味の醍醐はこれを精製したものといわれる。なお、奈良・平安時代には貴族だけでなく農民の間でも牛乳を飲む慣習があった。古代日本はユーラシア大陸の末端にあって結構大陸文化を共有していたのである。 戦国時代に、後北条、今川、武田、上杉、徳川といった東国大名は一定の間隔で街道に宿駅をおく伝馬・駅馬制度を整備した。これは「牛は道草を食べつつ歩み、野宿もできるが、馬は宿場に泊め、飼料を与えなければならない」(脇田晴子「戦国大名」小学館、1988年、p.170〜171)からである。一方、西国大名は渡船や馬借の独占的営業を認める代わりに船や馬の徴発を行ったが、駅馬制度は設けなかった。これは「東日本は馬が中心であるのに対して、西日本では牛と船が主であったからであろう」(同、p.172)。東日本は馬、西日本は牛という対比には、沿岸海運の利用可能度も関係している可能性があろう。 分布図を見ると、全国はおおまかには、東日本の耕馬地域、近畿・中国地方を主とする西日本の耕牛地域、九州・四国の耕牛・耕馬混合地域に分けられる。 この分布図の作者である中西僚太郎(1994)によれば、牛産地としては、中国地方の山間部(但馬牛が有名)、馬産地としては、東北地方の山間部(阿武隈山地、北上山地など)が中心であり、そこからの供給範囲の限界が主な要因となって、「東の馬、西の牛」という地域分布が生じたとしている。 このため、両者の谷間に位置する富山、石川、福井、岐阜、愛知ならびに静岡県は全国の中でも牛馬の供給が少ない地域だったため役畜密度自体が薄くなったとされる。そのため、こうした地域では農耕に関して畜力より人力に依存する傾向があったらしい。 なお、馬の産地は、東北のほか、中部地方(木曽馬など)や九州地方の山間部にもあり、特に九州の耕馬の供給はもっぱら九州の馬産地によっている。 東日本は基本的に馬が多く、牛は少ないが、例外はある。 「江戸時代、東日本は馬地域であったため、牛の産地はまことに少なく、伊豆半島の丹那盆地、佐渡の外海府(そとかいふ)海岸と、南部地方の三つの産地しかなかった。その中で南部地方は最大の産地で、当時1万5000頭の牛が飼われ、年々3000頭の犢(こうし)が生産されていた。南部牛は、その名のごとく南部領に限られていた。したがって、現在秋田県の鹿角地方は羽後国ではなく、陸中国に属するが、ここは南部領であったため、南部牛が主として飼われていた」(市川健夫「日本の馬と牛」東京書籍、1981年、p.125)。佐渡が牛の産地だったのは北前船の往来が激しく、上方文化圏に含まれていたためであろう(同、p.18)。 岩手北部から青森東部にかけてのかつての南部藩領を南部地方というが、この地方に古くから伝えられている民謡として「南部牛追い唄」が有名である。南部牛は、七頭単位の隊商で、鋳物製品「南部鉄器」とはまた別の南部藩の特産だったたたら製鉄による粗鋼「南部鉄」を三陸海岸の塩や海産物とともに内陸部へ運び、内陸からコメや酒、生活物資を北上山地・三陸海岸へ運ぶ手段だった。険しい山道は馬より牛の方が適していたという。南部牛追い唄は、運搬業者である牛方の労作歌だった。 南部地方など東日本の牛産地とそこから供給を受ける地方で耕牛が多かったことが図から見て取れる。南部牛は、房総半島南部、新潟平野、山形盆地、米沢盆地などへも移出されていた。新潟の三条へは金物屋で使う南部鉄がつけられて一石二鳥の輸送だったという。 宮本常一は塩の運搬に牛が用いられた点から話を広げて、牛の産地はもともと西日本だが、東日本では思いのほか広く南部牛が流通していたとしている。「南部牛が戦前、どのように分布していたかをみますと、中心が北上山中、それから下北半島ですが、西のほうは愛知県くらいまでが分布範囲になっています」(「塩の道」講談社学術文庫、p.59)。「北上山中でとれる鉄を運んだのも、やはり牛です。南部牛に鉄をつけて関東平野までもってくる。川口(埼玉県)のようなところが、大きな鋳物の産地になったのもそのためだと思いますが、ここまでもってきて鉄を売ったあと、東北の人たちはその牛を、もう一度向こうへ追っては帰らなかったのです。馬なら連れて帰ったのでしょうが、鉄を売ったついでに牛も売ってしまい、帰るときはお金だけもって帰る。途中で少々極道もでき、牛の面倒もみなくてもすむということになる。鉄の場合に限らず、塩の場合も、これと同じことだったのではないかと思っています」(同上)。 黒毛だった在来種の南部牛は、明治になって海外種(ショートホーン種)と交配されて肉牛としての品種改良が進み、褐毛の「日本短角種」に変身し、夏山冬里といわれる放牧主体の飼い方、放牧地での自然交配、赤身主体の肉質が特徴の「いわて短角和牛」のブランドとなっている。 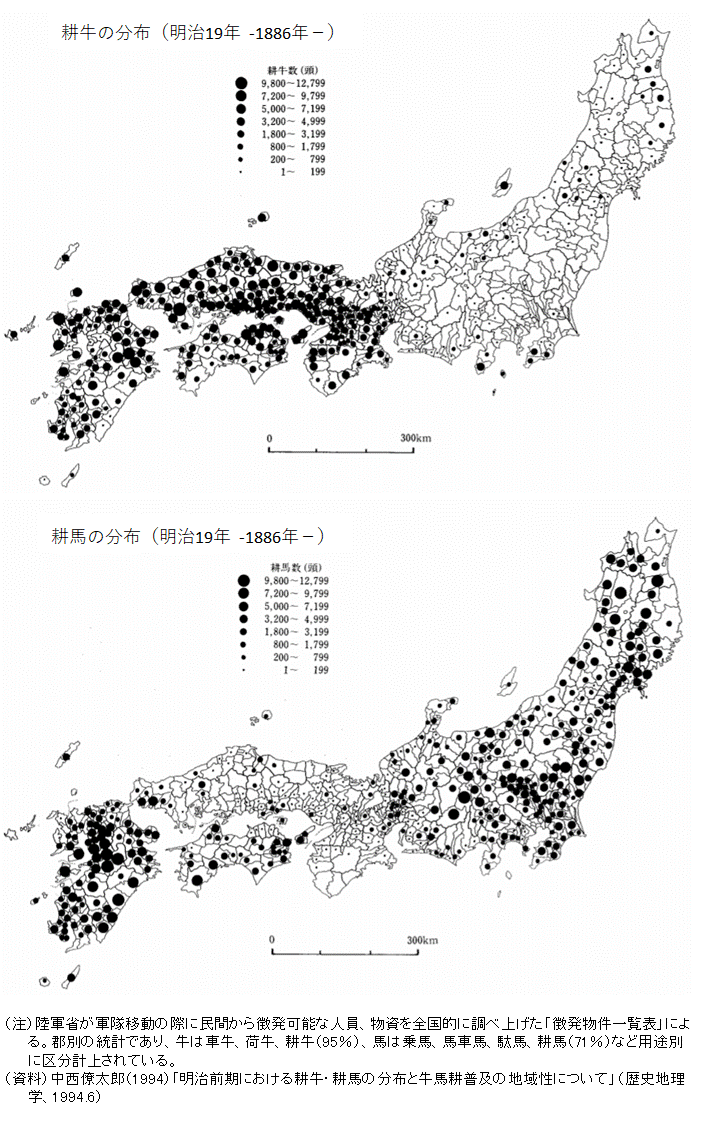 (2019年12月31日収録、2020年1月11日耕牛・耕馬分布図、7月20日更新、南部牛など東日本の牛産地、7月22日都道府県大正データ凡例「役肉牛」→「牛」、7月24日役畜としての牛馬の歴史の引用、蘇の貢納地、黒毛和種の由来、2021年12月9日宮本常一引用、2022年2月27日脇田晴子引用)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||