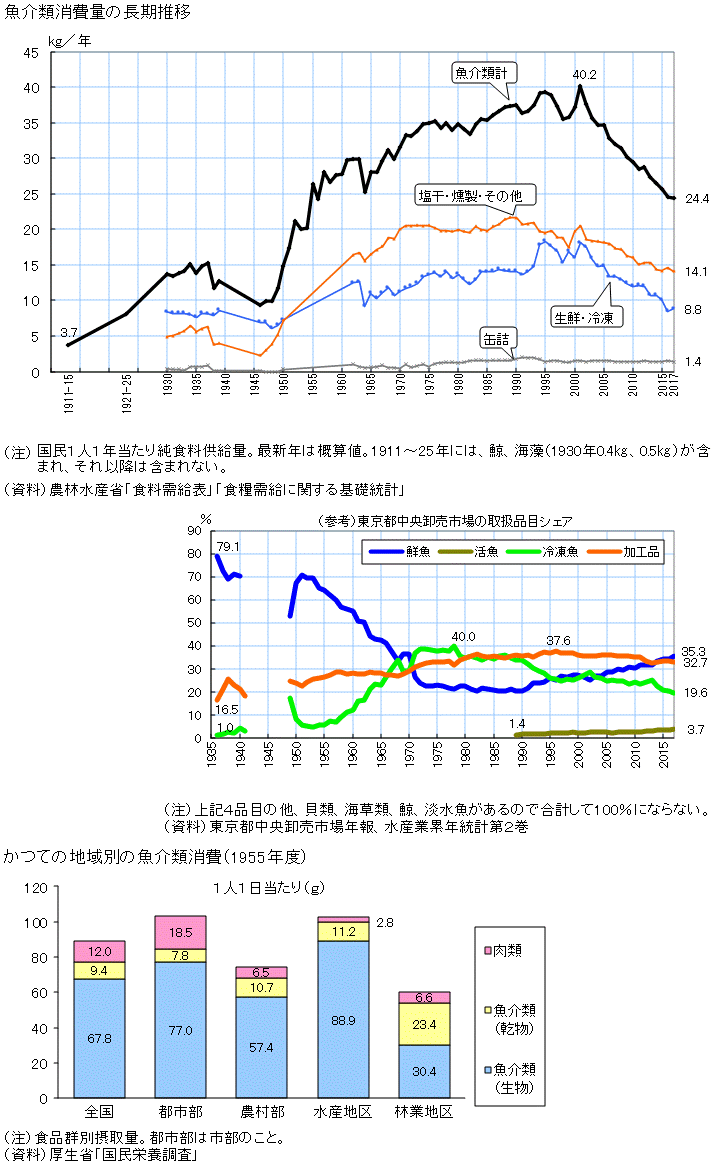
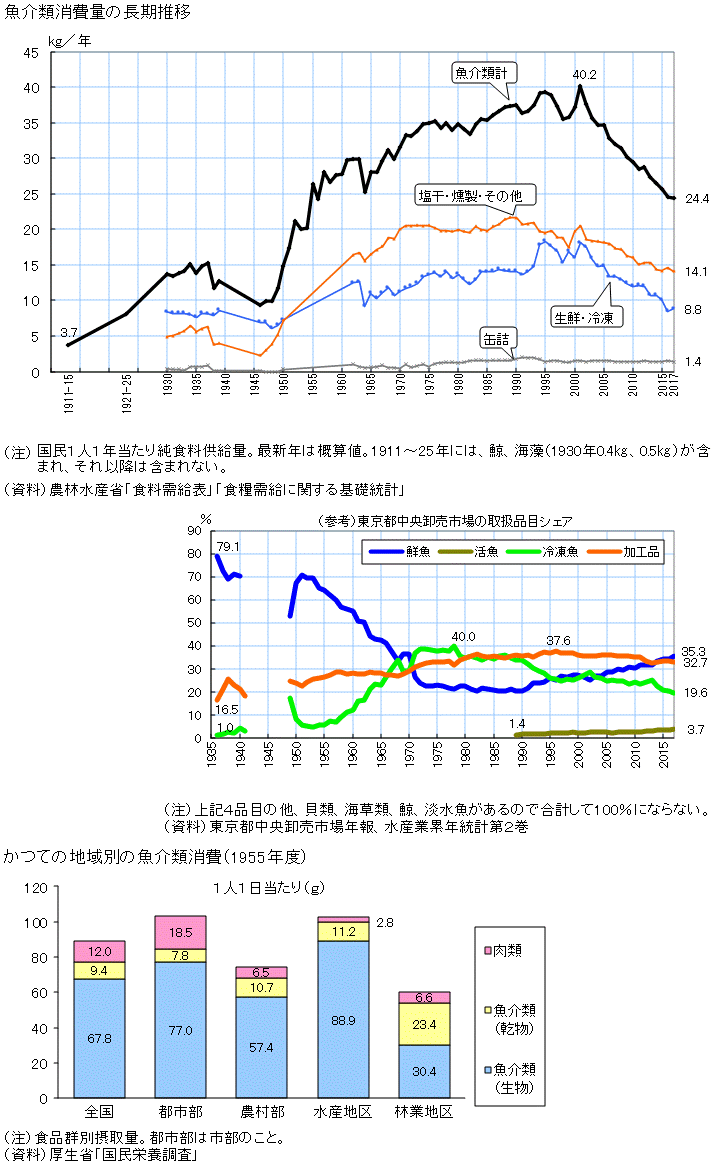
|
日本人は魚食民族として自他共に認めているところである。生の水産物を刺身で食する習慣は、今では、世界に広がりつつあるものの、かつては日本人ならではのユニークな食文化であった。 原始時代にまでさかのぼれば、貝塚遺跡には、200種類以上の魚貝類の骨が含まれ、原始日本人が捕獲していた水産物の幅が広かったことがうかがえる。古代の文献には貢ぎ物としての水産物が多く登場する。 江戸時代にはいると江戸・大阪に人口が集中し、日本橋魚市場、雑喉場(ざこば)魚市場を通じて水産物が都市住民に供給された。天ぷらの起源は1616年、日本橋に魚河岸が出来たときから露店で売られていたといわれ、真偽はともかく、德川家康が鯛の天ぷらを食べて食あたりを起こし死んだという話は有名である。 魚を蒸した米で長期間漬けこんで発酵させた保存食品である「なれ鮨」が古来より存在したが、江戸中期には江戸前の魚が珍重され、19世紀はじめには、「なれ鮨」をファーストフード化した食品として、酢飯に刺身をのせた「にぎり寿司」も登場した。それでも、最初は魚介類はすぐに悪くなるので、醤油漬けのすしねたを使っていたといわれる(なれ鮨の典型である鮒鮓については図録0340参照)。 日本の漁業は江戸中期から本格的な発展の道に入り、俵物三品、すなわち干し鮑、フカヒレ、煎りナマコ、及び諸色の中の昆布は幕府の専売品として重要な水産輸出品となった。 このような魚食の歴史をきき、また海岸線の長い島国という国土条件を思うと、さぞかし日本人は古来多くの魚介類を消費していたと考えてしまうが、実は、明治期の日本人の水産物消費量は、図に見るように現在の10分の1のレベルと今と比べかなり少なかった。1911~15年(明治44年~大正4年)平均の年間消費量(純食料供給量ベース)は3.7㎏と2011年の28.6㎏とは比べものにならない。 戦前において漁業生産は拡大していたが、漁獲物の多くは、ニシン、イワシであり、水産物の半分近くが魚粉、飼料利用に回されていたため、食用向けの水産物供給はそれほど多くなかったという側面もある。 明治以降、大正、昭和戦前期と魚介類消費は伸びていったが、戦時中は、漁船が輸送、監視のため徴用されたこともあって、消費が落ち込んだ。そして、戦後は急速に漁業生産が回復すると共に、一層の魚介類消費の普及が進み、まさに魚食民族と呼ぶにふさわしい食生活パターンとなったが、最近は、水産物に遅れて消費が急増した肉類との競合で魚介類消費は低迷している。 戦前については、少し反省してみると分かるとおり、自動車もなければ冷蔵庫も製氷・冷凍技術もない時代に、ただでさえ腐りやすい鮮魚を日本人が皆食べていたとは考えられない。塩干物など加工魚介類にしても、手間と経費がかかる高価な食べ物だったと想像できる。 大正、昭和と、動力船化等を通じた漁業技術の発展、また鮮度を保てる運輸・保冷技術の発展、そして塩干、すり身、缶詰製品など水産加工技術の発達により、肉類に先行して、動物性たんぱく質の供給の重要な柱として水産食品が普及していった(図録0280)。 そうした動きがかなり進んだ戦後の1955年においても、3つ目の図に見られるように、魚介類消費は、地域性が目立っていた。すなわち、1人1日当たりの魚介類(生もの)消費量は、水産地区では88.9gと多かったが、山間の林業地域では、30.4gと約3分の1程度と少なかった。人口の多い都市部は、まっさきに人口集積地へ向けた流通が発達した結果、77.0gと水産地区より若干少ないレベルに達していたが、農村部では、なお57.4gと低レベルであった。山間部の林業地区では生鮮魚介類は全国の半分以下であり、何とかたんぱく源を得ようと魚介類の中でも乾物の消費が多くなっているのも印象的である。末尾のコラムでもふれた通り、内陸部における生鮮魚介類への渇望は半端ではないのである。なお、この図では都市部では、他地域に先行して肉類消費が拡大しつつあった点も目立っている。 全国都市の鮮魚消費量を調べた図録7236によれば、1955年段階では、鮮魚消費は西日本の方が多く、また内陸部より海沿いの都市で多いという地域差があったが、これも、西日本の方が海洋性の高い風土を有しているためだと考えられる。 戦前の段階では、おそらく、都市と農村、漁村と山村の水産物消費格差は、さらに、大きかったと想像できる。このため、日本人平均では、魚介類消費は、思ったほど多くはなかったのだ。 なお、鮮魚、冷凍魚、加工魚、活魚といった流通形態の変化について概観すると、戦前は、保存性のよい塩干物など加工魚が多かったのではと想像すると、それは誤りで、むしろ、戦後、加工魚が鮮魚を上回ったのに対して、反対に、鮮魚の方が多かった。塩など加工コストが案外高かったこと、加工品目が豊富でなかったためと考えられる。戦後は、すけそうだらを使ったすり身製品、魚肉ソーセージの開発など水産加工が発達し、消費も鮮魚を上回って拡大した。一方、鮮魚と冷凍魚を比較すると、1950年代~60年代に冷凍魚が多くなり、鮮魚と逆転した。その後、コールドチェーンの一層の発達、鮮度保持技術の発達、鮮度志向の高まりにより、1990年代にはいると生鮮度の高い形態へのニーズが高まり、加工魚に対して鮮魚・冷凍魚が、冷凍魚に対して鮮魚が、また鮮魚に対して活魚が、シェアを上昇させるようになった。 このように日本人の魚介類消費は、量的に、地域的に、また質的に、大きな変化を遂げてきたのである。どの地域でも家庭で気軽に刺身を食べられるようになったのは最近のことなのである。 そして、21世紀に入ると魚介類の消費は2001年の40.2㎏のピークから一気に25㎏以下に急減している。
(2007年1月19日収録、2013年4月27日更新、2018年12月31日更新、2021年8月7日3つめの図の欠落を回復、コラム追加)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||