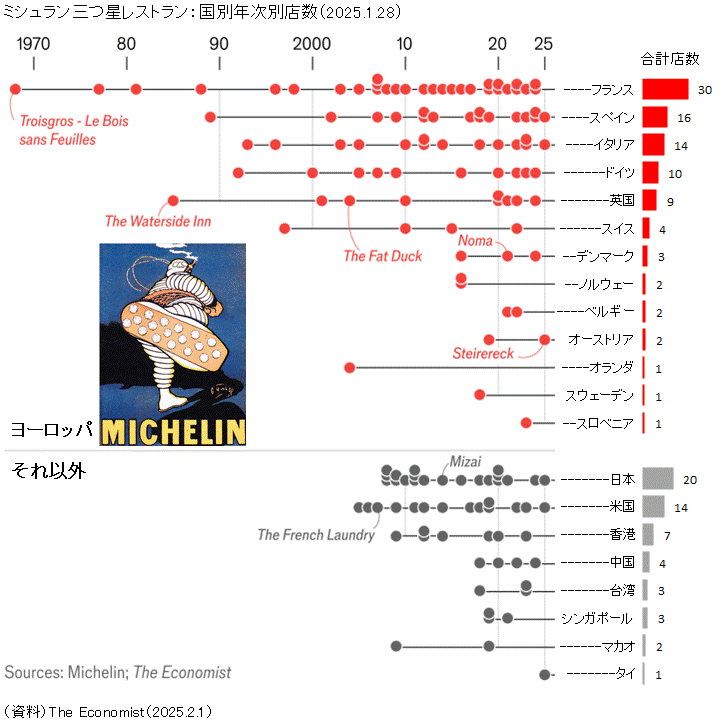
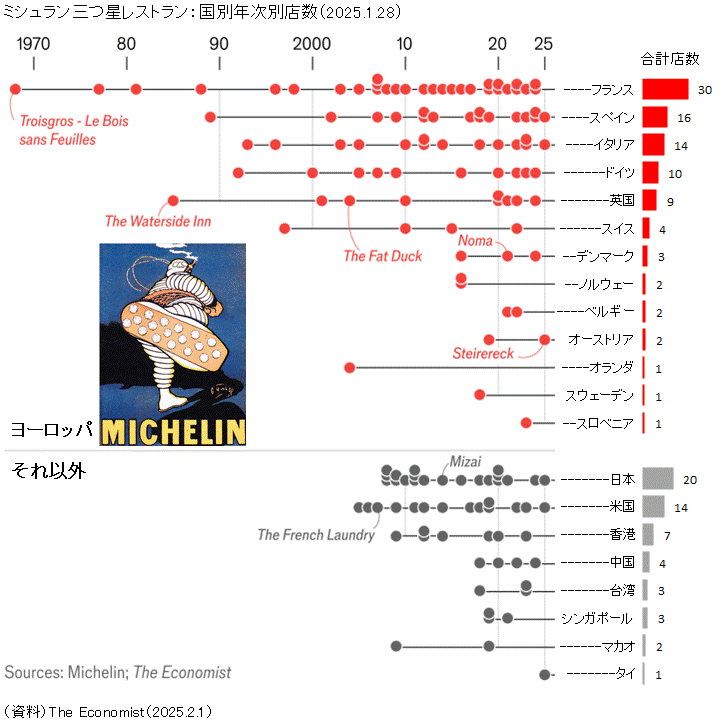
|
1900年、アンドレとエドゥアールのミシュラン兄弟は、タイヤの売上を伸ばす手段として、フランスの道路ガイドをつくることにした。最初の本は、地図や自動車整備工場の所在地といった実用的な情報を集めたものだった。その後、ドライバーは自分の燃料も必要としていることに気づき、レストランのおすすめ情報も充実させた。同社は1926年に初めて星によるランキングシステムを導入した。そして1世紀がたってミシュランガイドは3,000万部以上を売り上げ、ヨーロッパを中心に世界のレストランの標準的な評価基準となっている。 「星を獲得できるのは、最高ランクのレストランだけだ。世界中の飲食店約1,180万軒のうち、現在1つ星以上を獲得しているのはわずか3,647軒(0.03%)である。そのうち82%は一つ星を獲得しており、「独特の風味を持つ料理が一貫して高い水準で提供」されていることを示す。一方、13.6%は二つ星を獲得しており、「シェフの個性と才能」が光る「洗練され、インスピレーションに富んだ」料理を提供していると認められている。最高の栄誉である三つ星を獲得しているレストランはわずか149軒(図録参照)。ミシュランによると、三つ星は「料理が芸術の域にまで高められ」、シェフが「その職業の頂点に立つ」場所である」(The Economist、2025.2.1、以下引用は同記事から)。 食を取り巻く環境は時代とともに大きく変わりつつある。ミシュラン・ガイドはそうした環境変化に対して以下のようなそれなりの対応を図っている。 インターネットによってレストランを紹介・評価するサイトを皆が見るようになり、「料理批評を民主化」している。投稿者やブロガーのおすすめ発言が影響力をましている。料理店や地域自治体からの資金で動くインフルエンサーの活動やそうした資金による料理店PRも多くなっている。しかし、ミシュランはレビュアーによる複数回の秘密訪問による覆面調査にこだわり続けている。 自国料理だけでなく世界各地の料理に多くの関心が払われるようになっている。これに対応し、ミシュランの三つ星レストランは世界に広がっている。 ミシュランガイドによる世界の三つ星レストランは149軒だが、図録に掲げた通り、国別では、そのうちフランスが30軒で最も多く、日本が20軒で世界第2位。スペインが16軒、イタリア、米国が14軒でこれに次ぐ。ヨーロッパ以外では日本のほか、香港、台湾、シンガポールなどにも広がっている。 ミシュランの三つ星レストランが多い国はグルメ国といえよう。グルメ国の判定基準として食事時間の長さを取り上げた図録0210、あるいはエンゲル係数の高さを取り上げた図録0211も参照されたい。 「2004年には、星が輝くのはヨーロッパだけだった。星付きレストランの数では、依然としてフランスが最多だ。しかし、今日ではミシュランは4大陸、30カ国以上にレビュアーを派遣している。同社は43カ国でガイドを発行しており、その数は2020年以降、約50%増加している」。しかも、地方にも目を配るようになっている。例えば、米国では20年前、ニューヨークだけが評価に値すると考えられていたが、今では、アトランタ、シカゴ、オーランドなど様々な都市でおすすめレストランを見つけることができる。最近はテキサス州にも進出したという。 高級レストランの料理だけでなく、屋台料理やB級グルメにも関心が払われるようになった。1997年「質の良い充実したメニュー」を「手頃な価格」で提供するレストランとして、ビブグルマンというカテゴリーが登場している。また、環境志向、ベジタリアン志向、ビーガン志向に対応して「ミシュランは2020年、持続可能性への取り組みを示すレストランに与えられる「グリーンスター」制度を導入した(現在までに認定を受けたレストランは608軒のみ)」。 エコノミスト誌は、こうした取り組みでこれまでの100年同様、これからの100年もミシュランは存続できるかという問いを発している。答えはイエスだ。カネで動くインフルエンサーでは得られない覆面調査の専門レビュアーへの信頼があるからである。「今日では誰もが食について意見を持つことができるが、誰もが権威になれるわけではない。ミシュランは常に批判されるだろうが目の肥えた食通はこれからもミシュランを探し求め続けるだろう。劇作家であり批評家であったジョージ・バーナード・ショーがかつて書いたように、”食べものへの愛ほど誠実な愛はない”のだ」。 (2025年4月16日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||