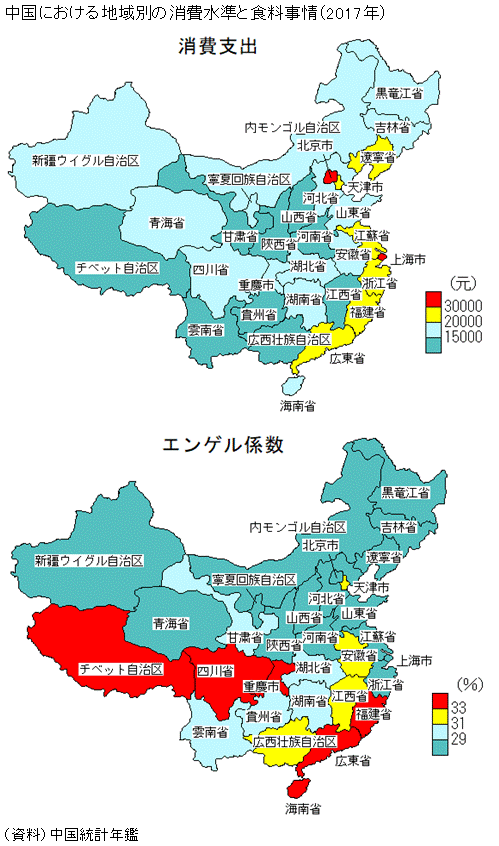
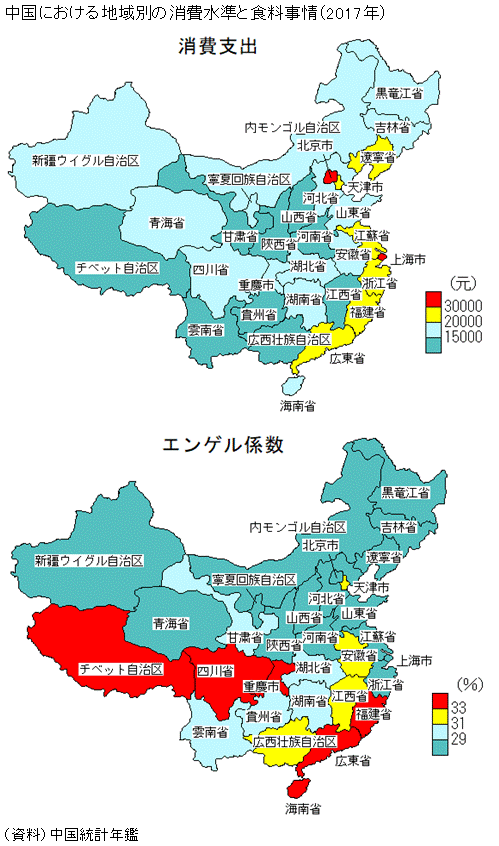
ところが、地域別に現在の状況をみると必ずしも所得の高い地域ほどエンゲル係数が低いといった形にはなっていない。 図録に消費支出レベルとエンゲル係数の両指標(2017年)について地域別の高低を示した地図を掲げたが、これを見れば分かるとおり、消費水準は、所得水準の高い沿海部で高く、所得水準の低い内陸部で低いのに対して、エンゲル係数は南高北低の構造が明瞭である。北と南とで食への姿勢の違いがあるためであろう。 ページ末尾には消費水準とエンゲル係数の相関図を掲げた。中国全体では両者の相関度は高くないが、北部地域と南部地域の域内ではそれぞれ、消費水準とエンゲル係数とが負の相関となっている。 中国では、多様で、かつ嗜好に富んだ食料消費が発展しており、特に南部ではそうした傾向が強い。このため、南部ではエンゲル係数が所得に比して高い状況をもたらしていると考えられる。「食は広州にあり」といわれる広州では、広東料理として野生動物料理が流行り全国に影響を与えたが、2003年のSARS流行以降は、新鮮・健康の方向へ急速に転換していると伝えられる。中国人、特に南の中国人は食に関して並々ならぬ意欲を示しているといえよう。 日本で評論家として活躍中である中国南部上海出身の張競はこう言っている。「もともと中国人の食事に注ぐ情熱にはすさまじいものがあった。それに長年の禁欲の反動なのか、食に対する欲求は日に日に増大している。人々は給料をもらってまず第一に考えるのは食べることだ。いまも市民たちの食にかける金は多い。生活水準が高くなっても、エンゲル係数はいっこうに下がらない。欧米の経済学者の理論は中国には当てはまらないようだ。」(「中国人の胃袋-日中食文化考 食文化の南北差については田原史起「中国農村の現在」(中公新書、2024年)において農村調査の体験から語られている。 山西、陜西、甘粛といった北方農村では「食事において主食、とりわけ小麦に価値が置かれている。主食でしっかり腹を満たすことが重視されており、飲酒はいわば二の次である」(p.179〜180)。マントウ、水餃子、お焼きなど「主食自体がバラエティに富んでおり、飽きがこない。わずかな副食があれば十分である」(p.181)。「飲酒よりも主食が勝るのとパラレルな関係で、北方の村民は世帯を超えて他の村民と日常的に食事を共にすることは多くないようにみえる」(p.180)。中国農民は宴会でしか酒を飲まない「社会的飲酒者」なので「社会関係によって飲酒を要請されない西北農村では、冠婚葬祭時を除いて、飲酒の習慣自体をもたない農民も相当たくさんいると思われる」(p181)。 これと対照的なのが南方の農村である。南方の村落は血縁者・近親者で構成されており、「いきおい、関係者がある家に集まっての日常的食事会が、特に農閑期には頻繁に行われる。家の主人の50歳の誕生日を祝う、などと何か理由をつけたものもあるが、ほとんどの場合、確たる理由もなくあちこちで酒宴が開かれている」(p.237)。 「食事の中心は、肉類を中心とした副食と酒である。(中略)このような酒宴化した花村(江西省)の食事では、主食である米は最後の「締め」として一杯だけかき込む感じである」(p.237〜238)。「筆者は、海外農村調査に携わる者として、基本的に食べ物は何でも受け付けるタチである。しかし、(2006年当時の豚、鶏、犬などの)花村の味の濃い肉ばかりの料理には正直、参った。まだまだ貧しかった当時、主家の側も、客人には肉を出さねば面子が立たない、という感覚にとらわれていたのだろう。その後、村が豊かになるにつれ、花村の酒宴にも野菜料理が増え、肉の味付けも改善され、近年では全く純粋に食事を楽しむことができるようになった」(p.239)。 以上のような対比を知ればエンゲル係数が南部で高く北部で低いという状況もよく理解できる。 巻末には現代の東アジア諸民族のDNAと古代北方・南方中国人のDNAの分布をあらわした散布図を掲げた(篠田謙一「人類の起源」中公新書、2022年)。これを見ると遺伝的な形質における現代の漢民族の南北差は時代をさかのぼるとさらに大きかったことが分かる。古代北方中国人は今よりよりモンゴル系に近く、古代南方中国人は今より東南アジア系に近かったのである。エンゲル係数にあらわれている食の嗜好の南北差が今でも残っているのもけだし当然と言えよう。 なお、中国の1人当たりのカロリー消費の動向は図録0200、品目別の食料消費の対世界シェアの動きは図録0300に示したので参照のこと。 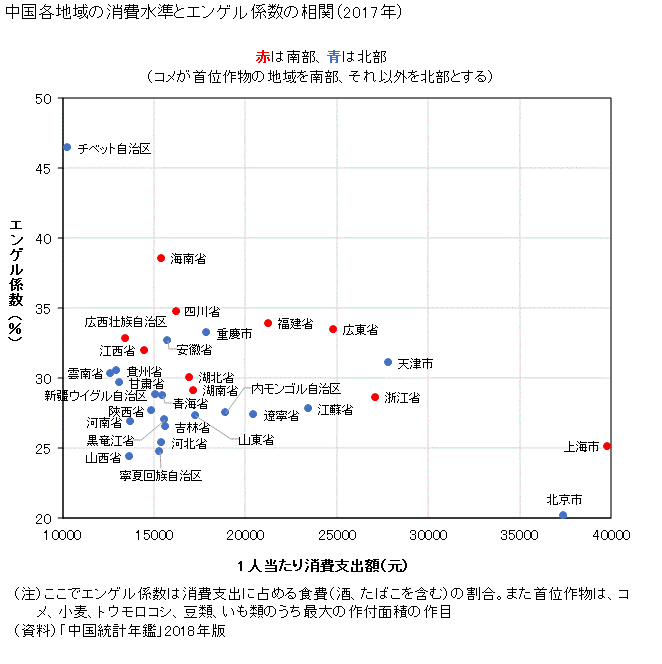 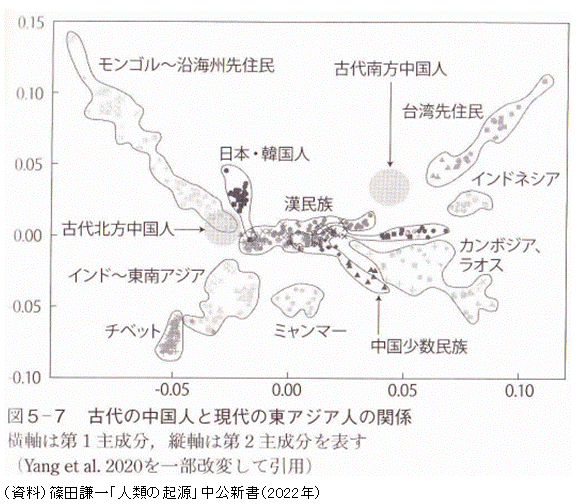 (2005年3月26日収録、2011年4月18日張競引用、2021年3月8日更新、都市世帯から全国世帯対象へ、相関図も、2023年2月20日篠田謙一「人類の起源」図、2024年4月18日地図に江西省の表示がなかったのを修正、6月17日田原史起「中国農村の現在」引用)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||