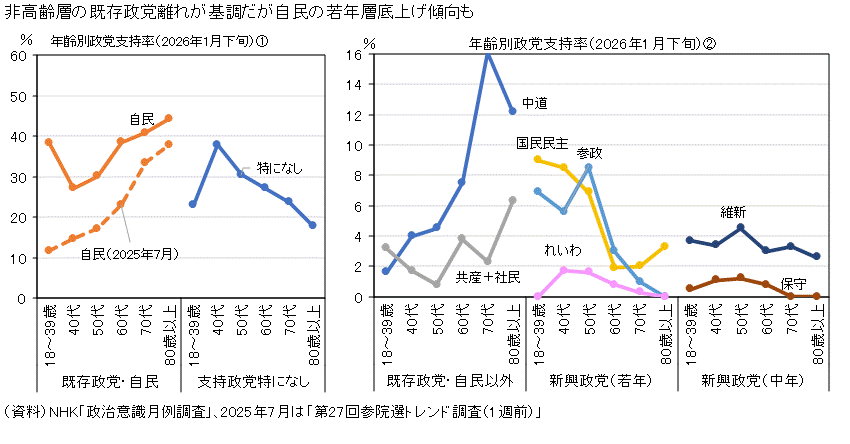
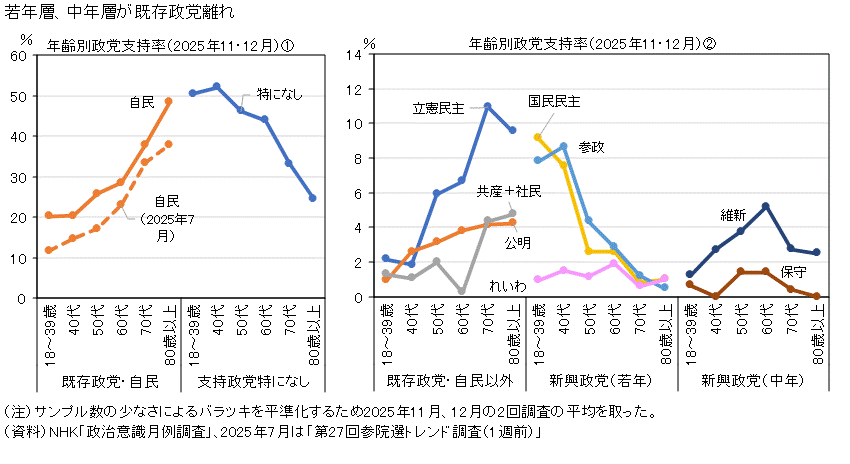
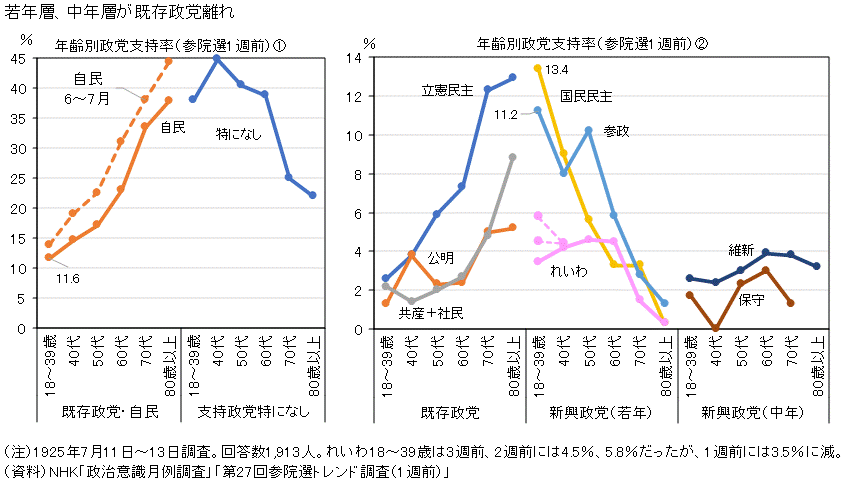
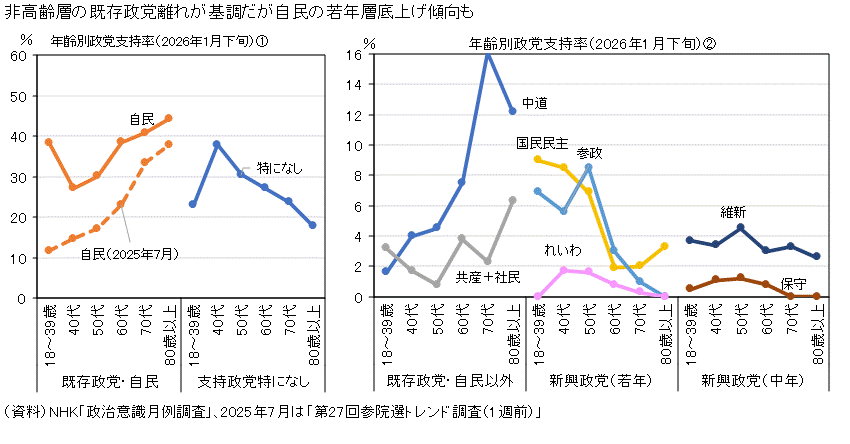
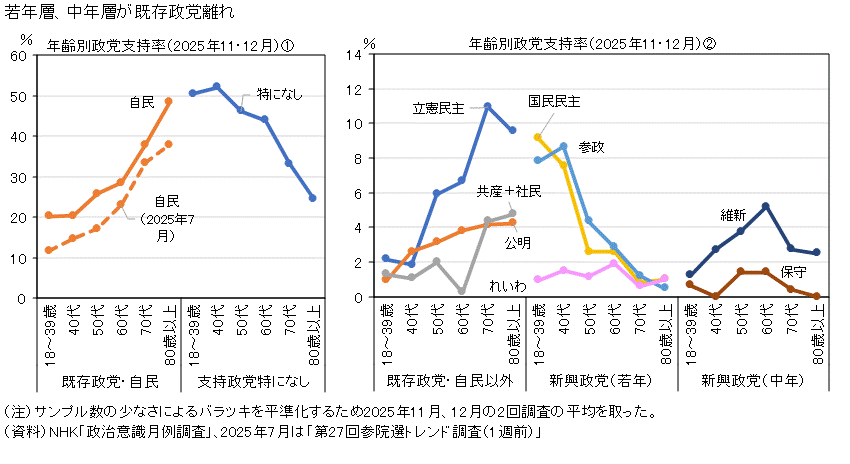
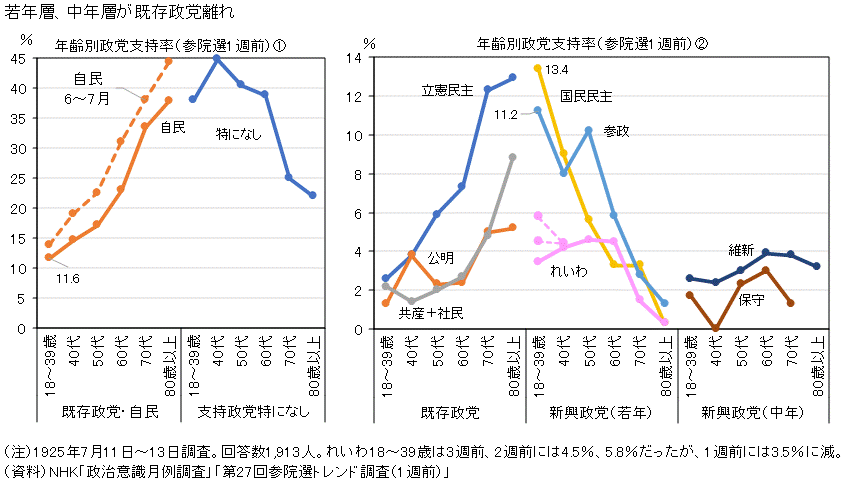
| 内閣支持率 | |||||||||||||||||||
高市政権(自民・維新連立政権)となって自民の支持率が全体に上昇している。これは特に若い層で国民民主や参政の支持層をシフトさせているからと思われる。立憲民主と公明がつくった中道はやはり既存政党と同様中高年が支持。これらを除くと2025年7月の状況とそう大きくは変わっていない。 (2025年7月:参院選1週前) 自民党に代表される旧来型の政党を既存政党とすると2025年7月の参院選を特徴づけているのは、既存政党への信頼が失墜し、既存政党以外の政党への期待が高まった点にある。 こうした動きの背景としては、裏金問題や不適切発言など、自民党という長期的に政権を担ってきた既存政党の不祥事が相次いでいるからというより、社会の機能不全の認識(社会が壊れている!)から、旧来型の政党ではそもそも国民の期待に応えることが無理なのではないかという認識が国民の間に広まっているからだと考えられる。 ここでは、既存政党と新興政党の違いについて、政党を支持する年齢層の違いから明らかにしておこう(NHK調査の原データ)。 既存政党の代表格である自民党は年齢があがるほど支持率が上昇する。参院選1週前の時点での年齢別の政党支持率をあらわした上図からもこの点は明らかである。 これを見ると自民党の支持率は50代までは10%台に過ぎないが、70代以上では35〜40%となっており、年齢傾斜が特徴的である。若者の保守回帰が、以前、話題となったが、そういう状況には現在はなっていない。少なくとも、保守回帰があるとしても自民党には向かっていない。 なお、選挙期間中は政権党以外の政党の情報もマスコミを通じて多く流されるため、政権党の支持率は低下するのが通例である。この図でも6〜7月の月例調査から投票日1週間前にかけて各年齢で自民党の支持率が低下しており、それが新興政党に流れたと考えられる。 支持政党が「特になし」と回答したいわゆる無党派層は自民党とは逆に若年層ほど多い右下がりの傾斜を示している。 既存政党離れを起こしている有権者は、一方で無党派層を形成するとともに、他方で新興政党支持に向かっている状況が明らかである。実際の選挙で無党派層の票が既存政党に流れるのか、それとも新興政党に流れるのかで結果が決まってくるというのが定番の選挙予想であるが、年齢的な構造からは、当然、新興政党に多く流れるに違いない。投票率の高低がその程度を決めることになるのである。 年齢があがるほど支持率が上昇するのは、自民党だけでない。古くからの政党である公明党や共産党・社民党も同様である。これらもまた既存政党と言うべきだろう。 一方、立憲民主党も同様の傾向が目立っている。立憲民主党と国民民主党は両方ともかつての民主党から生まれた政党であるが、国民民主党は年齢層が若いほど支持率が高く、立憲民主党とは正反対の性格を有している。生まれた時期は同時期でも、支持層の違いからは、立憲民主党は既成政党、国民民主党は新興政党と位置づけられよう。 年齢があがるほど支持率が上がる政党を既存政党、それ以外を新興政党と位置づけると、新興政党も実は2分される。 すなわち、一方で、若年層ほど支持率が高いのが国民民主党、参政党、れいわ新選組(注)。他方で、若者と言うより中年以上の支持が特徴であるのが日本維新の会、日本保守党という2区分である。 (注)ただし、れいわ新選組の18〜39歳層の支持率は参院選2〜3週前には各年齢層のうちで最多だったが、直前1週目には落ち込んだ。参政党に若年層からの支持が食われた格好である。 既存政党にも左右両派の政党があるように新興政党にも左右両派の政党が属している。れいわ新選組は左派系であるが、今回注目の的となっている「日本人ファースト」をうたう参政党は日本保守党とともに、むしろ、保守的な政見をもっている。 就職氷河期に安定雇用を逃した困窮層や財務省デモ参加者などでは、消費税廃止という共通の公約に賛同し、左右に関係なく投票先、れいわ、参政党2択になる傾向があるとの取材報道もある。こうした層では消費税廃止をトーンダウンさせた国民民主の影は薄くなっているという(東京新聞2025.7.13)。 新興政党の中には、党首に注目が集まったり、党首の発言がセンセーショナルだったりするポピュリスト的な性格の政党が目立つ。世界的な潮流ともなっているポピュリズム政治がわが国にも波及するかに関心がもたれている(この点に関するプレジデント・オンラインの私の記事はここ)。 なお、既存政党と新興政党との違いは、新興政党で男性の支持率が女性の支持率より高くなっている点にもあらわれている(下図)。女性は新規性の高い政治潮流に対して男性より懐疑的なのであろうか。 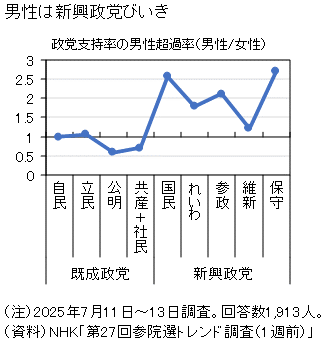 実際の参院選では、ここでふれた新興政党が大きく躍進し、既存政党はすべて落ち込んだ。こうした状況を比例票の推移から図録5231で見ているので参照されたい。 (2025年7月22日収録、12月26日最新追加、12月27日12月値から11〜12月平均値へ変更、2026年1月13日更新、1月26日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||