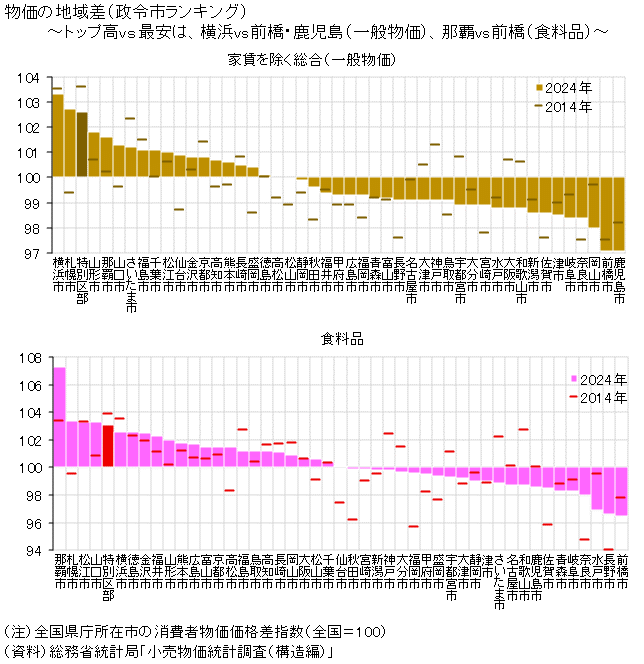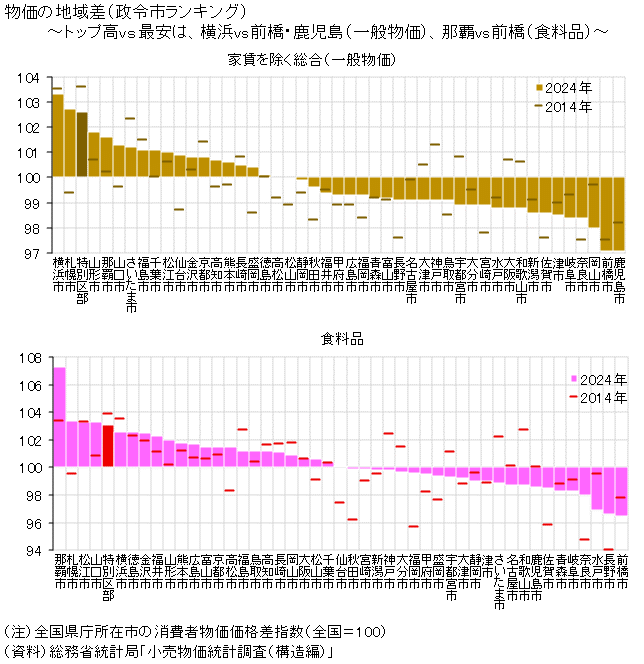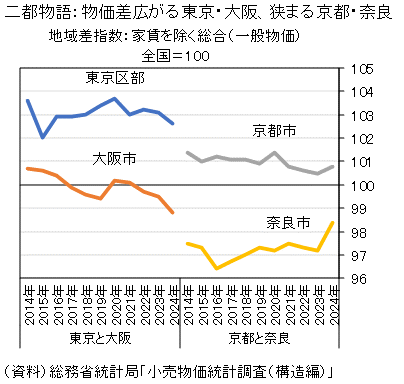米や食品をはじめ様々な品目の物価高に日本国中が揺れている。米の価格や消費者物価指数をはじめ、物価上昇にかんするデータは報道紙面やネット上にあふれているが、消費者物価の地域差に関する統計データはほとんど国民の目に届いていないのでここで紹介することとしよう。
物価高を示すデータは、生活の大変さをあらわしたり、政府に対策を迫るという意味では役に立つが、個人としてできることは、物価の高い地域を避け、少しでも物価の安い地域に住むことだろうから、こうした地域差のデータはそうした意味で有意義だろう。
全国を100とした場合の各地域の物価水準が「消費者物価地域差指数」(総務省統計局)として公表されているが、「総合」には住宅価格は含まれないが、家賃は含まれている。都心部の家賃はどうしても高くなる。消費者物価の対象となる家賃は、一般住宅用の家賃だが、どうしても業務用の需要にも影響されるだろうから、都心の家賃水準は過当に高い可能性もある。そこで家賃を含む「総合」と「家賃を除く総合」の2種類の指標が計算されている。
そこで一般物価というべき「家賃を除く総合」で地域差を比較した方がよいとも言える。
図では、価格差指数の県庁所在市別の結果をつかって各地の物価水準の特徴を概観している。指標としては、一般物価(家賃を除く総合)と食料品の価格を取り上げた。参考までに10年前の値も横棒アイコンで示した。
一般物価がもっとも高いのは横浜の103.3(全国より3.3%高)であり、もっとも低いのは前橋、鹿児島の97.1(全国より2.9%安)である。横浜に次いで高いのは札幌(102.7)であり、東京区部(102.6)は第3位に過ぎない。
一般物価のランキングを見ると以下のような点に気がつく。
- 〇大都市だからといって物価が高いわけではない
- 横浜、札幌、東京区部と上位3位の都市を続くので、大都市では物価が高いと思わせるが、福岡(99.3)、名古屋(99.1)、大阪(98.8)など他の大都市は全国平均以下である。特に大阪は全国でもかなり低い方である。逆に、物価上位4〜6位の山形(101.8)、那覇(101.6)、山口(101.3)は中小都市であり、小さな都市でも物価が安いわけではない。
- 〇東京は高いが大阪は安い
- 東京と大阪という日本の2大中心都市でも物価は大きく異なる。吉本芸人のように大阪に住んで東京で働くのはリーズナブルなやり方といえる。メリット分は新幹線代で消えてしまうだろうが。東京と大阪の差が広がる傾向についてはページ末尾参照。
- 〇京都は高いが奈良は安い
- 日本の2大古都の物価も大きく異なる(京都100.8、奈良98.4)。京都の高収入企業で働き、奈良から通うのは合理的かもしれない。京都と奈良の差が縮まる傾向についてはページ末尾参照。
- 〇熊本は高いが鹿児島は安い
- 同じ南九州で隣接県の県庁所在市であっても、熊本は物価が高く(100.6)、鹿児島は安い(97.1)。
- 〇物価安の都市に共通点は見当たらない
- 低物価都市5位は低い方から鹿児島、前橋、岡山、奈良、岐阜である。これら5都市の地域性に共通点を見出すのは困難である。
食料品価格のランキングについては、那覇が特段に高い1位であり(107.3)、札幌、松江、山口がこれに次いでおり、東京区部はこれらを下回る5位である(103.1)。
食料品がもっとも安価なのは前橋、長野、水戸、奈良、岐阜といった内陸都市のようだ。
一般物価と食料品価格の地域差ランキングを見比べると以下のような点が目立っている。
- 〇那覇は両方高いが、特に食料品が高い
- 〇東京の食料品価格は全国5位と特段高いわけではない
- 〇札幌は両方高い
- 〇前橋は両方安い
- 〇中国地方では山口が両方高い
- 〇近畿地方では奈良が両方安い
- 〇大阪は、一般物価は安いが食料品はそれほど安くない
- 〇さいたまは、一般物価は高いが食料品は安い
- 〇岡山は、一般物価は安いが、食料品は安くない
2014年との比較では以下のような点が目立っている。
- 〇東京の一般物価は1位から3位へ下落(図録4707参照)
- 〇札幌の一般物価は全国水準以下だったのが2位へと大きく上昇
- 〇高かった東京、さいたま、神戸、大阪などの一般物価は下落し、全国平均に近づくか、それを下回る
- 〇安かった長野、宮崎、佐賀、奈良などの一般物価は上昇し、全国平均に近づく
- 〇那覇の食料品価格は大きく上昇
- 〇東京の食料品価格は全国1から全国5位へと低下
- 〇秋田、福岡、佐賀、奈良、長野などの安かった食料品価格は全国水準に近づく
2014年からの地域差指数の毎年の推移を、地域差の大きな東京と大阪、および京都と奈良で対比させたデータを以下に掲げた。
東京と大阪では差が広がり、京都と奈良では差が縮まる傾向が認められる。