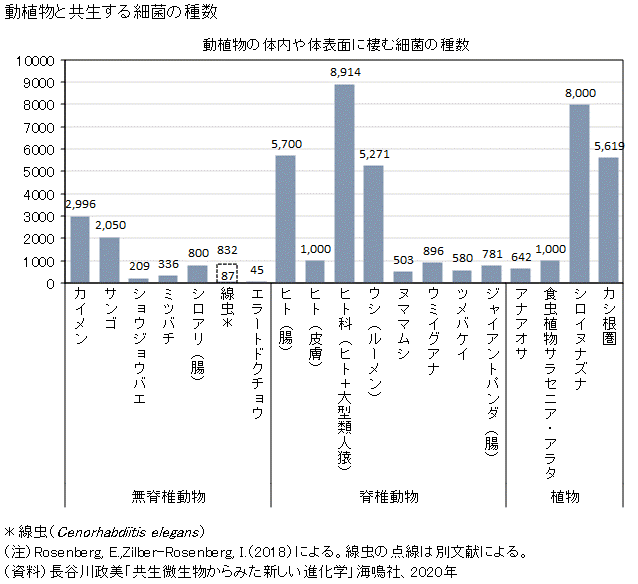
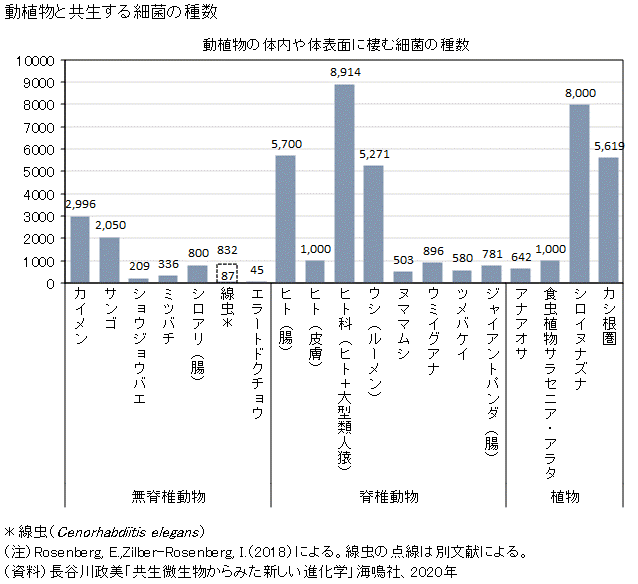
|
マイクロバイオームの中でも腸内細菌が健康上重要な働きをしていることが最近、よく知られるようになった(腸内細菌叢については図録1966参照)。 こうした点から、ラグビー日本代表の松島幸太朗選手らの便をモデルにした健康サプリが開発されたり、潰瘍性大腸炎などを「便移植」で治療する試みがなされている。また、欧米人とアジア人の新型コロナの死亡率の差がもともとすまわせている微生物叢の違いに由来するとされるなど、腸内細菌については種々の点から関心が高まっている。 ヒトの細胞数は37兆個であるが、腸内細菌の総数は100兆個という推定がよく引用される(最近では38兆個という研究も)。ヒトの遺伝子数は2〜2.5万だが、いろいろな人のヒトの腸内細菌叢の細菌種の遺伝子を合計するとその400倍ぐらいになる(長谷川政美「共生微生物からみた新しい進化学」海鳴社、2020年、p.7〜8)。マイクロバイオーム(微生物叢)の働きに関しては未知の部分が多い。 ここでは、さまざまな動物や植物と共生する細菌の種数をまとめて示している。 節足動物や脊椎動物など我々にとってなじみ深い動物である左右相称動物は口から肛門に至る消化管をもっている。これに対して、左右相称動物がカンブリア爆発とともに視覚の発達を伴いながら一気に広がる以前から存在した海綿動物のカイメンやかつて腔腸動物と呼ばれていた刺胞動物のサンゴは胃体腔と呼ばれる袋状の消化器官を有し、肛門はなく袋の口から排泄する点が特徴である。サンゴはポリプと呼ばれる個体がたくさん集まった群体である。 こうしたカイメンやサンゴでも胃体腔内に多くの細菌を棲まわせている。このことから、ヒトの腸内細菌との関係は、動物がはじめて消化管(袋状の胃体腔をふくめて)をもつようになった頃まで遡ると考えられるのである(p.46)。 「ビタミンB12を合成できるのは細菌だけであり、ウシなどの反芻動物ではルーメンと呼ばれる反芻胃の第一胃の中で細菌によって合成され、反芻動物の健康を支えている。従って、ポリプの胃体腔内でも細菌が食べたものの消化を助けたり、ビタミンB12を合成してポリプの健康な生活を支えているものと思われる(注)」(p.45)。 (注)ヒトも大腸内で細菌がB12を合成しているが、せっかくのビタミンも糞として排泄されてしまうので食品から摂取しなければならない。ウサギは「食糞」により、盲腸にすまわせている微生物によるその他の発酵栄養分とともにこれを活用している。 反芻動物であるウシの第一胃(ルーメン)の細菌種数はほぼヒトの腸内細菌と同じであるが、細菌以外にも多くの微生物をすまわせている。「反芻胃には真正細菌、古細菌(メタン生成菌)、原生生物(繊毛虫や鞭毛虫)、真菌など嫌気性の微生物がたくさん生息していて、反芻動物が食べたものを消化している。このルーメン発酵によって、微生物の増殖と栄養素の転換が起こり、合成された必須アミノ酸に富む良質の微生物たんぱく質は、反芻胃の下流にある消化器官で消化吸収され、宿主動物のたんぱく質となる」(p.163)。 ウマも草で生きる動物であるが、微生物が消化する場所が胃でなく、結腸(大腸)であるため、ウシのようにセルロースが有効なアミノ酸にならないので、「鯨飲馬食」という言葉があるように、馬はいつも食べていなければならない(注)。 (注)牛のように胃で発酵させた方が、できた栄養分を小腸で吸収できるので、結腸で発酵する馬より効率がよい。牛と馬の便を比較すると「ウシでは植物が完全に消化されているのに、ウマでは未消化の植物がたくさん含まれている」(岩堀修明「図解・内臓の進化」講談社ブルーバックス、p.117)。牛より馬が多かった東日本でも、塩や鉄などの運搬には牛が多く用いられていたのであり、その理由は夜横たわれるので野宿に適しているのに加えて、道草を食べてエネルギー源にできるからと宮本常一は指摘しているが(「塩の道」講談社学術文庫、p.48、p.57)、これも同様の根拠によるものであろう。耕作や運搬には牛の方が適しているのに何故東日本では馬飼育の方が優位となったかというと、やはり軍馬としての適性を仮定するしかないのでなかろうか(図録0448参照)。 胃を発酵の場としているのは、ウシやヒツジなどの偶蹄類のほか、カンガルーなどの有袋類、ナマケモノなどの異節類である。一方、微生物発酵の場として、クマは小腸、ウサギやダチョウは盲腸を使っている。さらに、コロブス類と呼ばれる霊長類のテングザルは「歯食いサル」と呼ばれるようにもっぱら木の葉を食べるが、前胃に微生物をすまわせている。鳥類のツメバケイは「空飛ぶウシ」と呼ばれ、食道に続くそ嚢(そのう)で食べた植物の葉を発酵させる。 シロアリの「食物は主に枯死した植物で、その主成分はセルロースである。しかし、下等シロアリではセルロースを分解する能力が低く、消化管内の共生微生物(主に原生動物)の助けを得ている。一方高等シロアリでは、シロアリ自身もセルロースを分解する酵素(セルラーゼ)を持っていることが確認されている。これは遺伝子の水平伝播を示唆していると考えられている。シロアリの腸内共生原生生物は、セルロースを酢酸まで分解し、これをシロアリの栄養源として提供する」(ウィキペディア)。 窒素は植物の生育に必須な養分であるが、大気中に大量に存在する窒素を植物が直接利用することはできない。根粒菌はマメ科植物の根に住みつく土壌細菌で、空気中の窒素を植物が利用できるアンモニアに変え、マメ科植物に供給している。ダイズなどのマメ科植物は、根粒菌と共生することで、空気中の窒素を利用できることから、窒素栄養の少ない土地でも生育できるのである。 これと同様のことを牛は、胃に棲まわせている微生物との共生で実現し、草しか食べないのに肉質に富んだからだをつくることができている。 大豆たんぱくを貴重なたんぱく源としてきたかつての日本人も、牛肉を食べるようになった現代日本人も、生きていくのに必要なたんぱく質摂取が可能なのは、動植物と共生する微生物のお陰なのである。 さらに、人間の腸内細菌にも窒素固定する能力があるのではないかと疑われるようになっている。 いも類を主食とするニューギニアのパプア人は、肉などのたんぱく質をあまり摂らないのに筋骨隆々のからだをしている。1960年代の研究では、パプア人の成人では摂取する窒素の量が1日におよそ2グラムなのに、糞や尿として排泄される窒素量はその倍近くである。どうやら、パプア人の腸内には豆類の根粒菌のような窒素固定細菌がいるのではないかと推測されるようになった。そして、「2016年になって、長崎大学の猪飼桂と東京大学の梅崎昌裕らのグループは、パプア人の糞便のなかに窒素固定活性をもつ細菌が含まれることを見出した。摂取した量より多くの窒素を出すということは、やはり彼らの腸内で窒素固定しているからであると考えられるのである」(長谷川政美前掲書、p.71)。 明治時代に日本で医学を教えたドイツ人医師ベルツは、当時の日本人が穀物、豆、イモ、野菜などしか食べないのに、驚異的な運動能力を有することを車夫と馬車の耐久力比較実験で確かめた。「当時の栄養学者らは、日本人はもっと肉類を食べなければならないと主張したが、ベルツは自分の実験から、日本人の食事は栄養的に改善を要する点はないと考えたのである。豆や精製していない穀物にはたんぱく質が含まれるが、それ以外にも車夫の過酷な労働を支える別の要因が彼らの腸内細菌にあったのかもしれない」(p.72〜73)。 そうだとすると、近年の低糖質ブーム(ロカボブーム)はまったくの虚妄の理論に基づいていることになる。 (2020年10月15日収録、2021年12月10日牛馬比較の(注))
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||