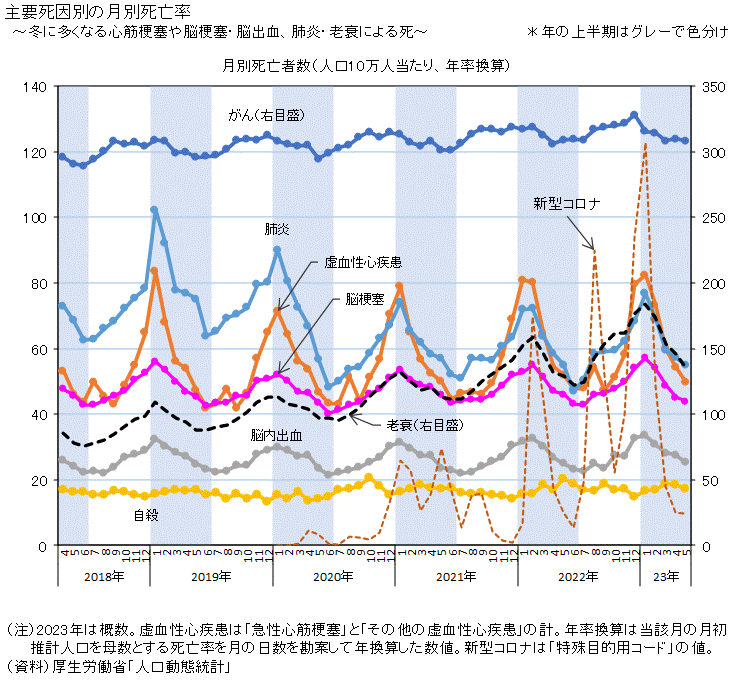
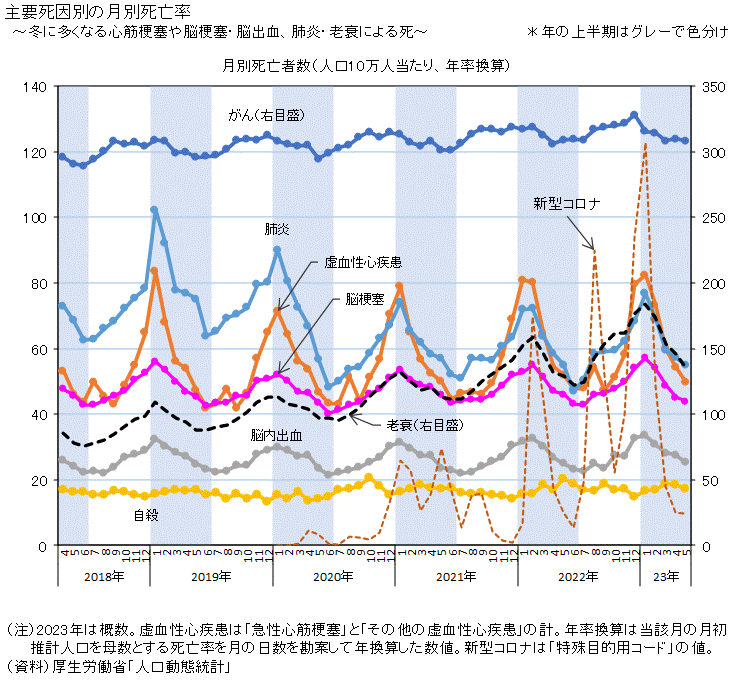
推移の折れ線グラフは、長期の傾向的変化と月別の季節変動が合成されたものと見ることができる。 季節変動に着目するとがんや自殺のように季節性が余りない死因と虚血性心疾患(心筋梗塞)、脳卒中(脳梗塞や脳内出血)、肺炎、老衰などの季節性の大きな死因とがある。 老衰死は傾向的増加と季節変動が合成した動きとなっている点が目立っている。 季節性は基本的に寒い冬の死亡率増加と暑い夏の死亡率低下である。季節性の大きな死因では「1月がピーク、6月か7月がボトム」である場合が多い。ただし、2022年は1月ではなく2月がピークとなっているなど若干の変動はある。 寒暖が影響しているとすれば、冬でも年次ごとの死亡率の高低は、長期傾向(図録2080)の影響に加えて、やはり、その冬の寒さの厳しさの程度が影響していると考えられる。 また、季節性が大きい死因の中でも虚血性心疾患だけは、夏季の低下の中でもいったん中間の8月に死亡率が上昇するW型のボトムとなっている。これは暑熱により、脱水状態が引き起こす心筋梗塞死が増えるためと考えられる。 さらに、虚血性心疾患と脳梗塞は血管が詰まることで生じる点は同じだが、両者を比較すると死亡率が低い季節にはほぼ同一のレベルであるのに対して死亡率が高い季節には虚血性心疾患の方がずっと死亡率が高い。すなわち、虚血性心疾患の方が脳梗塞よりも季節性が大きいといえる。 心房細動が原因となる脳梗塞は冬に多いが、動脈硬化が原因の脳梗塞は汗をかいて「血液がドロドロ」の状態になりやすく、血栓が生じやすい暑い季節にも注意が必要だとされる。心房細動による血栓が原因である心原性脳塞栓症は、比較的太い動脈に詰まり、広範囲の脳梗塞をきたすことが多く、高齢者に多くみられることから死亡率も高い傾向にあると言える。 なお、新型コロナ感染症による死亡については、死因は特殊目的用コード(22000)に格付けされることになっており、これについても図示したが、季節性はあるようなないような感じであり、インフルエンザとは異なっている。 (2021年6月4日収録、7月19日更新、脱水による心筋梗塞、8月20日更新、2022年6月27日脳梗塞の季節性補訂、2023年10月18日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||