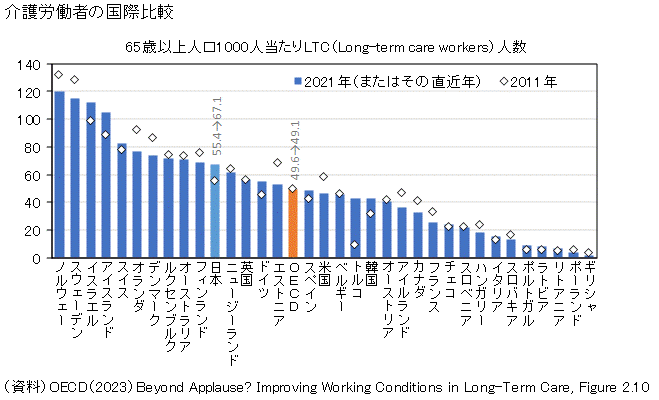
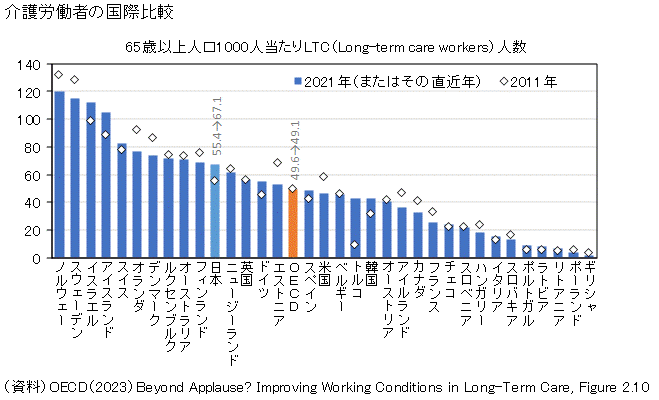
就業者全体の中でケア職が大きく増加してきている点については図録3500参照。 65歳以上の高齢者人口1000人あたりで介護労働者の人数を比較すると、ノルウェーやスウェーデン120人近くと最も多く、OECD34カ国の平均の49人の2倍以上となっている。他方、ポルトガルからギリシャでは10人以下と非常に少なくなっている。各国の介護労働者の人数はかなりばらつきが大きいといえる。 日本は67人とOECDの平均の1.36倍と北欧と比較すると少ないが比較的多い方である。 主要先進国(G7)の順番は、日本>英国>ドイツ>米国>カナダ>フランス>イタリアとなっており、日本は首位である。 少し前まで日本の介護人材は非常に少ないとされていたのと比較すると隔世の感がある。 それでも、日本の場合75歳以上の要介護対象者の多い年齢層が増えていることもあって、なお、介護人材不足が叫ばれていると言えよう。 図で対象としているのはOECD34カ国、具体的には、介護労働者の多い順にノルウェー、スウェーデン、イスラエル、アイスランド、スイス、オランダ、デンマーク、ルクセンブルク、オーストラリア、フィンランド、日本、ニュージーランド、英国、ドイツ、エストニア、スペイン、米国、ベルギー、トルコ、韓国、オーストリア、アイルランド、カナダ、フランス、チェコ、スロベニア、ハンガリー、イタリア、スロバキア、ポルトガル、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ギリシャである。 (2015年11月30日収録、2023年10月10日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||