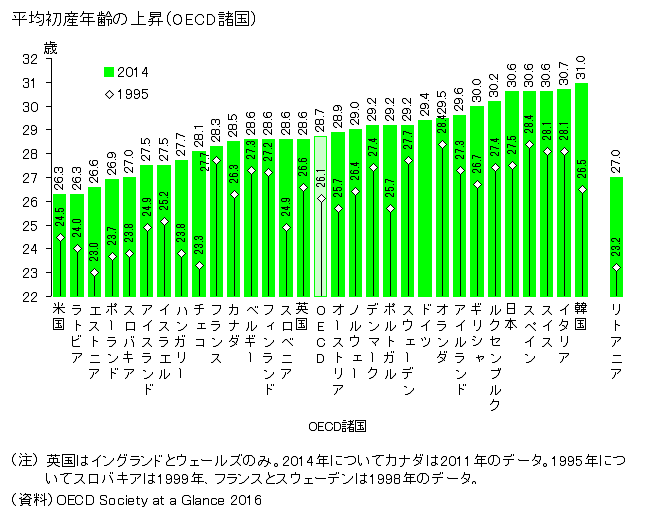
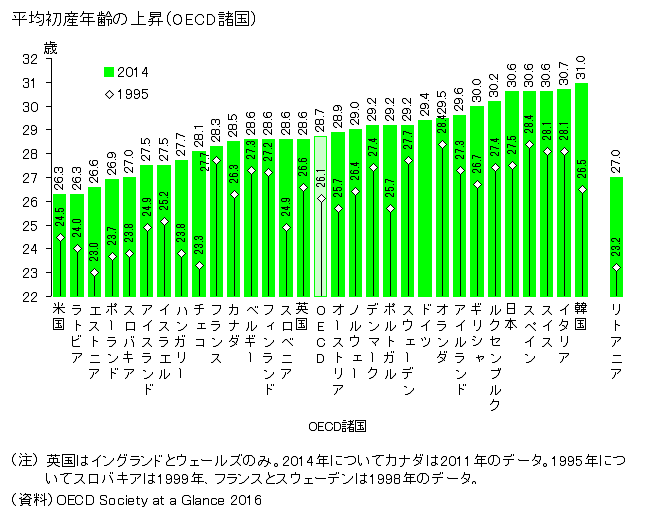
OECDのまとめによれば、1995年から2014年にかけてのほぼ20年間で、OECD諸国の平均初産年齢は26.1歳から28.7歳へと3歳近く上昇している。 各国の現在の初産年齢を見ると米国が26.3歳で最も低く、韓国が31.0歳で最も高くなっている。 日本は30.6歳と上から5位の高さとなっている。 米国のほかに、ラトビア、エストニア、ポーランド、スロバキアなどの東欧諸国で初産年齢は低くなっている。 平均初産年齢が高い点で目立っている地域は、アジア地域(日本、韓国)、大陸ヨーロッパ(ルクセンブルク、スイス)、南欧(イタリア、スペイン、ギリシャ)である。 多くの国でこの20年間に大きく初産年齢が上昇しているが、フランス、ベルギー、オランダやスウェーデン、フィンランドといった国では、すでに20年前にはかなり初産年齢が高くなっており、その後の変化幅はそんなに大きくなかったといえる。 日本は7位から5位に順位が上がっているので、上昇幅が大きかった部類に入るであろう。 平均初産年齢の上昇は、通常は、少子化の原因と見なされているが、よくよく考えてみると、むしろ、少子化の結果という側面もあるのではなかろうか。すなわち、以前、子どもを多く産んでいた時代には、早く生み始めるしかなかったのに対して、現在は、教育費がかかるなどのために子どもの数を減らすしかないとしたら、それは、早く生み終わるか、遅く生み始めるかの選択がありうる状況に変化したことを意味する。そして、後者を選択する女性が半分だとしても、平均初産年齢は上昇する。 女性の高学歴化や平均初婚年齢の上昇が進めば、なおさら、遅く生み始めるケースがより多くなるといえよう。 さらに、女性の高学歴化や平均初婚年齢の上昇じたいも少子化の原因と考えるのではなく、平均初産年齢と同様に、少子化の結果と考えることも可能である。 (2018年9月5日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||