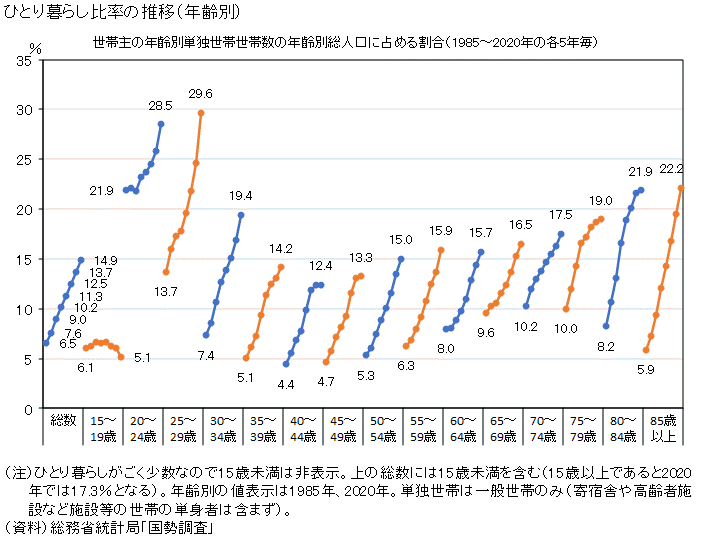
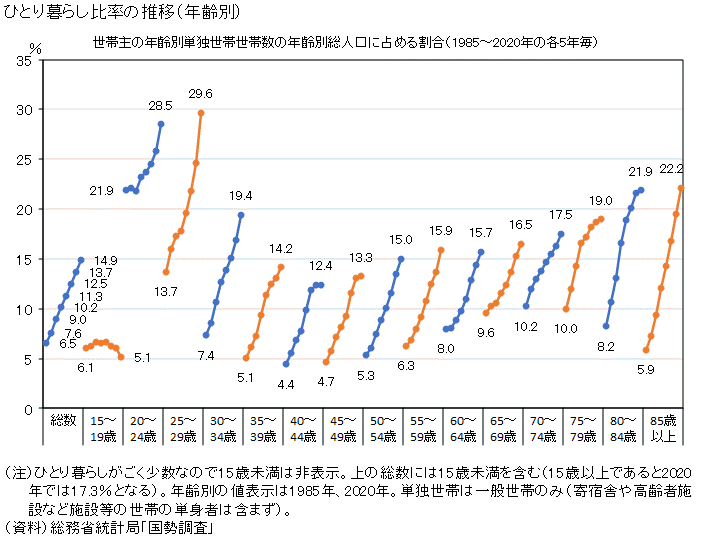
しかし、こうした世帯数構成比からは、各年齢層のひとり暮らし比率が実は分からない。これを知るためには、世帯主の年齢別の世帯員数別世帯数のうちの単独世帯(一人世帯)から年齢別のひとり暮らし人口を求め、これを別集計の年齢別人口で除して求めることができる。ひとつの集計で求められず、官庁統計の概要版でも公表されないので、マスコミも報じない状況となっている。 そこで、ここでは、この指標を1985年以降の国勢調査時系列結果から算出しグラフにして示した。 年齢を加えるとひとり暮らし比率はどう変化するかを2020年値で追ってみると、10代では5%程度と低いが、20代には3割近くに上昇し、結婚が進む30代では10%台に低下し、40代前半で最低の12.4%となる。最近は生涯未婚率が上昇しているので最低でも10%以上となっている。 40代後半からは、離婚、別居や単身赴任などで徐々に上昇をはじめ、子どもの独立も加えて、60代後半には16%を超える。65歳以上の高齢期には、死別や子どもの独立でさらに上昇を続け、85歳以上では22.2%にまで達する。 次に、1985年から2020年にかけての35年間の推移を見てみよう。 全体として、各年代、各年齢層でひとり暮らし比率が大きく上昇した。 1985年から2020年にかけ、年齢計で6.5%から14.9%、もっとも高い水準の20代後半では13.7%から29.6%へと2.2倍に上昇。85歳以上では5.9%から22.2%へと3.8倍とさらに大きく上昇している。 唯一の例外は10代後半であり、しばらく上昇したが2005年の6.6%から5.1%へとむしろ低下している。これは高学歴化にともなう就職年齢上昇により、親元を離れるのが遅くなってきているためである。 20代前半はバブル期ぐらいまでは横ばいであり、まだ働き始めてもまだ親と同居していたが、その後、上昇しているのは、高卒就職でも、大学生でも独立するようになったためと思われる。 20代後半の急速な上昇は、20代前半と同じ独立志向に加えて、結婚して2人世帯に移るのが遅れて行ったからであろう。 結婚するとひとり暮らしは減るのであるが、晩婚化の影響で、一方では、30代前半までのひとり暮らしの上昇加速、他方では、30代後半と40代のひとり暮らし上昇の鈍化にむすびついている。 20代における2015〜20年の伸びの大きさにはコロナの影響の可能性もあろう。もっとも国民生活基礎調査によると1人世帯が急増したのは2022年なので、コロナの影響は2020年段階ではそれほどでないとも考えられる(図録1188参照)。 死別が一般化する高齢期より以前の中年層のひとり暮らし比率上昇は、未婚、単身赴任、離婚の増大の影響によると思われる。 高齢層のひとり暮らし上昇とそのテンポには、本人の健康度の上昇や三世代世帯の減少のほか、配偶者との死別、子どもの独立、子どもからの独立のタイミング、在宅福祉・介護制度の充実などの要因が複合的に働いていると考えられる。 例えば、死亡年齢の上昇(図録1557参照)は高齢二人世帯を増加させ、70代後半〜80代前半のひとり暮らし比率の伸びを鈍化させるとともに、女性の死亡年齢の上昇は死別後の女性を増やし、85歳以上のひとり暮らし比率の上昇の大きさの大きな要因となっていよう。 (2023年10月2日収録、2024年1月4日総数の2010〜20年値世帯主年齢不詳を含まない値に補正など)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||