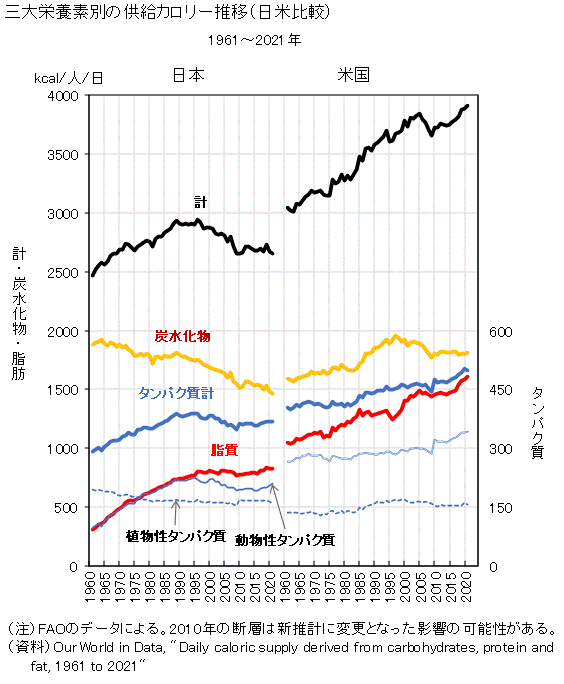
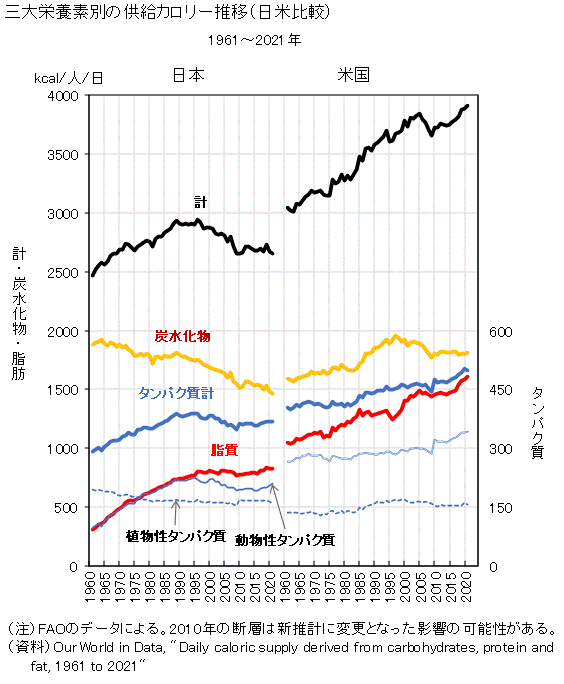
そこで、日本の特異性の理由を探るためにも供給カロリーの日米比較を行った。 タンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)を三大栄養素と呼ぶが、ここでは、日本と米国の供給カロリーの推移を三大栄養素ごとに示した。タンパク質については、植物性タンパク質と動物性タンパク質に区分した推移も同時に示した。 米国の動きは三大栄養素すべての傾向的増加と言う意味で比較的単純である。その中で目立っているのは、脂質の伸び率が炭水化物やタンパク質と比較して高い点である。その結果、脂質の割合は1960年から2020年にかけての60年間に35%から40%超へと拡大した(下図参照)。 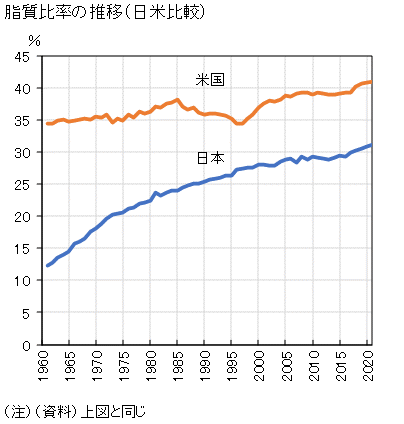 この60年間の中で、ほぼ1985〜95年の時期には炭水化物や植物性タンパク質がかなり増えて脂質の増加が抑えられていた。しかし、その後は、従来からの延長線の傾向に戻ってしまった。 日本の場合は、1990〜2000年のバブル崩壊後10年間の時期をピークに供給カロリー総量が増加から減少に転じたのが目立っている。同じ時期に、増加傾向をたどっていた動物性タンパク質、脂質が、それぞれ、減少、横ばいに転じた。いわゆる「草食化」傾向が目立つようになった。 こうした栄養摂取の内容変化と平行して、日本人の若い男性の草食化が進行したので、栄養変化がやはりその原因ではないかと言う仮説を私の前著「なぜ、男子は突然、草食化したのか」(日本経済新聞出版、2019年)で提示した。 三大栄養素のうちの炭水化物は減少し続けているので、脂質が横ばいに転じたにもかかわれず、上図で見るように脂質割合は増勢を維持している(勢いは弱まったが)。 それでも日本の脂質割合は30%を若干上回る程度で米国の1960年当時よりも低い水準である。 バブル崩壊後の時期に、増加傾向をたどっていた動物性タンパク質が減少に嘆じたのは、魚介類の摂取が減少傾向をたどる中で、増勢を続いていた肉類の消費が増加から横ばいに転じたためである。 こうした供給カロリーの大変化をバブル崩壊後の10年間に引き起こした要因としては、南方民族DNA説と質量代替的食文化説という2つの仮説を考えている。 前者は、日本人の身長が戦後長らく継続していた伸びから横ばい、ないし低下に転じた。しかも、韓国や中国が伸び続いているのと対照的である点に着目した仮説であり、ベルクマンの法則どおりの小さめの体格を維持するにはこれ以上栄養は不要だからとする考え方である。 後者は、日本人は、肉食禁止の長い歴史を通じ、肉や脂肪に頼らないで味的に満足可能な食の体系を長い期間にわたって営々と築き上げてきたため、バブル崩壊後の経済低迷をきっかけに、そんなにカロリーを摂取しなくとも毎日を送ることが出来るようになったという説である。 後者の質量代替的食文化説の方が有力ではないかといまのところ私は考えている。日本の特異な供給カロリーの大変化の説明を科学的に行うことが出来れば、肥満に悩む世界中の人たちへの福音となるのだから、マスコミや有識者は、この変化にもっと着目し、活発な研究や議論を行うべきだと思うのだが。 (2024年12月15日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||