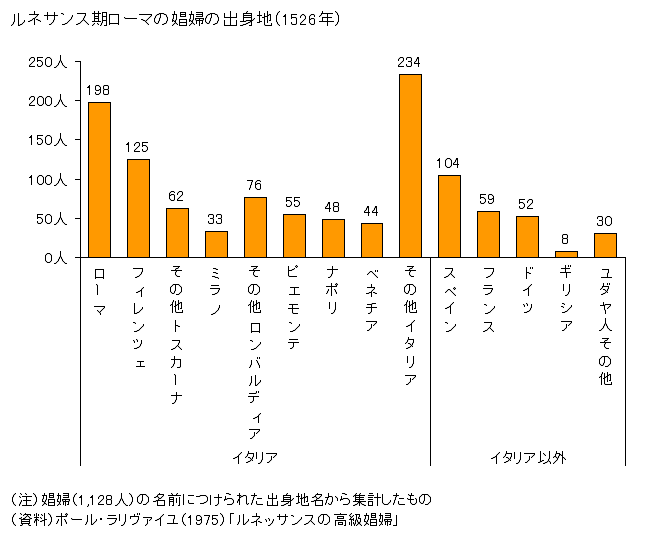
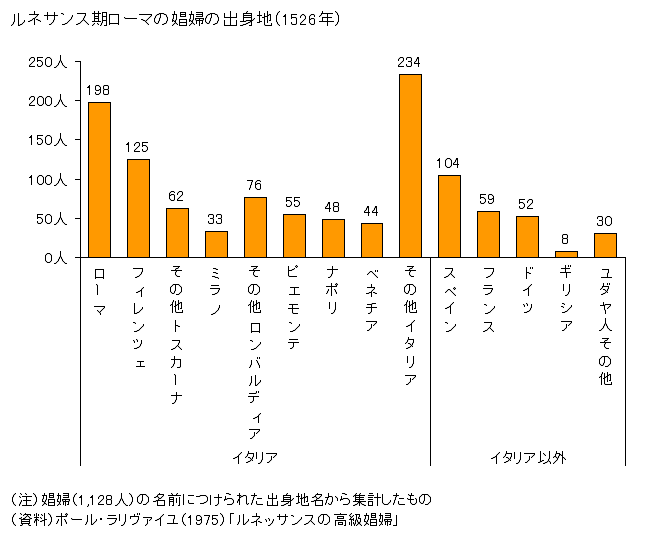
ポール・ラリヴァイユ(1975)によれば、ルネサンス期イタリアの娼婦は、詩的な名前、大袈裟な名前、古代ローマや古代ギリシャの有名な名前を自分に付けていたという。プリマヴェーラ(春)、インペリア(帝国の女性形)、コルネリア(第二次ポエニ戦争での英雄スキピオ・アフリカヌスの娘にしてグラックス兄弟の母の名)等々である。また他と区別するため出身地名を添えていることも多かった。アンジェラ・グレカ(ギリシャ)、クラウディア・フランチェスカ(フランス)、レオナルダ・ポルトゲーザ(ポルトガル)、パオリーナ・ロマーナ(ローマ)、カテリーナ・ベネチアーナ(ベネチア)といった具合である。ここから出身地を集計したのが上図である。 ポール・ラリヴァイユ(1975)は、また、娼婦の2大中心地だったローマとベネチアの娼婦の人数について以下のようなデータを掲げている。
なお、バーン&ボニー・ブーロー(1987)によれば、両都市に匹敵するか上回る人口の15世紀パリ(フランス)の娼婦数は5〜6千人という記録がある(西欧主要都市の1500〜1800年の人口は図録9015参照)。 ラリヴァイユ(1975)によれば、ローマの娼婦数が3万人(1520年頃、フランシスコ・デリカド)、4万人(1588年頃、オランダ人ビュヘル)といった数字はローマ市の人口から考えてあり得ないが、「少なくともトレント公会議(1545年)と反宗教改革の勝利に先立つ時代のローマ市では、人口の10%が売春業で生計を立てていたというニョーリの算定は、事実からあまり隔たっていなかったといえるだろう。この比率は女性の人口のほぼ20%に相当する(中略)ともかく1つのことは確かである。つまりルネサンス時代において、キリスト教の首都は売春の首都でもあったということである。やはりインフェッスーラの証言によるのだが、1490年の娼婦の戸籍調査が僧侶や教皇庁付きの聖職者の放埒な生活が原因で行われたということや、彼らのなかで内縁の妻や娼婦を囲っていなかった者はまれであったという事実を考えれば、この2つのことは互いに無関係ではなかったのである。」 ローマについては、聖職者や教皇庁とむすびついた要職を得る(買う)ため独身を保っていた貴族の子弟たち、さらに巡礼者や使節らが多かったため、男性人口比率が60%前後と高かった点を考慮に入れる必要がある(日本近世の江戸の男性比率と同レベル−図録7850)。 ベネチアについては、人口はローマよりベネチアの方が多かったので、娼婦人数は1万人より多いが「16世紀初めの娼婦の比率−人口の10パーセント−は、二つの都市でほぼ同じであったにちがいない。」外国から帰国したあるベネチア人が自作のソネットで、町中どこを歩いても娼婦から合図を送られないところはなく、「ベネチアは売春窟(ボルデッロ)になってしまったらしい」と退廃都市を嘆いているのも当然だということになる。 なお、江戸時代初期(1609年)に今の房総半島に流れ着いたフィリピンの臨時総督ドン・ロドリゴがのちに本国スペインの国王に提出した「日本見聞録」によると京都の人口は30〜40万人であるのに対して「娼婦は司法官に依り指定せられたる特別区に置かれたる者五万に達すと(京都所司代の板倉は)述べたり」とある。ここでの「特別区」は1602年に「二条柳町」から移された幕府公認の遊女町で遊女歌舞伎の根城ともなっていた「六条三筋町」(のちの1640年にさらに移転し島原遊郭として発展)と考えられる。しかし、いくら何でも京都に人口の10%以上も遊女がいたとは信じがたいが、洋の東西を問わず、16〜17世紀にそうした状況の報告があることだけは確かである。 近代に入っての同類の数字の例としては以下があげられる。「サンフランシスコで発刊されていた邦字新聞『新世界』(1907.7.3)に、「名古屋におけるユー・マッヒー氏の日本警察の統計に就きて調べた所によれば、40人に1人淫売婦という算当である」という記事がある」(宮島新一「芸者と遊郭」青史出版、2019年、p.190)。 【参考文献】
(2012年5月21日収録、10月5日京都の遊女数追加、2021年5月2日宮島引用)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||