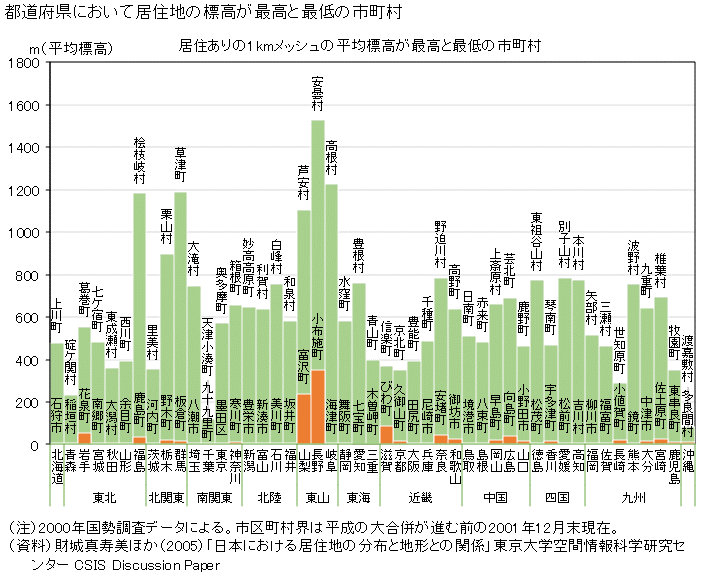
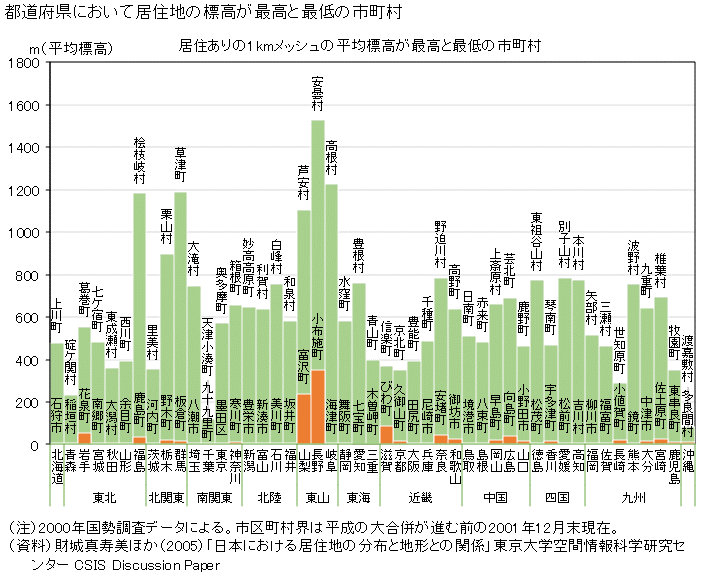
平成の大合併後は小さな山間の町村が麓の市と合併したケースも多く、そうした疑問の意味が薄れてしまった。ここでは、2000年国勢調査時の市町村別居住地平均標高のデータを用いているので、そうした疑問の意味がまだ有効だった時点のデータである。 都道府県単位の平均高度と平均居住高度は図録7231b参照。 市町村の中で最も居住地の平均標高が高かったのは、長野県の安曇村の1,527.7メートルだった。 安曇村は村内の白骨温泉で入浴剤による着色が2004年に発覚し、村長が辞任する事態を招いたことでも知られる北アルプス南部の観光地であったが、2005年4月1日に安曇村を含む松本市周辺4町村が松本市に合併し、現在は松本市の一部となっている。 居住地平均標高の高い市町村トップ5は以下である。 1.安曇村(長野県、現松本市)1,527.7m 2.高根村(岐阜県、現高山市)1,224.7m 3.草津町(群馬県)1,188.9m 4.桧枝岐村(福島県)1,181.8m 5.芦安村(山梨県、現南アルプス市)1,103m このうち3村は合併で消えている。現在では草津温泉があることで有名な草津町が最も高い市町村となっていると思われる。 逆に居住地平均標高の低い市町村トップ5は以下である。 1.七宝町(愛知県、現あま市)0m 1.木曽岬町(三重県)0m 3.大潟村(秋田県)0.1m 4.墨田区(東京都)0.4m 5.福富町(佐賀県、現白石町)0.8m このうち2町は合併で消えている。現在では三重県の北東端、木曽三川の河口部に位置する木曽岬町が最も低い市町村となっていると思われる。 なお、県内最高の市町村の居住地平均標高が最も低いのは沖縄県の渡嘉敷村の82mである。2番目は千葉県の天津小湊町の121.5mだったが、同町は今では合併し鴨川市の一部となっている。 また、県内最低の市町村の居住地平均標高が最も高いのは長野県の小布施町の351.7mである。2番目は山梨県の富沢町の236.9mだったが、同町は今では合併して南部町の一部となっている。 (2025年4月23日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||