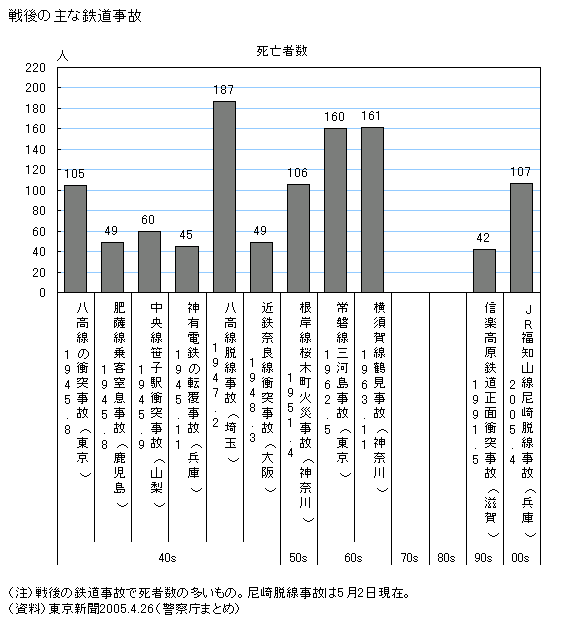
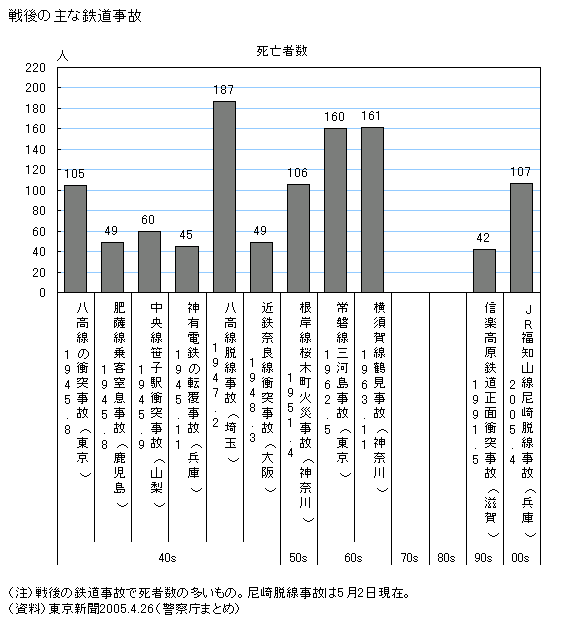
|
死亡者数の多い順の主要な鉄道事故
(資料)東京新聞2005.4.26(警察庁まとめ) 尼崎で発生したJR福知山線列車脱線事故は死者107名と非常に深刻な鉄道事故となった。
戦後の大きな鉄道事故を死亡者数の多い順に並べると表の通りである。尼崎脱線事故は戦後4番目にランクされる。 図は年代別にこれらの鉄道事故を並べたが、これを見ると、1940年代、終戦後の混乱期には、大きな鉄道事故が多発したが、50年代、60年代と深刻な事故の数は減少し、70年代〜90年代の30年間は信楽高原鉄道事故を除けば大きな事故は起こっていなかった。そういう意味からも今回の尼崎の事故はどういう環境の変化が事故の背後にあるか、深刻に受け止める必要があろう。 死亡者数最多の八高線脱線事故については、川本三郎「荷風の昭和 後篇―偏奇館焼亡から最期の日まで―」(新潮選書、2025年)に次のように記されている。 「買出電車」といえば、鉄道好きには昭和22年2月25日、八高線(実質的に八王子―高崎)の東飯能―高麗川間で起きた脱線転覆事故が知られる。蒸気機関車が6両の木造客車を引いて走っていたとき、脱線し、高さ約5メートルの築堤の下に転落。死者184人を出す大惨事になった。事故の一因は、当日、車内は定員の三倍以上の混雑で、車両のコントロールがきかなくなったことにある。混雑したのは、沿線の農家へ買出しに行く乗客が多かったため。買出しが日常化していた時代の悲劇である。 (2005年4月26日収録、5月2日改訂、2025年8月24日八高線脱線事記事)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||