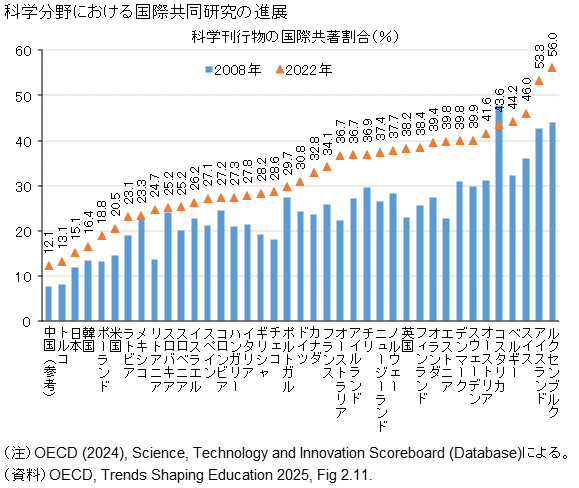
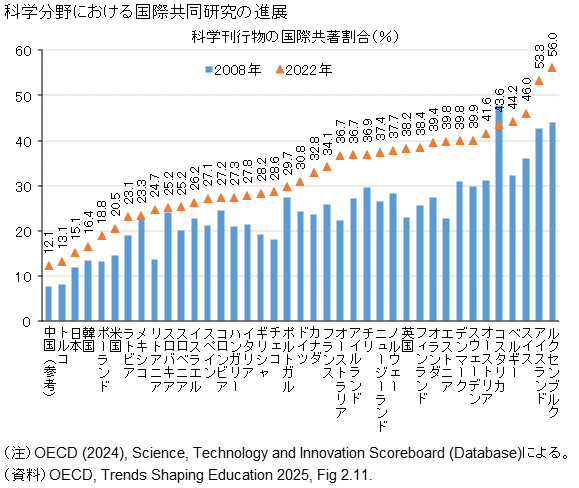
科学の国際的な共同研究がどれだけ進んでいるかを科学刊行物(論文、著作)における国籍の異なる研究者の共著割合から知ることができる。OECD各国におけるその指標の値をグラフにした。 2022年の値が最も高いのは、ルクセンブルクの56.0%であり、アイスランド、スイス、ベルギーが、それぞれ、53.3%、46.0%、44.2%で続いている。こうした国では、科学論文の何と4〜6割が複数の国の著者によるものとなっているのである。 この値の高い順の国の並びを見てみると、比較的小国のヨーロッパ先進国が最も高く、ヨーロッパ主要国がこれに続き、東欧や南米の途上国的な諸国や日本、韓国、中国で値が低くなっている。 米国は下から5位の20.5%であり、案外、国際共同研究が比率的に多くない。大国の米国では人材が豊富であり、外国人を入れずとも科学研究が成り立つケースが多いのではなかろうか。 主要先進国(G7諸国)のランキングは以下であり、けっこう差が大きい。 1.英国 38.2% 2.フランス 34.1% 3.カナダ 32.8% 4.ドイツ 30.8% 5.イタリア 27.8% 6.米国 20.5% 7.日本 15.1% 日本が韓国と共に国際共同研究が少ないのは、米国とは異なり、国際的にオープンな科学研究の環境が未熟だからであろう。中国で国際共同研究が少ないのは、日韓と共通の閉鎖性もあろうが、むしろ米国と似た事情もありそうだ。 同じ島国でも、英国は島国なので広く人材を海外にも求めざるを得ないのに対して、日本は島国なので国際交流に対して閉鎖的であるという違いがある。 図では2008年値を棒グラフ、2022年値を点グラフであらわし、その間の変化を追っている。ほとんどの国でこの間に国際共同論文の割合は上昇しており、科学研究における国際協力は世界的に進展していることが確認できる。 特に、現在、値の高い国ほど上昇幅も大きくなっており、逆に言えば、国と国との差は大きくなっていると言えよう。 上昇幅が最大なのはエストニアの16.9%ポイントであり、英国の15.3%ポイント、オーストラリアの14.3%がこれに次いでいる。 以下には、主要国における毎年の値を折れ線グラフで示した。全般的に上昇傾向にある中で、英国の伸びが著しいのが目立っている。 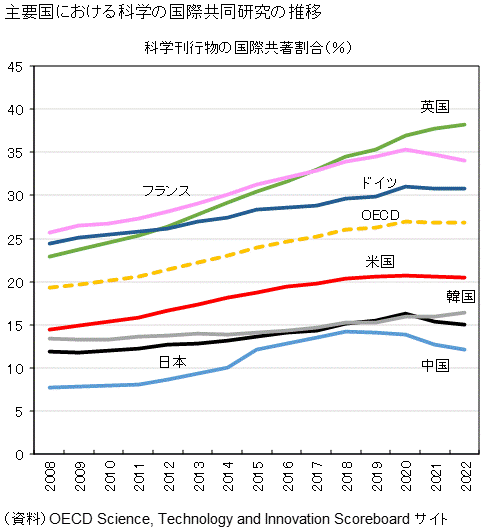 一方、日本、韓国、中国といった東アジア諸国では国際協力の進展度が低い。 2020年以降、フランス、日本、中国など科学研究の共同論文率は低下している国が目立っているが、これは新型コロナの影響による国際交流環境の変化によるものであろう。 (2025年5月26日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||