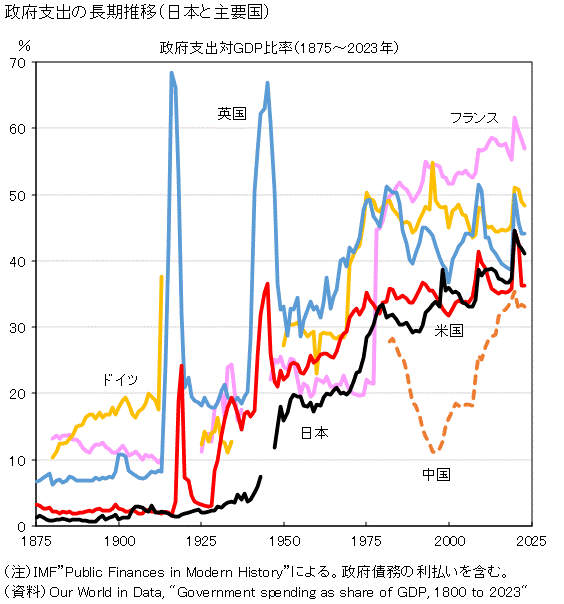
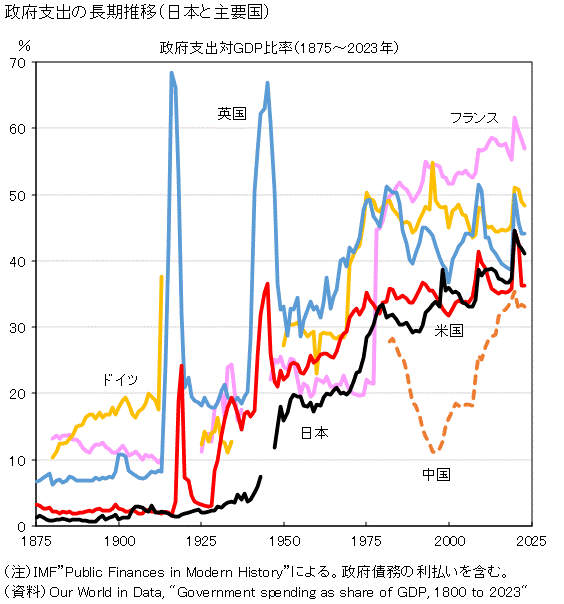
| �@ | �@ | ||||||||||||||||||
�@���̓_�ɂ���IMF�����Ɋ�Â�Our World in Data�T�C�g���e���̎��n��f�[�^���f�ڂ��Ă���i�Y���y�[�W�j�B�����ł́A���{�̃f�[�^���k���1875�N�i����8�N�j�ȍ~�̎�v���̒l���O���t�������B �@GDP���v�iSNA�j�ɂ����鐭�{�x�o�́A�傫���u���{�ŏI����x�o�v�Ɓu���I�Œ莑�{�`���v��2�ɕ�������B���{�ŏI����x�o�́A���{�̈�ʓI�Ȋ�����Љ�ۏ�Ȃǂɔ�₳�����̂ŁA���I�Œ莑�{�`���͓��H��w�Z�̐����Ȃnj������Ƃɔ�₳�����̂ł���B?�����Ő��{�Ƃ́A�������{�A�n�����{�A�Љ�ۏ����i���I�N���A��Õی��Ȃǂ̑g�D�j����Ȃ��Ă���B �@���E�I�ɂ͗��j�I�ɐ��{�x�o�̊g��X�����F�߂���B�o�ςɉʂ������Ƃ̖����͊�{�I�ɑ傫���Ȃ��Ă��Ă���B���{�̈ꕔ�ƌ��Ȃ������I������Ǘ�������I�N�����Õی��Ȃǂ̎Љ�ۏ�x�o���g�債�Ă����e�����傫���낤�B �@���j�I�Ɍ��Đ��{�x�o���ꎞ�I�ɑ傫���g�債���_���ڗ����Ă���̂͌R����ł���B��1�����E���Ƒ�2�����E���̎����̉p���A�č��̐��ڂ��[�I�ɂ������Ă���B�h�C�c�A�t�����X�A���{�̒l�̊g�債�Ă���͂��ł��邪2013�N�̃h�C�c�������ăf�[�^�������Ȃ��B��1�����ւ̎Q�킪�x�ꂽ�č��̐��{�x�o���g�債���͎̂��1918�`9�N�ł���B �@�č��͑勰�Q���1930�N��ɂ����{�x�o���g�債�Ă��邪�A����̓��[�Y�x���g�哝�̂��i�߂��j���[�f�B�[������ɂ����̂ł���B�č��͂��̌�A���������e�����Ď��{�����e���Ƃ̐킢��2009�`10�N�ɁA�܂��V�^�R���i���2000�`01�N�ɂ����{�x�o���}�g�債�Ă���B�V�^�R���i�ɂ��Ă̓��[���b�p�e������{�ł����l�̐��{�x�o�̈ꎞ�I�g�傪�F�߂���B �@���{�ɂ��ẮA���ɂ����āA���ꂼ��A�I�C���V���b�N��A�o�u�������A���[�}���V���b�N��A�����ăR���i�̎����Ɍi�C��ȂǂƂ��đ傫�ȍ����o�����s��ꂽ���A���̓s�x�A�h��߂��������������̂ŁA���E�I�ȌX���Ɠ��������{�x�o�̊g��X���͂�����̂́A�Ȃ��A��i���̒��ł͕č����݂́u�����Ȑ��{�v���Ƃ����n�ʂ��ێ����Ă���B �@�����Ƃ��A��O����1990�N��܂ł͐�i���̒��ōŒ�x�����ێ����A���Ɂu�����Ȑ��{�v�ł���_�������������̂Ɣ�r����Ɛ�i�����݂ɋ߂Â����Ƃ͌����悤�B���{�ł͑��̐�i�������鍂����i�W���A�Љ�ۏ�ɌW�鐭�{�x�o���g�債�Ă���̂ŁA�������������͓��R�ƌ�����B �@�Q�l�̂��ߒ����̐��ڂ��L���Ă��邪�A�Љ��`�����ɂ�������炸��v��i���Ɣ�r���Đ��{�x�o���x���͒Ⴍ�A���v�J����i�߂����������ɂ͂ނ��됭�{�x�o�䗦�͒ቺ���Ă����B1997�N�����������������A�]�̎��オ�͂��܂�ƁA�����͖����ӎ������߂邽�߂̐��͊g����߂����u�J���ƍفv���ƁA����������u�卑��`�v��W�Ԃ��Ĝ݂�Ȃ����Ƃւƕϖe�����ƌ����邪�A���{�x�o��1996�N���{�g���ɂ��ċ}�g��̋ǖʂɓ����Ă���B �@���{���u�����Ȑ��{�v�ł��闝�R�����������̏��Ȃ��̗��R����T���������ɁA�O�c�����Y�u�s�����ق�Ȃ����Ɓ`���{���������̏��Ȃ����ւƎ��������`�v�i������w�o�ʼn�A2014�N�j������A�L��������Ă���B���Ҏ���̗v��͈ȉ��ł���i���y�[�W�������j�B �u��ʓI�ȃC���[�W�ɏ]���A���{�̊������͋���Ȍ��͂������Ă���B�������A���������C���[�W�Ƃ͗����ɁA���{�̌��������͐�i���̒��ł��ɒ[�ɏ��Ȃ��B�{���́A���̗��R��T�������̂ł���B...���j��k��A���{�͏�Ɍ������̏��Ȃ����������킯�ł͂Ȃ��B����ǂ��납�A����E���O�܂ł̓��{�́A�o�ϔ��W�̐������猩��Ό������̐������ΓI�ɑ������ł������B�����Ɣ�ׂ����{�̓����́A�o�ϐ����ɔ�����������̖c���𖢑R�ɖh�������Ƃɂ���B���{�́A����E����̍��x�������Ƃ����A�����ɔ�ׂđ��������ɍs�����v���J�n���A���������̑����Ɏ��~�߂�����������Ȃ̂ł���B�i�����j �@����E����̓��{�ł́A�I�풼�ォ�猃��������������̘J�g�����ɑΉ����邽�߁A�A�����J�̉e�����ŁA�������̘J����{���𐧖�̂ƈ��������ɁA���̋��^������l���@���ݒ肷��l���@�������x���̗p���ꂽ�B�����������x�́A�����͌������̋��^������}������d�g�݂ł��������A���x�o�ϐ����ɂ���Ė��ԕ���̒����������㏸����ƁA�t�Ɍ������̋��^�����������グ�郁�J�j�Y���Ƃ��ċ@�\����悤�ɂȂ����B���̌��ʁA�l���@�����ɂ���Ėc������l����ɑΉ����邽�߁A1960�N�ォ��������̒����}�����邽�߂̎��݂��J�n���ꂽ�̂ł���B���̌��ʁA���������͒Ⴂ�����ɗ��܂����ŁA�������ɑ����Č����T�[�r�X�̋�����S�����v�@�l�Ȃǂ̐��{�O�̑g�D���c�����邱�ƂɂȂ����B�܂�A���{�ł͐��{���������̋��^������}�������i�𐧓x�I�ɐ���Ă������䂦�ɁA���̍��X���������s�����v�̏��o�����̂ł���B�i�����j �@�C�M���X�ł́A�J�g����ʂ��Č������̋��^��}�������i���̗p���ꂽ���߁A1970�N��Ɍo�ϊ�@��������܂Ō������傪�g��𑱂����B���̉��Đ�i���ł��A�������̋��^��}�����₷�����x�������ł͍s�����v���J�n����^�C�~���O���x���Ȃ�A���������̑��������Ȃ�x�������܂ő������B �@�ȏ�̌��ʁA���{�̌��������͑��̍��X�����ɒ[�ɒႢ�����ɗ��܂�A�u�s�����ق�Ȃ����Ɓv�ƂȂ����̂ł���v�B �@�܂�A���������̊ϓ_����ł��邪�A���{���u�����ȍ��Ɓv�Ȃ̂́A��O����Ȃ̂ł͂Ȃ��A���̌��������x�̉e�����Ƃ����̂ł���B �@�Ƃ��낪�A���{�x�o��GDP�̎w�W����͂����Ō����悤�ɐ�O������{�́u�����Ȑ��{�v�ł���B���́A�V���u���v�Ŗ₢���� �͂���l���炯�̓��{�l�v�i���C�АV���A2025�N5�����j�̑�6��3�߁u���{�̌������������E�ŏ����x���ł��闝�R�́H�v�ŁA�������������Ƃ�@���I�ȗ��R�ŁA���Ƃ��Ɨ��j�I�ɓ��{�l�͍��ƂƂ͑a���Ȗ����ł���Ɣ��f�������A���}�^�̃f�[�^�͂���Ɛ����I���Ǝv����B �@���{�l�قǎ��̃J�t�J�̌����������Ǝv�������͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B �u�}������Ă���҂����ɑ��āA���������҂����́A���̐ӔC���ʂ����ƌ����Ĕz�����Ă݂��邪�A���������̔z�������A�������ێ����邽�߂̂��̂ɂق��Ȃ�Ȃ��̂��v�i�J�t�J�u�f�ЏW�v�V�����Ɂj�B �i2025�N5��2�����^�A7��25���J�t�J���p�j
�m �{�}�^�Ɗ֘A����R���e���c �n |
|
||||||||||||||||||
�@