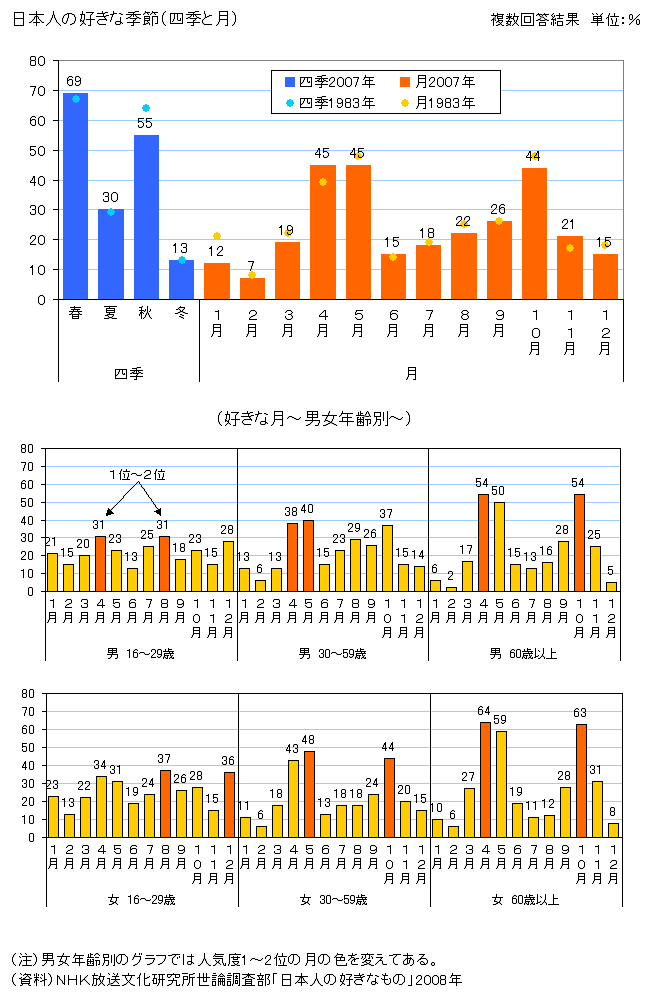
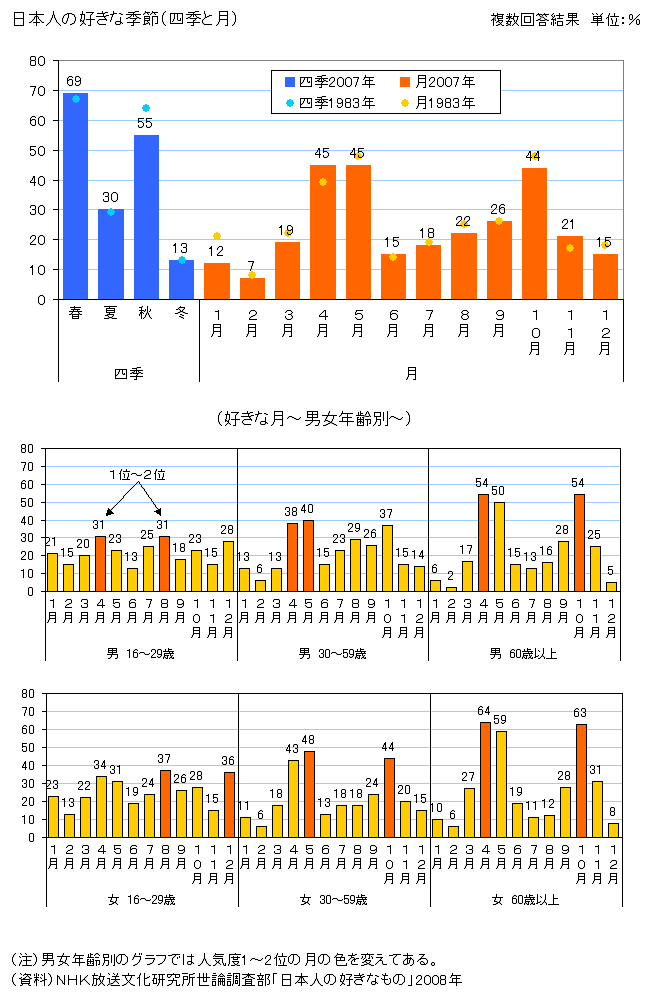
NHKの放送文化研究所では2007年に全国300地点、16歳以上の国民3,600人を対象に今の日本人が好きだと感じているものの調査を行っている(有効回答率66.5%)。この結果から、四季と月について、いずれが好きかの回答率(複数回答)をグラフにした。資料はNHK放送文化研究所世論調査部「日本人の好きなもの」(2008年)である。 四季では、春が69%と最も好きで、秋が55%でこれに次ぎ、夏は30%とかなり支持率が落ち、冬は13%で最低の支持となった。やはり、暑すぎる夏、寒すぎる冬より、気候の過ごしやすい春や秋が好まれている様子がうかがえる。寒く積雪のある冬には暖かい春を待ちこがれ、うだるような暑さの夏の日には、早く涼しい秋が来ないかなと感じるのは我々の日常的な経験である。おそらく、夏の厳しさより冬の厳しさの方を強く感じているから、春の方が秋より支持率が高いのであろう。 したがって、日本列島の中でも北国と南国では結果が異なっていると思われる。報告書(NHK「日本人の好きなもの」)では、数字は掲載されていないが、地方別の結果についてこう言っている。「地方別では、北海道・東北に住む層で「夏」の支持率が全体の傾向より高くなりましたが、前回も北日本で「夏」を好む人が多く、冬に厳しい北国で夏が変わらず好かれている様子がうかがえました。」 前回(1983年)の調査結果と比較すると大きな変化はないが、秋への支持が前回に比べやや減っている。クーラーが普及し、夏の過ごしにくさが低減したことにより秋の有り難さも感じにくくなったと考えるのは穿ちすぎだろうか。 月別では、4〜5月と10月を好むものが多いという結果である。最も人気がないのは2月である。四季に対する結果とほぼ平行的な回答となっている。前回との比較では5月と10月に対して、4月の人気が高まり、この3つの月がほぼ同等の最高人気となった点が目立っている。 次ぎに、男女年齢別の特徴を、何月が好きかの結果から見てみよう。 まず、グラフ化したことによっていやでも気づかされる点であるが、若年層より高齢者層の方が月別の好き嫌いの程度が大きい。支持率が最高の月と最低の月の比率の差は、若年層では15〜20%ポイントであるが、高年層では50〜60%に達している。個人的な経験からも若い頃は暑かろうが寒かろうがそんなに生活や気分に関係なかったのに対して、年齢を重ねてくると季節の変化が体調にダイレクトに関係してくることを感じざるを得ない。また年齢を重ねると夏の入道雲、落ち葉など季節感の変化に自分の人生を重ね合わせたりして、妙にセンチメンタルになったりするのだ。 年齢別の特徴としては、次ぎに、若年層と高年層で好きな月が異なる点を挙げねばならない。
若年層は暑い夏の8月を最も好んでいる。やはり夏は若者の季節なのだ。また寒いのに12月を男は第3位、女は第2位の支持率としている。8月と12月は、中高年、特に高年層では全く人気がないのと対照的である。夏休み休暇のある8月、クリスマスのある12月は、適齢期にある男女にとってはやはり海や山で開放感を感じたり、男女のロマンスが生じやすい季節からであろう。特に女性で8月と12月の支持率が高い点が目立っている。女性の身なりもこれら季節には肌が露わになったりするなど独特な変化を生じる。男女とも60歳を越えると、そんな気分もどこへやら、むしろ寒かったり暑かったりする点のデメリットばかりが目立つようになるため、8月と12月は人気が最低に近くなる。 中年層の男女は5月を最も好む月としているが、これは、子供と過ごす5月の連休を重視しているためだと思われる。 なお中年層の女性は、20歳代までと異なり、8月への志向は一気に衰え、4〜5月の春を除くと、秋の10月を特に好むようになる。食欲の秋、芸術の秋を好むようになるからだろうか。
(2009年2月10日収録、2025年8月5日コラム)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||