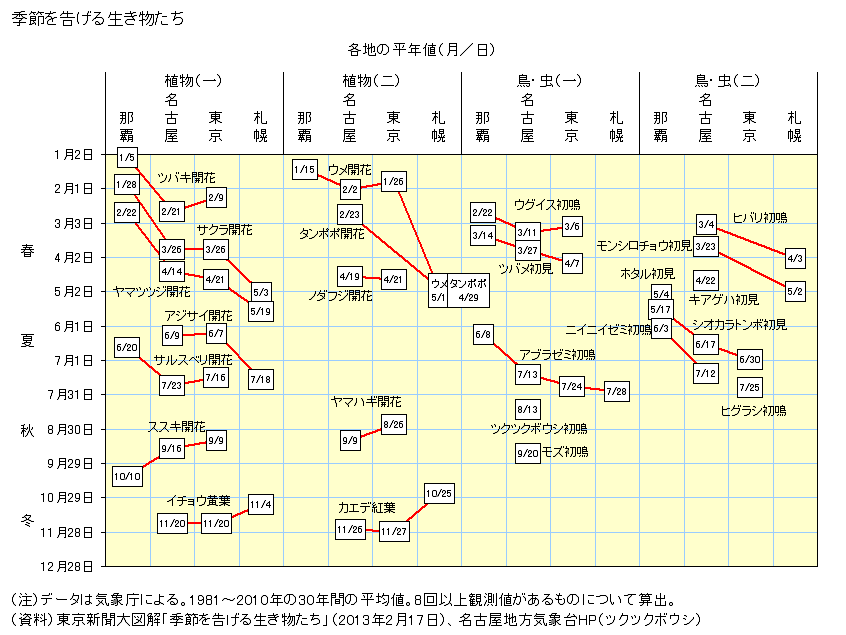
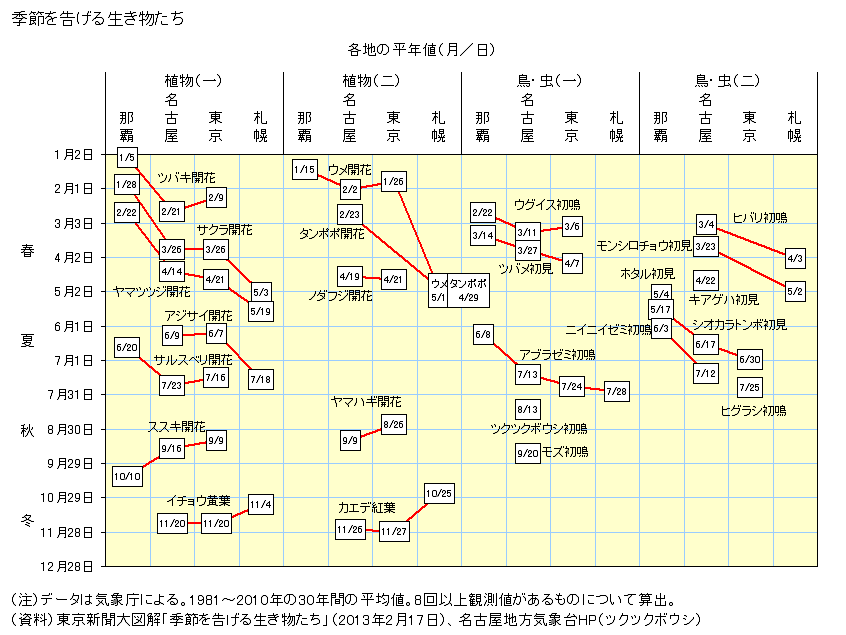
こうした季節を告げる生き物の動きを観測することを「生物季節観測」というが、気象庁では、明治時代からの取り組みを発展させ、1953年に指針を制定し、全国規模で統一基準のもとに生物季節観測を開始した。現在、59地点ある観測地点により何を観測しているかは異なるが、植物34種、動物23種、合計57種の生き物の動向が観測されている。サクラは59地点全てで観測されているが、これに次いで、ヤマツツジ、モンシロチョウ、ウグイスがそれぞれ56、53、52地点で観測されている。 ここで取り上げたのは、主な生き物に関する1981年から2010年までの那覇、名古屋、東京、札幌での観測結果の平均値である。 東京で春を告げる生き物としては、かなり早く1月26日にウ(梅)メが開花、ツバキ(椿)開花の2月9日を経て、3月6日にはウグイス(鶯)が鳴く。そして春本番を告げるサクラ(桜)の開花が3月26日に年度始めの入学式に先立って見られる。 その後、いわゆる5月病(受験戦争を切り抜けて入学した学生の虚脱感)の時期には4月21日に開花したツツジ(躑躅)が満開となる。 梅雨にはいるとアジサイ(紫陽花)が咲く(6月7日開花)。 夏を告げるのは何といってもセミ(蝉)の鳴き声。ニイニイゼミに続いてアブラゼミが鳴き始め(7月24日)、遅れてヒグラシが7月25日に鳴き始める。そして夏の終わりを告げるツクツクボウシの初鳴は8月13日(名古屋)以降である。 9月9日にはススキ(薄)の開花。秋が深まってイチョウ(銀杏)が11月20日に黄葉し、カエデ(楓)も11月27日に紅葉する。紅葉した木々の葉っぱが散ると冬である。 以上、東京での例を示したが、春や夏の訪れは、南の地が早く、北の地が遅く、また秋の訪れは、北の地が早く、南の地が遅いことは、それぞれを示す生物季節観測の地域別の結果が、右下がり、あるいは右上がりとなっていることからうかがえる。 時代の変化はこうした生物季節観測にも大きな影響を与える。 観測方法の変化としては、1964年に蚊帳、こたつ、手袋、水泳などの「生活観測」が取り止めとなる一方で、全国的に観測する種目が増加した。 1996年には気象庁の測候所の無人化・機械化をスタートさせ、生物観測地点は102地点から半減となった。継続観測地点が減ったため、きめ細かく桜前線、紅葉前線を描くことや開花予想をすることは難しくなった。 2003年には生物観測の種目が106から59に減少し、ヘビなどが卒業となった。2011年にも見直しがあり、トノサマガエルが17地点で、ホタルも12地点で観測を取り止めた。 その後も、観測はしていても姿が確認できない場合も増えている。朝日新聞の報道(2016年3月5日)によれば、トノサマガエルは「かつて、東京都と神奈川県を除く45道府県で確認された。しかし、15年春に観測を実施したのは22県で、姿が確認できたのは栃木や三重など5県のみ。25都道府県はすでに観測をやめている。(中略)東京・大手町の東京管区気象台では11年、6種の観測をやめ、ウグイス、ツバメ、シオカラトンボ、アブラゼミ、ヒグラシの5種類に絞った。ただ「春告鳥(はるつげどり)」とも呼ばれるウグイスの鳴き声は00年を最後に確認できない。地方都市でも変化が見られ、甲府地方気象台のヒグラシの初鳴は13年が最後だ」。 気象庁による観測はこのように縮小傾向にあるが、一方で、環境意識の高まりにともなって市民参加型の調査は各地で盛んとなっている。 観測結果の時系列的な変化としては温暖化による開花時期や紅葉の時期の変化が起こっている。以下に1950年代からのさくらの開花日とカエデの紅葉(黄葉)日の変化を示した。 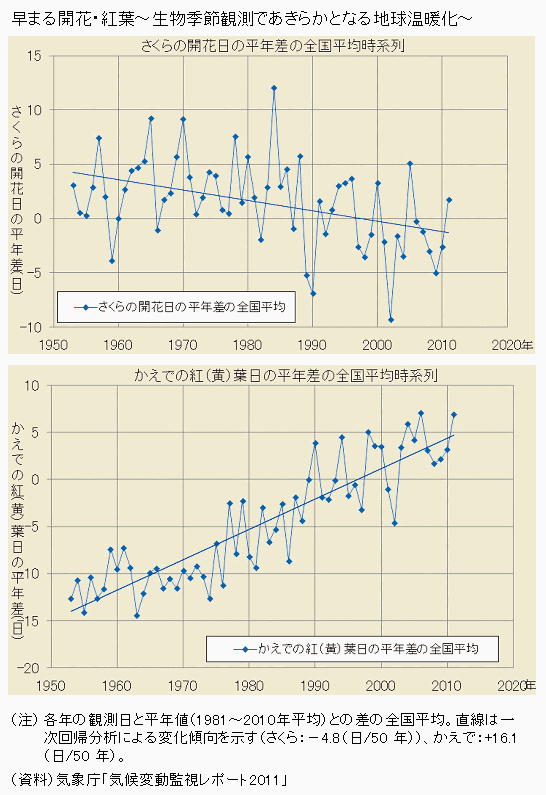 これに関して気象庁は次のように述べている。「1953年以降、さくらの開花日は早まる傾向が明瞭に現れており、変化率は50年あたり4.8 日である(信頼度水準95%で統計的に有意)。また、かえでの紅(黄)葉日は遅くなる傾向が明瞭に現れており、変化率は50年あたり16.1 日である(信頼度水準95%で統計的に有意)。さくらの開花日、かえでの紅(黄)葉日は気温との相関が高いことから、これらの経年変化は長期的な気温の上昇が影響の1 つとして考えられる。」(気象庁「気候変動監視レポート2011」)
(参考)取り上げた植物、鳥、虫
(2013年3月1日収録、2016年3月5日朝日新聞記事引用)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||