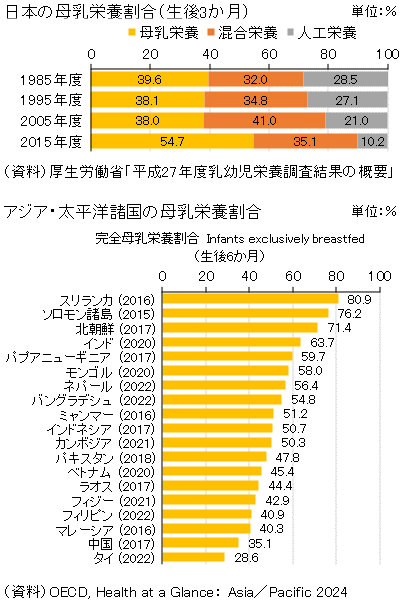
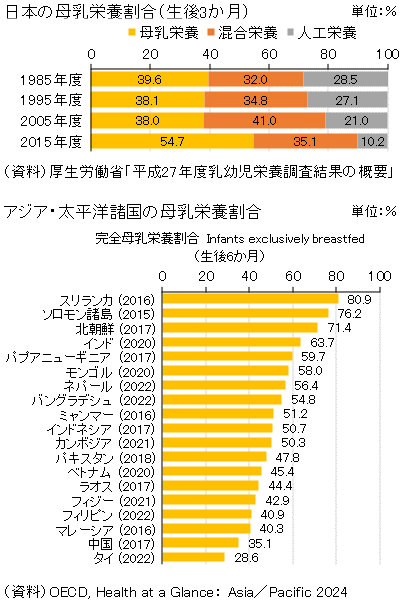
日本では戦後、病院での出産が増え、新生児は新生児室に入れられ粉ミルクを与えられた。米国での粉ミルクのブームもあり、1950年頃からは母乳栄養が衰退し、人工栄養が増加した。 図に示した通り、母乳栄養のみの育児の割合が生後3か月時点で、2005年まで減少傾向だったが、2005年の38.0%から反転増加に転じ、2015年には54.7%へと大きく増加している。 これは、スキンシップを通じた精神面の効用だけでなく、乳児期の腸内細菌叢の形成に母乳栄養が果たす役割が見直され、消化吸収、アレルギー、病気への抵抗力など母乳育児のメリットが広く知られるようになったことによっている。WHOなど国際機関が母乳を推奨していることも影響している。 母乳栄養割合は、途上国では経済の発展にともなう粉ミルクの登場により低下する傾向にあるが、近年では、母乳よりも粉ミルクのほうがよいというあやまった考えで粉ミルクを使っている母親が増えた。HIVに感染してしまっている母親が母乳をためらうケースもある。 そこで、かえって、お金がなく貧しい家庭で粉ミルクを薄めて飲ませてしまったり、粉ミルクをつくる水が汚染されていて多くの乳児が病気や栄養不良になり、命を失っている弊害が生じている状況にある。そこで、WHOやユニセフは、生後1時間以内の初乳や、6ヶ月間は母乳だけで育てることを推奨している。 アジア・太平洋諸国の母乳栄養割合のデータを見ると、割合が最も高いスリランカの80.9%から最も低いタイの28.6%まで大きな差があることが分かる。タイのほか、中国やマレーシアなど最近経済発展のめざましい新興国で母乳栄養割合が40%前後と低いという特徴がうかがえる。 各国の国内においても所得水準による格差が生じている。ユニセフの担当者は次のように言っている。「貧しい国の裕福な母親は母乳育児をしない傾向にあり、逆説的ではありますが、豊かな国では貧しい母親がしない傾向にあることがわかっています。この所得レベルによるギャップは、各国が、その富の程度に関わらず、すべての母親が母乳育児をするために必要な情報と支援を提供していないということを強く示唆しています」(ここ)。 日本も2005年までは完全母乳栄養割合が4割以下だったので、そういう意味では少し前まで新興国的な状況にあったと言えよう。 (2025年2月9日収録、10月18日コメント補訂)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||