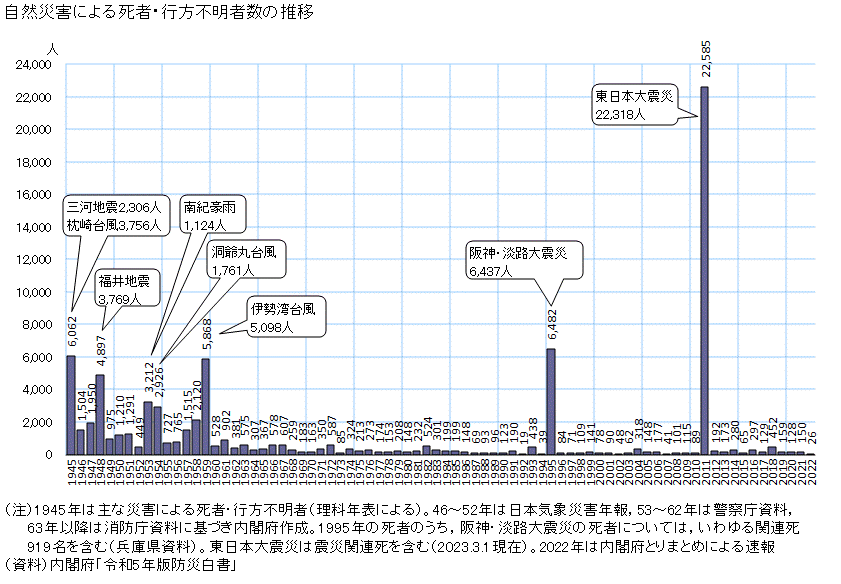
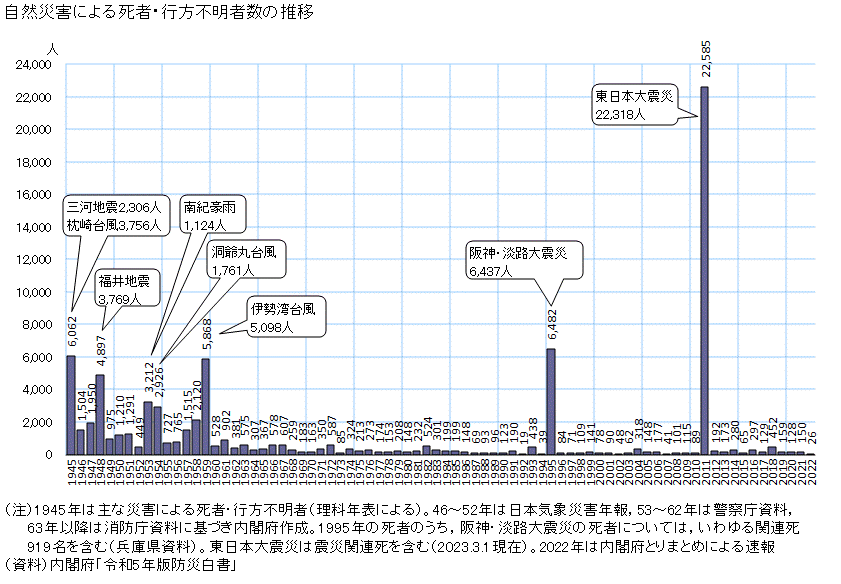
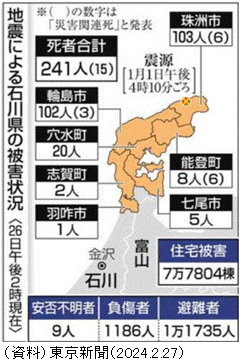 この地震の影響で震源を中心とした広い範囲の21府県約1万6千基のエレベーターが停止し、計14件の閉じ込めが発生したことを国土交通省が明らかにした(東京新聞2024.1.24夕刊、下図参照)。さらに警察の調べによると死因は圧死が92人ともっとも多かったが、救助が早ければ救えた低体温症・凍死も32人と多かった(下図参照)。 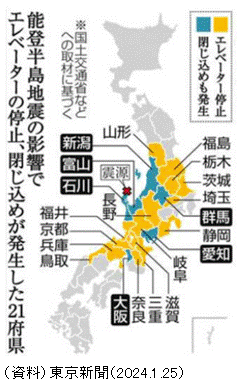 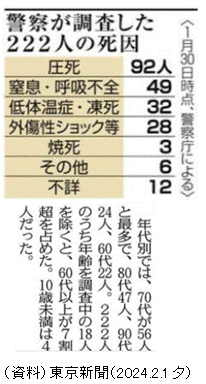 2019年10月12日に静岡県伊豆半島に上陸し各地で記録的な大雨をもたらした台風19号により、東日本の広い範囲で甚大な被害が出た。死者・行方不明者は下表の通り。決壊した堤防は74河川140か所に上るという(東京新聞2019.12.29)。台風の進路と川の流れの方向が同じだった阿武隈川では流路沿いのほぼ全域で浸水した。このため、流域の福島、宮城両県で人的被害も大きくなっている。
原則として都道府県が適用を決める災害救助法法の対象地域では、国と都道府県が市区町村に代わり避難所の運営や水、食料の提供などの費用を負担する。内閣府防災担当によると14日現在で災害救助法が適用された自治体の数は13都県315市区町村に上り、記録のある1995年の阪神大震災以降の自然災害で最多で、2011年の東日本大震災や18年の西日本豪雨を超えている(下表)。
2018年6〜8日の西日本を広域的に襲った豪雨被害(「平成30年7月豪雨」)は、次表のような大きな被害をもたらしている。末尾一覧表と照らし合わせると、豪雨災害としては、439人の死者・行方不明者を出した1982年「7,8月豪雨及び台風第10号」以来の大きな被害となっている。
2018年西日本豪雨の際に3日間に降った雨量は過去40年最多の553億m3であり、全国の年間降水総量6,500億m3(国土交通省)の1割弱に当たる量が降った勘定となる(東京新聞2018.7.17)。 2016年4月.14日、4月16日におこった熊本地震は死者・行方不明者267人を出す大きな震災となった。 2014年9月27日午前11時53分ごろ、長野県と岐阜県にまたがる御嶽山が噴火した。死者56人と戦後最悪の火山災害となった(次表参照)。
我が国では、自然災害によって、毎年、尊い人命が失われている。図には、1945年以降の毎年の自然災害による死者・行方不明者数の推移を示した。世界の主な自然災害については図録4367参照。 戦後、1940年代後半〜1950年代には、地震、台風などによって1000人以上の人命が失われる大災害が頻発した。 5,000人を越す犠牲者と未曾有の被害をもたらした伊勢湾台風の年、1959年以降は、死者・行方不明者は、著しく減少していった。これは、治山・治水・海岸整備の他、観測体制、予報技術、災害情報伝達、避難体制など防災体制が充実した結果である。 しかし、1995年に起こった阪神・淡路大震災では、6,437人と戦後それまでで最大の死者・行方不明者数をもたらし、さらに2011年には2万人近くの死者・行方不明者と、他を圧倒して戦後最大の被害となった東日本大震災が発生し、それにともなう福島第一原発の原子力事故はなお収束を見ていない。自然の力を侮ることはできないことを如実に示しているといってよい。 近年の自然災害による犠牲者は、北海道南西沖地震、阪神・淡路大震災、東日本大震災が起った1993年、1995年、2011年を除くと、大部分が、土砂災害をはじめとした台風などの風水害、そして雪害によっている。 下に我が国における明治以降の主な自然災害の状況を一覧表として掲げた。 昭和22年のカスリーン台風はキャサリン台風として知られている。この台風の被害については、川本三郎「荷風の昭和 後篇―偏奇館焼亡から最期の日まで―」(新潮選書、2025年)に次のように記されている。同書にはキャサリン台風に関し、青木正美の回想録、安岡章太郎の紀行文による記述、荷風が水害の様子を見ようと出かけた記事なども付されている。 昭和22年(1947)の9月、大型台風が関東地方を襲った。利根川と荒川が決壊し、東京と埼玉が大きな被害を受けた。死者・行方不明者は1930人といわれている。 キャサリーン台風である。占領下のこと、この時代、台風は数字ではなく、アメリカ風に女性の名前で呼ばれた。このあとのキティ台風(昭和24年)、ジェーン台風(昭和25年)も同様。このなかでもキャサリーン台風のもたらした被害はとくに大きかった。 関東大震災後に開けていった葛飾区の立石で暮す人々を描いた半村良の市井小説『葛飾物語』(中央公論社、1996年)に、この台風についてこうある。 「九月なかばにやってきたキャスリン台風は、戦時中森林伐採が激しかった酬いのように、雨量をそのまま利根川水系へ流し込み、9月16日には栗橋の右岸堤防を突き崩し、やがて金町の桜堤を決壊させ、さらに中川の堤防も決壊して、亀有、青戸、立石と荒川放水路までの一帯が水没したのだ。 低地に建つ家々は軒下すれすれが吃水線になり、水の引いたいまでも、家の柱や壁にそのときの浸水位置を示す汚れた線がくっきりと残っている」 「下水道はゼロに等しい町なのだ。水洗便所などあるはずもなく、汲取式便所だけの家々が床上浸水してしまったのだ。/路地にも横丁にも大通りにも、水のあふれた道には人々の排泄物が浮かび漂って、移動を余儀なくされた場合、人は糞尿の水に胸まで浸かって歩いたのだ」 惨状がうかがえる。 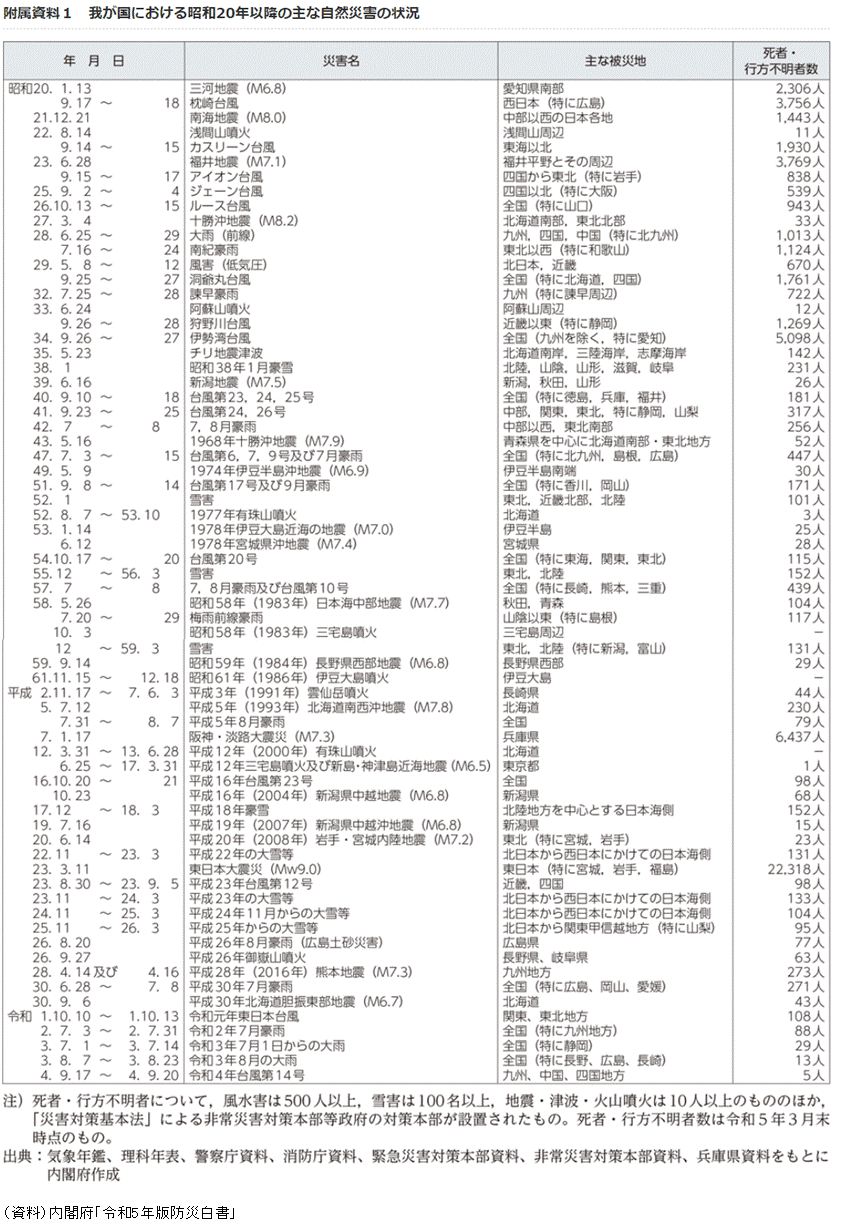 関東大震災の死者・行方不明者数の従来の定説は1925年調査に基づき、14万2000人余りとされてきたが、2003年頃、新しい実態調査により焼死者数と行方不明者数のダブルカウントが明らかとなり、上図の数字に改められた(理科年表でも2006年版から修正)(門倉貴史「本当は嘘つきな統計数字 (幻冬舎新書)
(2006年6月15日収録、2007年8月9日更新、2009年6月30日更新、2011年3月16日更新、6月23日更新、2012年7月5日更新、2014年7月8日更新、10月2日御嶽山被災コメント追加、10月8日御嶽山更新、10月17日御嶽山年内捜索中止時、2015年8月23日更新、2018年7月8日〜17日更新、17日3日間降水総量、7月21日更新、2019年7月3日更新、10月16日台風19号被害、10月17日・19日・23日・11月12日・12月29日同更新、2020年7月9日更新、2024年1月6+日更新、1月25日能登半島地震エレベーター事故、2月2日能登半島地震死因、2月3日能登半島地震被害地図、2025年8月24日キャサリーン台風に関し川本三郎引用)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||