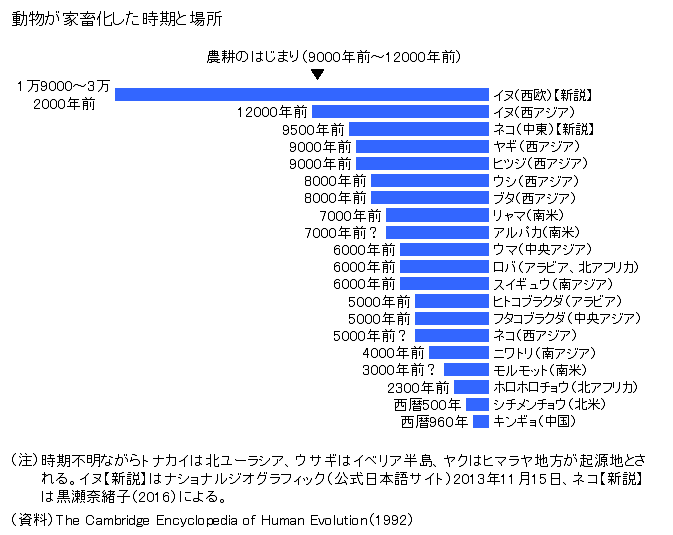
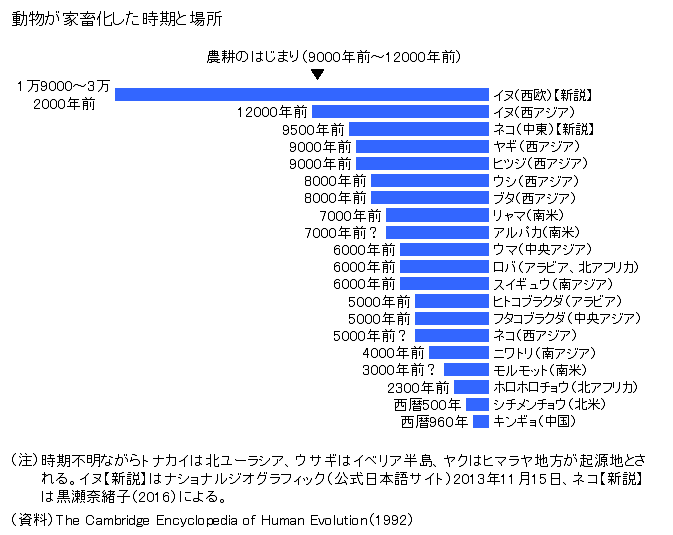
9000年前の新石器時代の西アジアの考古学遺跡から耕作された穀物と同時に他の動物を圧倒する数のヤギやヒツジの骨、それも家畜化していることを示す小型の骨が出土することから、この頃に牧畜と動物の家畜化がはじまったとされる。すなわち狩猟採集時代から定住・食糧備蓄を特徴とする初期農耕時代への転換点に動物の家畜化もはじまったとされているのである。 狩猟採集民にとっては、とにかく獲ったら食べてしまう行動パターンが基調で定住農耕民のようにイヌ以外で野生動物を家畜化する余裕がなかったようだ(松井章編「野生から家畜へ (食の文化フォーラム 33)」ドメス出版(2015年)の総合討論における秋篠宮文仁(生き物文化誌)の発言)。 同じく豚が家畜化されたとはいっても地域事情が異なれば家畜化の時期も大きく異なった。同書総合討論では以下のような発言がある(p.232)。なお、家畜化の過程については末尾コラムも参照。 池谷和信(地球環境史) 最近の西アジアの考古学の研究からすると、東南アジアから中国にかけての豚と、西アジアの豚のいわゆる起源の問題について、担い手が大きく違うということです。西アジアでは定住した狩猟採集民が農耕を始め、少し遅れて家畜を飼う。その後、農耕社会や牧畜社会は生まれるわけです。中国から東南アジアにかけての豚の家畜化の始まりはだいぶ後ですね。前者は8000年ぐらいの話に対して後者は4000年ほど遅れています。 池谷和信(2015)「人類による動物利用の諸相」(前掲書)によれば、豚の飼い方には、①舎飼い(しゃがい。米のとぎ汁や残飯などのエサをやる)、②放し飼い(家畜囲いはあるが豚が集落のなかを移動し自由に農作物残渣などのエサを得たり勝手に繁殖行動をしたりする)、③放牧・遊牧(牧夫が豚の群れを誘導し野生の植物や昆虫を食べさせる)の3パターンがあるが、舎飼い・放し飼いは中国・東南アジア・南アジアに広く分布、西アジアでヤギやヒツジの飼育法を応用して発生した豚の放牧・遊牧は、南アジア(バングラデシュ)のほか、中世のドイツ、フランスを含め各地で報告されているという(p.101~102)。弥生時代の遺跡におけるブタ/イノシシについては図録0277参照。 実際、血液型や遺伝子の研究によっても、ユーラシア大陸の東側の「イノシシとブタ」、西側の「イノシシとブタ」が、東西のイノシシ同士やブタ同士より似ていることが確認されているという。イノシシの祖先は500万年ほど前に東南アジアに出現し、100万年ほど前にアジア系と欧州系に分かれたが、ブタへの家畜化はずっと遅れ、アジアと欧州で別々に起きたためである(毎日新聞2019.1.5)。 イヌの家畜化は、ヤギやヒツジからはじまりウシ、ブタと続く肉や乳を利用する家畜化のメインストリームに先行したと考えられている。「最初に馴れたオオカミはヒトの同伴者にすぎなかったが、しばらくして残飯処理、狩猟パートナー、番犬、暖房動物の役割を果たすようになった」(The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution (1992)p.385)イヌの家畜化の証拠としては化石と言うよりは文化遺跡としてイスラエル北部の婦人がイヌとともに葬られているBC9600年の事例があげられていた。 ところがナショナルジオグラフィック誌(公式日本語サイト、2013年11月15日)などが報じたところによると、イヌの家畜化の時期はもっと前の狩猟採集時代に遡り、起源地もヨーロッパであるという新説があらわれた。研究チームは「古代のイヌ科の動物から18種のDNAサンプル(ミトコンドリアの)を収集した。主にヨーロッパのもので、うち8種はイヌに近く、10種はオオカミに近いと分類された。チームはこれらを、現代のさまざまな品種のイヌ、オオカミ、コヨーテのDNAサンプルと比較した。その結果、ヨーロッパの古代のオオカミにDNA的に最も近いのは現代のイヌであることが分かった。このことから、イヌの家畜化はヨーロッパで始まったと考えられる。チームはイヌの直接の先祖は、ヨーロッパの、現代では絶滅している系統のオオカミであると結論した。現代のオオカミよりも古代ヨーロッパのオオカミの方が、イエイヌとの関係が近いことが分かったとウェイン氏は言う。「遺伝的データは考古学的な記録とも一致している。ヨーロッパでは、最古のイヌ(の化石)が見つかっている」。この研究で使用されたイヌの化石は1万9000~3万2000年前のものとされている。」(ナショナルジオグラフィック誌)なお、この研究ではヨーロッパ単一起源説は証明されていないが、イヌの遺伝的多様性の専門家によると、科学的には単一起源が妥当とされているようだ。 一方、朝日新聞(2024.3.17)が報じたところによると、絶滅したニホンオオカミは、ゲノム(全遺伝情報)解析から、オオカミの中でイヌに最も近い種だったことがわかったという。総合研究大学院大や岐阜大などの研究チームが科学誌ネイチャーコミュニケーションズに発表した論文によると「国内に残る江戸時代や明治時代のニホンオオカミ6標本に加え、オランダとドイツの博物館に保管されていた3頭の計9頭の標本からDNAを抽出した。そのうち3頭については、ほぼ全ての配列を解読することに成功した。さらに別のチームが解読していたニホンオオカミやイヌ、ハイイロオオカミなど100頭分のデータを加えて遺伝的な近さから系統関係を割り出した。その結果、ニホンオオカミの祖先は2万~4万年前の東アジアにいたハイイロオオカミの仲間から分かれて誕生し、その後にイヌの祖先となる集団がニホンオオカミの祖先から枝分かれしたことが判明した。(中略)チームを率いた総研大の寺井洋平准教授は「ニホンオオカミがオオカミの仲間の中で最もイヌに近いという結果は予想しておらず、イヌの東アジア起源説を裏付けるような成果が得られたのは幸運だった。日本列島が大陸から離れた島国で、古い系統が残りやすい地理的な特徴のおかげだろう。絶滅したオオカミのゲノムをここまで大規模に解読した分析はほかになく、イヌの進化の歴史を塗り替える価値があると考えている」と話している」。 イヌの家畜化が他の家畜動物と異なっていた点について植物学者の中尾佐助は次のようにいっている。「栽培植物の開発と確立という作業は、人類史のなかの新石器時代という一つの発展段階だけにおこったもので、それ以前の狩猟採集時代はもちろんのこと、新石器時代以後の金属器時代、文書の歴史時代には若干の例外はあるが、これまた栽培化はおこらなかった。家畜についてもほとんど同じことがいえるが、ただイヌだけは例外で、新石器時代より古い旧石器時代、おそくとも中石器時代には確実に家畜になっていたようである。栽培植物、家畜を通じてイヌだけが人間の付属物となった年代がかけはなれて古いということは、イヌの品種のバラエティが非常に多くて幅の広いことからもうなずける。ただしイヌでは、先祖のオオカミのような野生獣が一種類だけでなかったらしいという事情も関与していたかも知れない」(中尾佐助「栽培植物の世界」中央公論自然選書、1976年)。ここでは、上記と異なり、イヌの単一起源が疑問視されている。 イヌの品種のバラエティについては主要犬種の大きさを図示した図録0456参照。 イヌに関しては番犬としても役割が現代でも生きているという研究もあるようだ(下図)(注)。 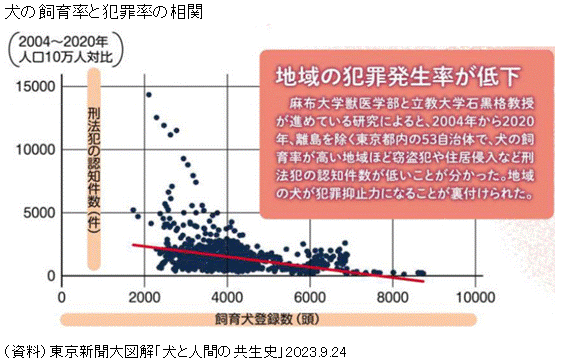 (注)ただし、この相関には疑似相関の側面があるかもしれない。すなわち、犬の飼育率は富裕層の住む地域で多く、富裕層は犯罪率の低い地域に住むので相関があるように見えるだけで、犯罪率との因果関係はないという疑いもあると感じる。 ネコの家畜化については、Cambridge Encyclopedia では「5000年前?」となっているが、現在のイエネコの祖先かどうか確認はされていないとはいえ、最古の飼育例は、キプロス島の約9,500年前の遺跡から見出されるので、約1万年前と家畜の中では早い方とされる場合が多い(ウィキペディア2015.2.6、及び下表)。 ネコの家畜化は人類が穀物栽培をはじめ、ネズミ駆除が重要な課題となったからとされる。4~3千万年前からはじまったネコ科の進化の中で狩りの上手な大型種との競争に破れ、森から乾燥地帯に移し、体形が小型化、エサもトカゲやネズミにして生き残っていたネコの祖先の食性が穀物栽培をはじめたヒトにとって好都合だった訳である。つまり最初から愛玩用ではなかったようだ(今泉忠明「猫脳がわかる!」文春新書、2019年)。 毎日新聞(2015年2月5日夕刊)は図のような家畜ネコの普及ルートを明らかにした京大チームの研究を紹介している。哺乳類では、過去に感染したウイルスがゲノムの一部に組み込まれることがあり、内在性レトロウイルスと呼ばれるが、現存イエネコにおける保有割合を調べた結果、保有割合の低い三毛猫などアジアのネコは、高い欧米のネコとは別系統の進化をとげたことがわかったのである。
 ウシやブタが最初に家畜化したのは西アジアとされるが、元動物であるオーロックスやイノシシはヨーロッパから東南アジアにかけて広く分布しており、いくつもの起源センターがあったと考えられている。 ウマの家畜化はこれらからは遅れ、ウクライナや黒海地方北部で初期の化石が見つかっている。「最初に6000年前にウマを家畜化したのはスキタイ人の祖先であり、かれらは古代世界最大の騎馬民族だった。」(The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution(1992)p.384) 南アジアからはヤクやスイギュウ、そして野鶏からニワトリが家畜化された。 ラクダの家畜化は、砂漠の思想というべき一神教の普及の契機となったということから大きな文明史的な意義をもっているとされる(鈴木秀夫「森林の思考・砂漠の思考」NHKブックス、1978年)。 「ラクダは陸上哺乳動物のなかで、もっとも高温と乾燥に抵抗力のある動物であって、この家畜化が成功したのが、今から約3200年前であった(上より遅いとされているー引用者)。この結果、人間の世界の勢力分野に大きな変動が生じた。砂漠は、これによって人間の生活空間のなかに入っただけではなく、それ以上に、遠距離の物資を直線で結ぶ、巨大な流通空間になったのである。森林は、人類の発生以来、流通を疎外する空間でありつづけた。草原が民族移動の空間であり、交易のルートであったのだが、新たに砂漠が人類にとって重要な空間となった」(p.73)。砂漠の縁辺部には海の縁辺部と同様に特定の場所が「港」として交易の拠点となる。「イスラエルは、砂漠の縁辺であり、かつ、三大陸の接する高通常の要所として、その利を得た。イスラエルは、砂漠の縁辺で半放浪の生活を送る民であったが、カナンの地に侵入して定着した前後に、ラクダの家畜化という人類史上の大事件に遭遇したために、ソロモンの栄光と呼ばれるような、繁栄を享受することができたのである」(p.74)。
(2013年12月10日収録、2014年11月27日中尾佐助引用追加、2015年2月6日ネコの家畜化コメント追加、2016年4月8日・11日「野生から家畜へ」引用、2017年1月1日黒瀬2016からの表、4月10日ラクダの家畜化について鈴木秀夫引用、2019年1月5日イノシシ・ブタ遺伝子、12月3日補訂、2023年9月25日犬の飼育率と犯罪率との相関図、2024年3月17日イヌの東アジア起源説)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||