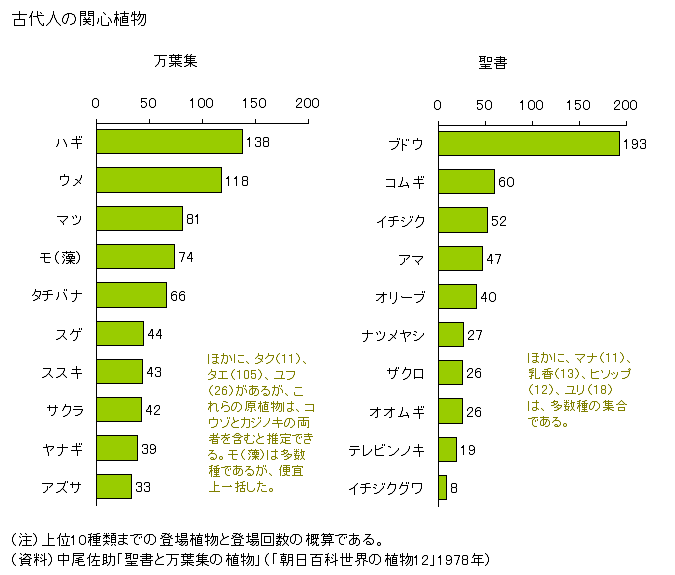
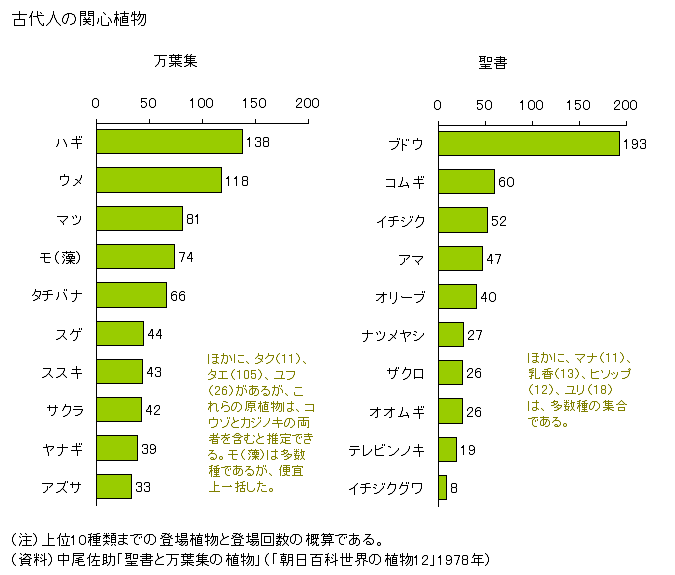
古代人が関心を持った植物種類について探ってみよう。 日本の万葉集に登場する植物種類は約166に達しており、この数は、ユダヤ民族の聖書、インドのヴェーダ、中国の詩経より多く、世界の古典の中で最も多いとされる。 万葉集に登場する植物の上位10位までは、図に掲げた通り、登場回数の多い順に、ハギ、ウメ、マツ、モ(藻)、タチバナ、スゲ、ススキ、サクラ、ヤナギ、アズサである。これらは、総て実用植物でなく、花や姿に特徴のある植物である。ウメ、タチバナ、サクラなどは果樹でもあるが、おおむね、果実としては歌われていない。 一方、聖書の上位10位までは、登場回数の多い順に、ブドウ、コムギ、イチジク、アマ、オリーブ、ナツメヤシ、ザクロ、オオムギ、テレビンノキ、イチジクグワであり、ほとんどが食用および衣料用の実用植物である。作物のコムギ、アマ、オオムギとウルシ科のテレビンノキを除くといずれも果樹である点に特徴がある。10位以外のものをみてもほとんど実用植物であり、ユリの他花は問題になっていない。 なお、古代人は衣料用の植物に強い関心を持っていたと思われる。タク、タエ、ユフはコウゾとカジノキを含むと考えられるが、万葉集では多数登場する(タエは105回で第3位)。聖書でも衣料用のアマの登場回数が第4位である。 日本人の関心は植物の美学的側面に向けられていた点が特色となっている。万葉集と聖書は詩集と宗教書という違いがあるが、その違い以上の関心の差があるといってよかろう。 同じ詩集でも唐詩選では、登場する植物種類は少なく、草、花、芳樹といった概念的な取り上げられ方をしている場合が多いという。「国破れて山河あり/城春にして草木深し」(杜甫「春望」より)。文明度の高い唐代の詩人にとっては植物は具体的な存在でないのに対して、万葉集の詩人たちは、自然の中に没入して詳しく1つ1つの植物を知っており、それが詩の中に多数の植物を登場させることにつながったと見ることができる。 聖書と比較すると、万葉集の植物の中では、栽培植物は少ない。上位10位まででは、ウメとタチバナだけである。これら栽培植物は、いずれも中国から渡来して栽培されていたものであり、当時の先進文明である中国文化の影響によっている。 万葉集に登場するほとんどの植物は、日本原産植物であるが、中でも、ハギが最も多い。「ハギは原生林の植物でなく、自然破壊をした後に成立するマツ林などの二次林などで目だつ植物である。ハギの歌の多いことは、万葉集時代には自然破壊がすでに進行しており、まわりにハギがかなり普通であったことを示すことにもなろう。こんな自然破壊の中で日本の花の美学は最初に誕生したのである。」(中尾佐助1986) 弥生時代に北九州から近畿にかけての西日本から森林破壊が進んだ様子については図録7720で掲げた以下の図がビビッドに物語っている。英国の森林破壊の進行についても対照図が掲げられているが、「イギリスが日本と異なっているところは、完全な破壊というのがとくに南部では非常に早くはじまっているということである。これは、イギリスにおける農業が家畜をともなっていて、ニレ属の樹木などは、それ自身が家畜の飼料となって破壊されたし、一旦完全に破壊された森林は、夏の低温もあって回復することが少なかったのである。これに対して、日本の森林破壊は、ほとんど低平な土地にかぎられ、周辺の丘陵の森林は木材としてきられたあとは、樹種は変わっても、マツやスギなどの二次林が温暖な気候のもと、ただちに再生した」(鈴木秀夫1978)。 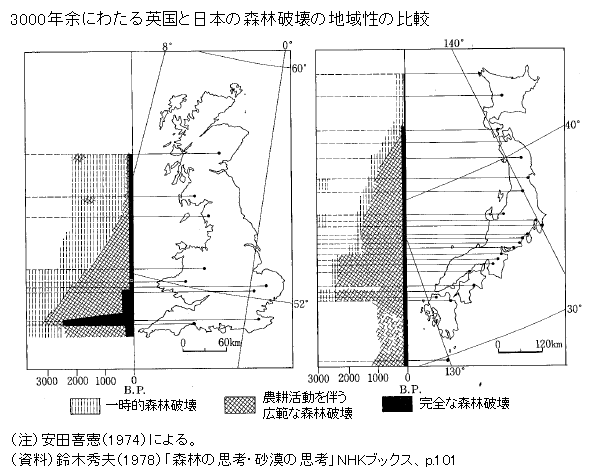 2.神道と花木
日本列島、特に関東以西の原生林は照葉樹林であり、世界でも稀なことであるが、なお鎮守の森にはその面影が残っている(図録9490参照)。ところが、常緑広葉樹の照葉樹林では、「林内は薄暗く、ジメジメした陰湿な森林である。...若葉のころの快活性もなく、また樹木が花でかざられる季節もない。照葉樹林をつくる主要木のカシの木は、...全部が花に花弁が退化している種類であるので、花の美しさは全然ないといってよい。」(中尾佐助1978a) 「しかし照葉樹林の中にも若干は見ばえのする花の咲く木もある。オガタマ、サカキ、シキミ、ヒイラギなど、日本の神道によく結びついた木は、いずれもその花がなかなかよいものだ。これらのうちシキミは平安朝以降は仏教専用になってしまった。サカキは万葉のころには常緑樹の総称であったとされているが、神道は照葉樹の枝を儀式用に用いてきたのである。またツバキは日本の照葉樹林では普通に見られるが、この花は照葉樹としては例外的なまでに大きくて立派であり、また土俗的にも日本人の習慣によくなじんでいるものである。日本の照葉樹林の中になる数少ないこうした花が美しい樹木が儀礼にとりこまれたのは、まことに当然の結果というものであろう。」(同上) 3.奈良時代から平安時代へ
奈良時代には中国原産のウメが中国の詩文の影響で詩歌に多く歌われるようになった。平安期に入るとウメよりサクラが多く詩歌に登場するようになり、ウメの歌われ方も花から香にシフトしていった。万葉集と古今集でのウメとサクラの歌の比較(上表)からもそれがうかがわれる。 嵯峨天皇が812年に神泉苑で桜の花樹をみて文人に詩をつくらせたことについて「花宴の節、此に始まる」と史書に記された。そして、ウメからサクラへの転換を象徴するのは、9世紀半ば以降、内裏の紫宸殿の前のウメとタチバナのうち、ウメがサクラに植え替えられたことである。いわゆる「左近の桜、右近の橘」のはじまりである(吉田孝1997、p.180)。 4.平安時代以降の日本人の花の美学
日本の花の美学は、平安時代から鎌倉時代にかけて、アサガオ、キク、ホテイチクといった中国伝来の栽培花きが前面に出て、特にキクの地位が上昇し、ついには後鳥羽上皇の好みから、その紋様を衣服などに付け、皇室の菊紋章の起源となった。「菊」という漢字の読みが「キク」という音読みのみで訓読みがないことからも我が国固有の植物でないことが明らかである。私などにとって、幼い頃の少年雑誌の影響で、菊の紋章といえば、戦艦大和の舳先についているイメージが強いが、当時のルイ・ビトン柄だったわけだ。なお、キクは現在では仏の供養のための花となっていることもあって生産額第1位の花き品目となっている(図録0420参照)。 そして室町時代には、国産の栽培品種が主流を占めるようになり、また江戸時代には世界的な水準に達した。 世界の花き園芸の歴史には、オリエント・ローマ・イスラム、そして欧米へ引き継がれた西欧の流れと中国・日本の東洋の流れとがある。東洋の流れの第1次センターは中国であるが、室町以降、日本の園芸文化は中国から受け継いだものに独自のものを加え、江戸時代には東洋の第2次センターとして世界最高水準に達し、欧米にも大きな影響を与えた。その特徴を箇条書きにすると以下の通りである。
なお、古代日本の花と言えば私の世代では親から言い伝えられた本居宣長の「敷島の大和ごころを人問はば朝日に匂う山桜花」のイメージから原生のサクラという既成概念があるが、どうやら違うようだ。サクラの花見の習慣はサクラの改良の進んだ室町時代以降であり、また、江戸時代になってサクラが日本独自の花であるという誤解が知識人の間で広まったため(平凡社世界大百科事典「サクラ」)、こうした遡及的な理想化が働いたのではないかと考えられる。日本のサクラは栽培品種としては独自に発達したが、サクラやそれに基づく美学はもとから中国にもあったのである。 日本の「国の花」はサクラとキクとされ、我々は、この2つの花を日本らしい花として理解している。ところが、キクは植物そのものが中国伝来のものであり、また両者とも、鑑賞文化は中国伝来のものであり、日本人は、それらを取り入れ、栽培植物として、また花の美学として、再創造し、日本文化の一部にしていった訳である。こうした経緯そのものが、日本文化の大きな特徴であると考えられる。 我が国固有の極端な短詩形式である俳句は季語なしでは成立しない。季語ランキングトップは芭蕉も蕪村もサクラである(図録3990a参照)。 5.古代地中海の食料
聖書において、果物類の登場回数がコムギ、オオムギを凌駕しているのは、当時のイスラエル、ギリシア、カルタゴなど古代地中海人の食生活では、ブドウやイチジク、ナツメヤシの乾燥果物、オリーブなどの塩蔵食品、そしてぶどう酒などの果実酒が主であり、小麦粉製品の位置は今よりずっと低かったからである。 「地中海東岸がコムギ、オオムギの原産地で、その地域はすべてムギによって農業と食生活が打ち立てられて、現在まで続いてきたと考えるのは誤りである。硬葉樹林地帯にムギ作専門といえるような農業体系をうちたてたのは実はローマであったのだ。乾燥果物のようなうまい食物を食べていた人達は、粗末であるが、ともかくもコムギ食品を食べるローマ人の生産力のすぐれた畑作の力に敗れ去ったのである。」(中尾佐助1978a) ローマ人が発酵したおいしいパンを食べられるようになったのは起源47年頃アウグスツス皇帝時代からであり、それまでは、コムギのあらびき粥、あるいは「コムギ粉を濃く煮て、粘ったドロドロのものにする。冷えてきたらそのまま食べたり、またそれがすっかりさめて餅のような塊になったものを切って、再び火で焼いて食べたりする」(同上)といった不味い食生活だったという。 聖書のオリーブには、塩漬け果実の食用とオリーブ油利用とがあった。オリーブ油について、聖書では、燈火用途と香油用途(身体に塗る)への言及はあっても、現代と異なり、「オリーブ油を料理に使ったり、食用にするという話が一度も出てこない」(中尾1976)。そもそも、古代エジプトの植物油(ゴマ油、オリーブ油、ヒマシ油)の利用もそうなのであるが、「当時の植物油は燈用、身体塗布用、工芸用、儀式用、医療用が主で、食用はあっても、ごくわずかであった。」植物油の食用としての利用は、バターや動物性の油の代用として、普及していったものであり、ここ数百年の歴史しかないという。 【参考文献】 ・鈴木秀夫(1978)「森林の思考・砂漠の思考」NHKブックス ・中尾佐助(1976)「栽培植物の世界 (自然選書)」中央公論 ・中尾佐助(1978)「聖書と万葉集の植物」(「朝日百科世界の植物12」) ・中尾佐助(1978a)「現代文明ふたつの源流―照葉樹林文化・硬葉樹林文化」朝日選書 ・中尾佐助(1986)「花と木の文化史 (岩波新書) 」岩波書店 ・吉田孝(1997)「日本の誕生」岩波新書 (2005年4月30日収録、2006年11月2日コメント加筆、2007年1月4日朝日百科中尾論考により図・コメント補筆、2008年6月9日コメント修正・加筆、2010年3月12日「古代地中海の食料」追加、3月13日「神道と花木」追加、2011年4月2日オリーブのコメント追加、2014年12月16日森林破壊進行図追加、2016年10月8日森林破壊進行図ファイル名是正、2019年3月31日吉田孝引用)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||