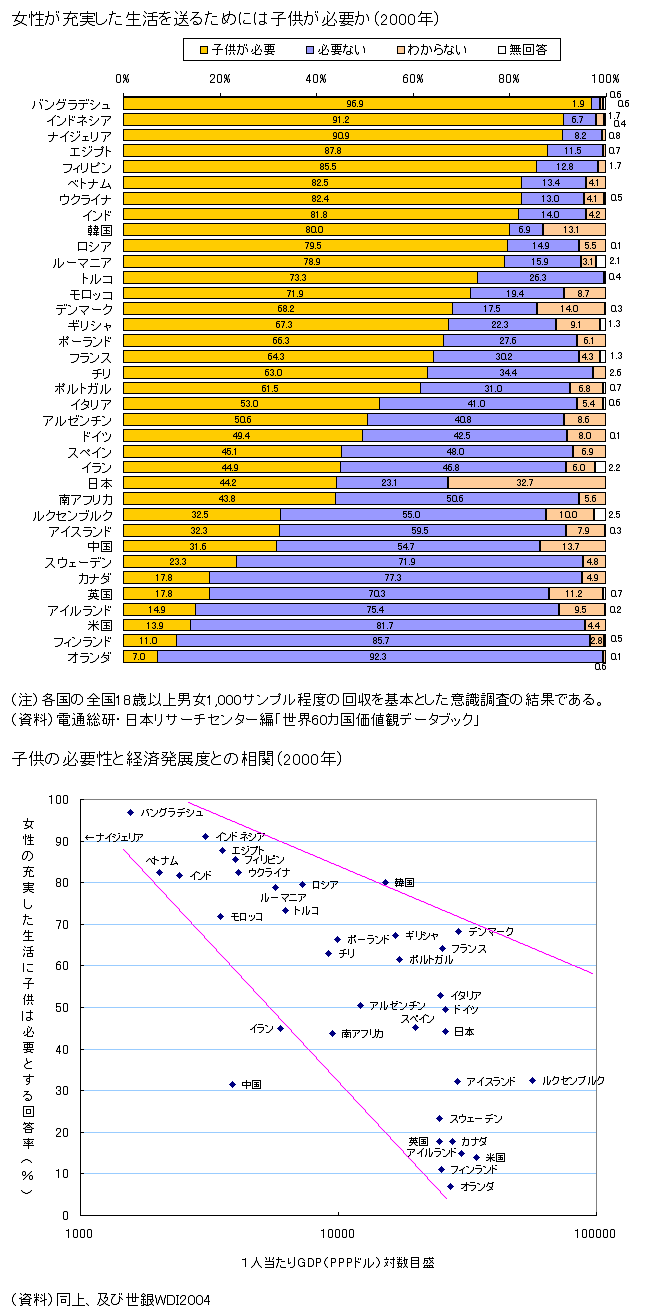
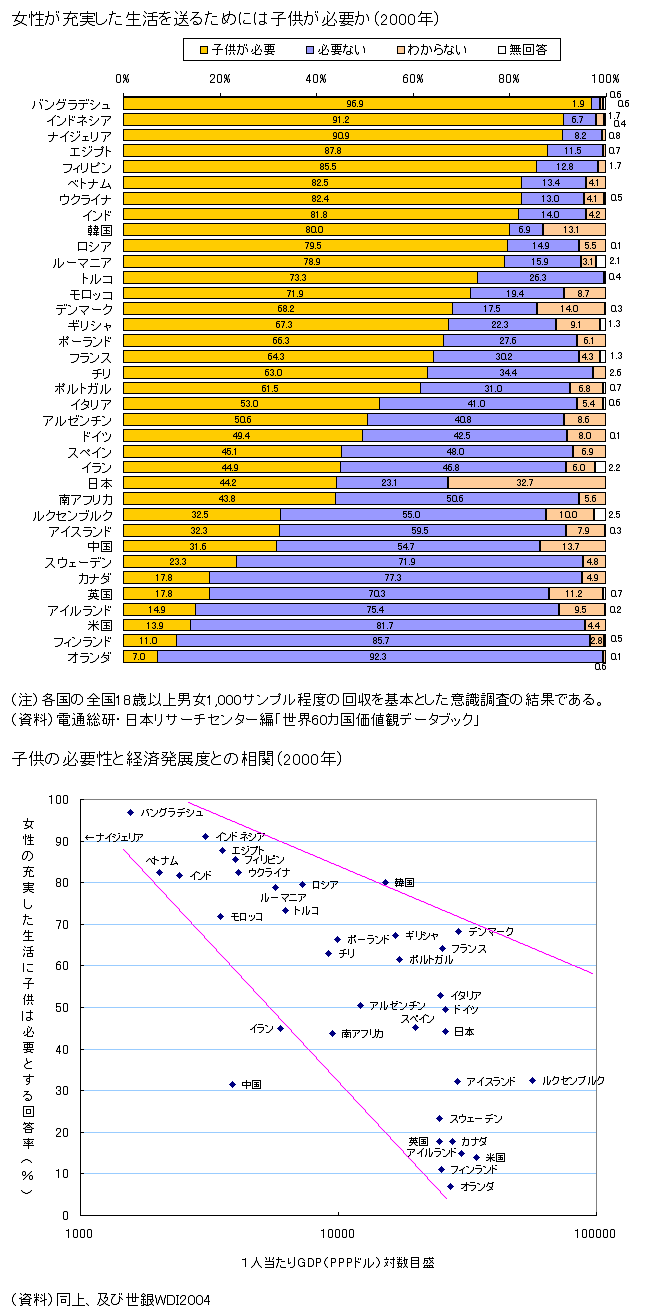
2000年に行われたこの国際意識調査によると、「女性が充実した生活を送るためには子供が必要か」という問に対する回答は国によって大きく異なっている。 図にあらわした国は、36カ国、具体的には、子供が必要と回答した比率の高い順に、バングラデシュ、インドネシア、ナイジェリア、エジプト、フィリピン、ベトナム、ウクライナ、インド、韓国、ロシア、ルーマニア、トルコ、モロッコ、デンマーク、ギリシャ、ポーランド、フランス、チリ、ポルトガル、イタリア、アルゼンチン、ドイツ、スペイン、イラン、日本、南アフリカ、ルクセンブルク、アイスランド、中国、スウェーデン、カナダ、英国、アイルランド、米国、フィンランド、オランダである。 「子供が必要」と回答した比率は、最大のバングラデシュの96.9%から最小のオランダの7.0%まで大きく異なっている。逆に「必要ない」と回答した比率は、最小のバングラデシュの1.9%から最大のオランダの92.3%まで大きな幅がある。 日本は、中間的な位置にあるが、特徴は、「わからない」が32.7%と36カ国の中で最大値を示している点である。迷っているとも、どちらとも決めかねると考えているともとれる。「必要ない」の値で並べると順位はトルコからギリシャぐらいの間に位置することとなる。なお、日本の時系列変化はページの最後にふれる。 おおまかに傾向を見ると、途上国、貧困国ほど「子供が必要」と回答する割合が高く、経済の発展した先進国ほど「必要ない」の比率が高くなっている。 そこで、下の図に、ヨコ軸の経済発展度との相関図を掲げた。これを見ると、経済発展度が高い国ほど、必ずしも子供は必要ないと考える傾向があることが見てとれる。また経済発展度が高い国では、この点の価値観の幅が大きくなることも分かる。このように変数の値の大小によって相関度に変化が生じることを私は「片相関」と呼んでいる(他の例としては図録9482、図録3001)。 貧困国、途上国では、子供が必要とする者が大体の場合多くを占めるが、先進国では、同じぐらいの所得の国でも、子供が必要かという点の意見に大きな差があるのである。オランダとデンマークを結ぶ縦に並んだ国々は、ほとんど経済発展度は同水準であるが、「子供が必要」が70%近くを占めるデンマークと10%以下のオランダとでは、まるで意見が異なっている。 英国、米国、カナダといった英語圏は、子供は必要なしとする意見が強いようだ。 また、途上国でも、中国、イランといった実効的な産児制限政策をとっている国では、経済発展度との相関において、相対的に、子供は必要なしとする意見が多いということも分かる。中国については一人っ子政策がこうした意見を生んでいると考えられる。また、イランについては、エマニュエル・トッドのように、宗教的過激国家という通念とは裏腹にイスラム圏諸国の中で、旧来型の宗教精神からの転換ともいうべき低出生率と両立する生活信条を形成している点で将来性の高い国家とする見方がある(巻末コラム「「文明の衝突」か「文明の接近」か」参照)。相関図におけるイランのはずれ値的な位置は、こうした見方を裏付けるものといえよう。 逆に、韓国は、経済発展度の割には、「子供が必要」とする者が多い。儒教の影響であろうか。1990年代以降、韓国では出生率が極端に低下している(図録1550参照)。意識と現実のギャップをどう埋め合わせているのであろうか。 この点に関する日本の意識変化についてのグラフを次ぎに掲げた。これを見ると「子供が必要」の比率は、1990年以降、傾向的に、「わからない」あるいは「必要ない」の増加に伴って、縮小していることがうかがえる。 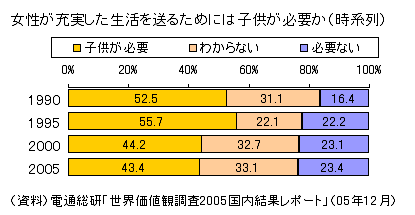
(2006年6月5日収録、6月22日時系列変化追加、2010年9月29日コラム追加等)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||