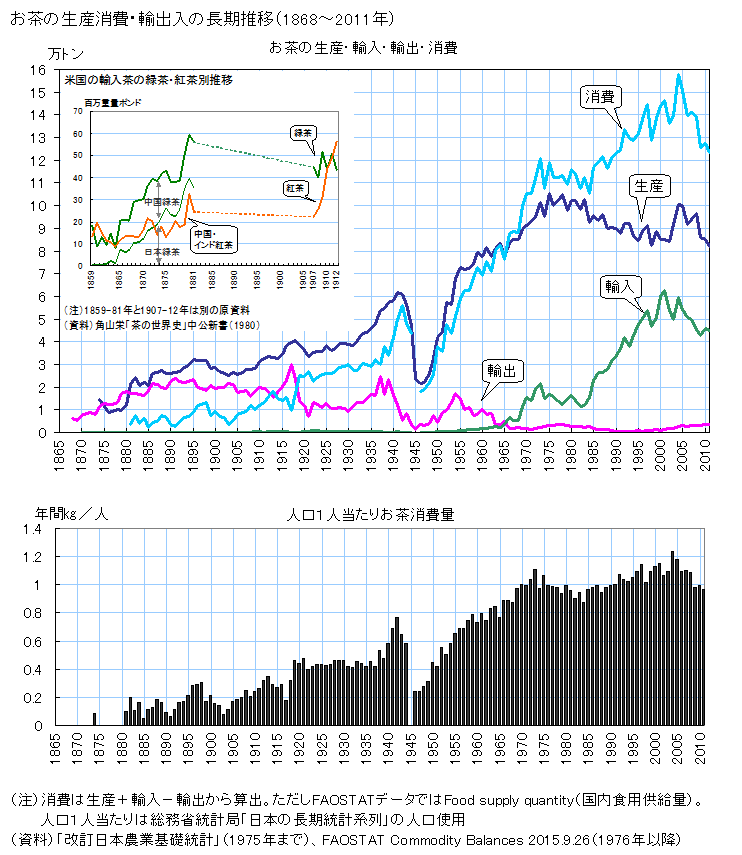
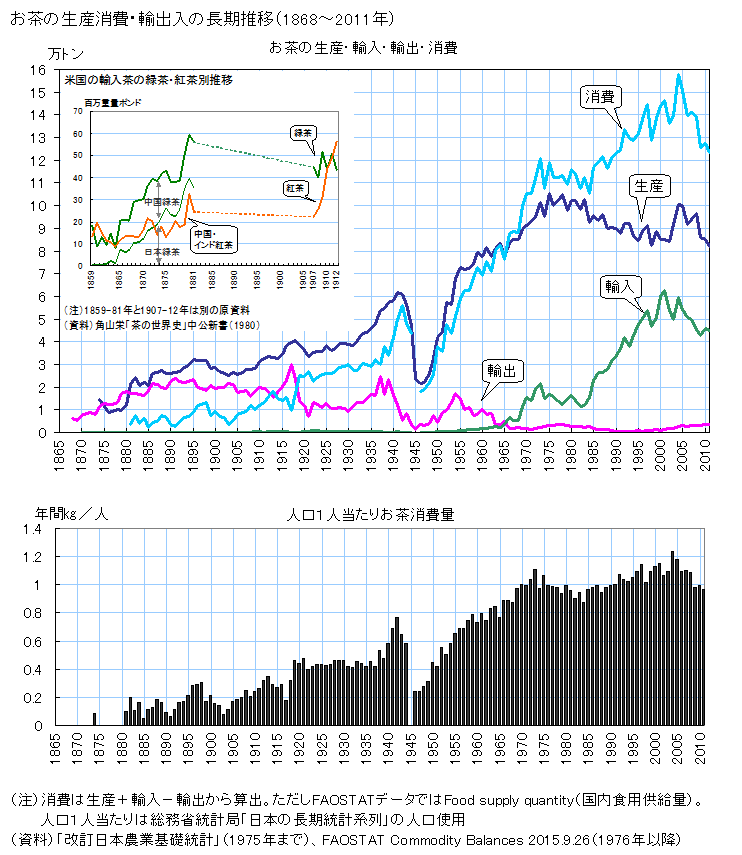
| �@ | �@ | ||||||||||||||||||
�@���{�ɂ́A�����A�����̓`���A�e�n�ɂ�����Ԓ��A�����蒃�A�������̈����K�������������A���Y���{�i�I�ɂ͂��߂�ꂽ�̂́A�A�o�����̐����ɂ����Ăł���B �@���������y����O�A�e�n�ő������܂�Ă��������́A���ȊO�̐A���t�̗��p���܂݁A�܂������̂悤�ɂ悭���܂��A��Ԃ����������Ȃ��Ŋ������邽�ߏo���������̐F�����F�̔Ԓ������������Ǝv����i���F�Ƃ����F�̂�����j�B�o�����������̂悤�ɂ��������Ė���}�{�ş����Ƃ������i�悭����ł���Ƃ����o��j�A�y�r�Œ��Ϗo���ĂP��������������������Ő����⋋�����˂Ă��������ނƂ����悤�ȃX�^�C���������Ƃ����i���F2006�j�B �@�����̊J�`��A���{�͂���Ƃ������A�o�Y�i���Ȃ��A�����ƒ����Q��A�o�Y�i�ł������i�y�ъC�Y���j�i�}�^4750�Q�Ɓj�B�����̗A�o�s��͕č������S�ł������B�u��������������āA�����A�o�̂��悻80���ȏオ�A�����J���O���ɁA10���O�オ�J�i�_�ɗA�o����Ă����B�v�i�p�R1980�j �@�p���́A18���I�����ɂ͗Β�����̕��������������A���̍��͂��łɍg������嗬�ł���i���}�Q�Ɓj�A���{�̗Β��͍D�܂�Ȃ������B���Ȃ݂ɉp���ւ̍g���A���̎d�o���͒�������ł��������A1823�N�̃A�b�T����̔����ȍ~�A�C���h�E�Z�C�����ł̃v�����e�[�V�����o�c���i�W�������ʁA���{�Ɠ��l�ɏ��_�o�c���S�̒����̃V�F�A�͏k��������A1887�N�ɂ͒����g���͔����������Ɏ����Ă���B 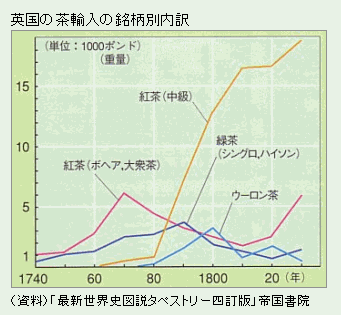 �@�č��͉p���̓��C���h��Ђ̒��̐ꔄ�⒃�łɒ�R�����{�X�g���E�e�B�[�E�p�[�e�B����Ɨ��푈���͂��܂����o�܂������āA�����R�[�q�[���D��ł����B�����ɂ��Ă��g���ł͂Ȃ������B�č��ł́u�e�B�Ƃ����ΗΒ��̂��ƂŁA�Β��ɍ����ƃ~���N�����Ĉ���ł����v�i�p�R1980�j�B�Β��͕n���K���̈����������炵���B�u���{���n�_�o���h�ՃX���R�g���L�K�^���D�D�D�k�č��O���y�J�i�_�m���؎҃n���{��������X�������^���v�i25�N���J�i�_�f�Ռi���j�B�G�h�K�[��A������|�[�̏����������u�����`�̔��v�i1844�N9���j�ł���l�����`���[���X�g������j���[���[�N����������D�Łu�Z���Β��̈��݂����̂����ŁA��悭����Ȃ������v�Ƃ��������肪����i�u�|�I�����S�W�W�v�n���������ɁAp.84�j�B �@�O���t�Ɍ�����悤�ɁA19���I�㔼�ɂ����āA���{�̐������Y�Ɛ����A�o�͊g��̈�r��H���Ă����B�S���e�n���炨�������l�ɏW�߂���ƂƂ��ɁA1869�N�ɖq�m���ւ̎m�����Y�̓��A�㒃�����J������1877�N�ɂ�500�����ւƊg�債���̂�������������ɉ������̂ł������B �@�����A�A�o���ɂ��āA�����`���̒��F���A���邢�͊䒃�A�܂����̒��Ȃǂ����ƂȂ����B���F�ɂ��Ă͒������ɕ�����ʂ��傫�����A���Ē����܂����̒��ƂƂ炦��ꂽ�肵�����Ƃ����������ʂ�A�n�悲�Ƃ̑��l�Ȓ����i���̂���Ɍ��т��Ă����ʂ�����ƍl������B1882�N�ɂ͕č��c��ŕs�����A���֎~��Ⴊ�������A����ɑΉ����邽��84�N�ɂ͒������Ƒg���{�����������ꂽ�B���{�̒��Ƒg�����A�o��Ƃ��Ă̕i������̂��ߍ��ꂽ�Ƃ����_�ɂ��������A�o�����̎Y�i�������R����������Ă���B �@�}���O���t�ɂ���Ƃ���A�č��s��ł́A�����Β������|���ē��{�������i���A�č��ɂ�����Β�������g�債���B���ɓ����̕č��ɂ�������{���̃p�b�P�[�W���f�����B  �@�������A19���I������́A�č��ɂ����Ă��p���ɒx��āA�g���̏�����X�ɑ����A����1910�N��ɂ͗A���ʂ��Β�������Ɏ������B���{���̗A�o��1891�N��2.4���g���̃s�[�N�̌�A��������̎����ɓ������i1917�N3.0���g���͑�P�����E���ɔ��������j�B���{�Β��ƃC���h�E�Z�C�����g���Ƃł́A��҂̑�K�͐����@�B���H�A�~��܂Œ��t��E�߂�L�����A�g�p���������N�[���[�J���͂Ƃ��������Y���i���������A����蓖���̗��ʋZ�p�ł͕i���ێ����g���ɗL���Ƃ����_������{�Β��͒���𑱂����Ƃ����i�p�R1980�A���F2006�j�B �@�č��Β��s��̎��k�ɔ����āA�g�����Y�ւ̎��g�݁i�Β��o�c����̓]���ɉ����A��K�͋@�B�����Y�̍\�z�A��p�ł̑�K�͌o�c�̍\�z���������j�A���邢�́A���������D��ł������V�A�암�A�����A�W�A�A���ߓ��A�k�A�t���J���ʁi�펞���̖��B�A���Áj�ւ̗A�o�w�͂���O�A���Ƒ�����ꂽ���A���������҉�ɂ͎���Ȃ������i1952�N1���g���A�o��2/3�͖k�A�t���J�����ʗΒ��ɂ��j�B �@���{�Β��̗A�o�U���Ƃ��āA������~���N������Ȃ��{���̓��{���̂o�q���s��ꂽ�B1893�N�̃V�J�S�����A1900�N�̃p�������ȂǂŁA�Z�C�����ȂǂɑR�����{�̒��X���o�������A�u���������E���_��������������Β��̐�`�́A�h�{�ƌ��N���A�s�[������g���̕��������̐�`�ɂ͂Ƃ��Ă��G��Ȃ������v�i�p�R1980�j�ƌ�����B���q�V�S���ݕĒ��ɏo�ł����u���̖{�v�i1906�N�j�������̐��_��������D�]���������A�Β��̔҉�ɂ͖𗧂��Ȃ������B �@���{���A�o�̌����ɂ��ẮA����܂ŏq�ׂĂ����悤�ȕč��j�[�Y�̍g���ւ̕ω��A�g���o�c�Ƃ̐��Y���i���A�o�q�ׂ��Ȃǂ��������邱�Ƃ��������A���{�̗A�o�z�S�̂ɂ����邨���̃V�F�A�̏k�����A1890�N��ȍ~�A���ԂɁA���D���A�Ȏ��A�ȐD���̃V�F�A�㏸�ɂ���Ă����炳��Ă��邱�Ƃ����������Ƃ���A�����̗A�o�ɗ���Ȃ��Ă��悭�Ȃ����Ƃ������R���傫���ƍl������B�܂����Y�҂̗��ꂩ��͗A�o�ɗ��炸�Ƃ������ɗ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����ʂ��傫���B �@���{���̗A�o�̕ω��ɉ����āA���{���̊��ω��Ƃ��ďd�v�Ȃ̂́A�����̊g��ł���B�吳�N�Ԃɂ́A�A�o�Ə���t�]���Ă���A�A�o�����̐����͓��������ɂ������Ɋg�債�Ă����A�N�ԂP�l������200�O�������x�̏���A���a��O���ɂ�400�O�����ɒB�����B�{�i�I�Ȑ������Y�͗A�o�����ɂ͂��܂����̂ł��邪�A���ɐ��������{�l�̐����K���ɍ��t�����ƂɂȂ����̂ł���B�����āA���A���x���������o�āA1970�N�O��ɂ�1�s�ȏ�ɂ܂ŒB�����B �@���̌�A�R�[�q�[��Y�_�������Ƃ̋����ŁA�P�l������̏���ʂ͒�����A1984�N�ɂ�880�O�����܂Ō����������A80�N��㔼����ēx�P�l������̏���͉�ƂȂ����B����̓{�g���e�B�[�̏���g��ɂ����̂ƍl������B�����̃E�[�������A�g�������̐L�сA�����āA2000�N�������ɗΒ����������v��L�������Ƃ��A�������������̏���ɂȂ����Ă���ƍl������i�}�^0480�Q�Ɓj�B �@�{�g���e�B�[�́A��y�ɂ��������߂�Ƃ����_�ł́A���Ĕ_��Ƃ̍��Ԃɓy�r�ʼn���������𒍂��ŏo���Ĉ���ł����Ԓ��̍ė��Ƃ����ʂ�����A�Z��������A���A�h���Ɛ����⋋�������I�Ɏ�����������Ƃ��č��������v�������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B �@����A�A���́A���Y��1970�N��㔼���瓪�ł��ɂȂ��Ĉȍ~�A1980�N��ɓ����āA�}�����͂��߁A���̍�������̐L�т��x���鑶�݂Ƃ��đ傫�Ȗ������ʂ����悤�ɂȂ��Ă���B �@�����Ƃ�������������̐L�т�2004�N���s�[�N�ɁA�A����2001�N���s�[�N�ɉ��~�ɓ]���Ă���B �@�ߔN�ł́A�i���ւ̍����v���A�C�O�_�Y���̔_���蓙����A���Y���ւ̃j�[�Y�����܂�A�{�g�����ɂ��Ă��A���Y���t�g�p������I�ɂ������邱�Ƃ�����A����ɍ��㌴�����̎Y�n�\�����`���Â�����\�����������߁A�A���ƌ�����荑�Y���ւ̗��ꂪ���݉�������B2006�N�Ɏ{�s���ꂽ�_��̃|�W�e�B�u���X�g�����K�����������A����}����������ɓ����Ă���ƌ�����B �@�܂��A���{�͍U�߂̔_���Ƃ����L���b�`�t���[�Y�Ŕ_�ѐ��Y�i�̗A�o�g��Ɏ��g��ł���A���E�I�Ȍ��N�u�[���ɉ����A�C�O�ł̎��i����{�H�̎��v���g�債�Ă��邽�߁A����ɔ����āA���{���̗A�o�����������\��������B���ہA���̗A�o�ʂ͋ߔN�����X���𑱂��Ă���B �@�����̈ݑ܂͋���ł���A�l���P�l������̂����̏���ʂ����݂̂Ƃ��됢�E���ς�������Ă��邱�Ƃ��l����Ƃ����̃��[�c�ł��钆���̎��v���L�т�Ɛ��E�I�Ȓ��̋����s�����N����\�����Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��i�}�^0476�A0300�Q�Ɓj�B �@��Ō��Ă����悤�ɓ��{�̂����͒������j�̒��ŕϓ]���J��Ԃ��Ă������A�ēx�A�傫�ȓ]���_�ɂ����������Ă���̂����m��Ȃ��B �i�Q�l�����j �p�R�h�u���̐��E�j�\�Β��̕����ƍg���̎Љ� ���F�����u�����͐��E�������߂��� �i2006�N9��5�����^�A2015�N9��26���X�V�A2019�N2��28���|�[���p�j
�m �{�}�^�Ɗ֘A����R���e���c �n |
|
||||||||||||||||||
�@